※この記事は批評、評論であるため1つの解釈です
うたまるです。
養老孟司といえば解剖学者にしてバカの壁の著者で有名な東大出身のエリート言論人、YouTubeやTVでも人気の有識者。
今回はそんなエリートの思想がもつ限界点を論理的に提示し養老孟司を超える心理学を提示します。
このようにいうと、お前ごとき一介の心理学のニワカオタクが、スーパーエリートの養老孟司の考察の限界を指弾などできるのか?と思う方もいるでしょうが養老孟司は解剖学者であって人間心理については僕のようなオタクに勝つことは不可能なので簡単にできます。
僕がどうやっても養老孟司に解剖学で勝てないように、養老孟司がどうあがいても僕に人間心理の洞察で勝つことはないと思ってます。そんなにオタクやマニアという人種は甘くないのです。
というわけで今回はアンチ近代としての形而上学批判をなすデリダの音声中心主義批判、エクリチュール論、東浩紀による後期デリダの郵便的などの論考を念頭に養老孟司の最新の考えの限界を理論的に提示します。
いうまでもないことですが揚げ足取りをする意図はまったくありません。そうではなく養老思想の全体が認識論的誤謬によって隘路におちいっていることを提示し、より建設的な議論の道筋を示すのが目的です。
※今回の記事はかなり難易度高めです
養老孟司の現在地
上の動画をベースに養老孟司の思想を分析したい。
この動画は今の養老孟司がどのようなパラダイムを前提にして心を考察しているかもっとも分かりやすい。とりわけ、その問題点が浮き彫りとなっている。
さて、今回取り上げる養老思想の要諦を示そう。
行動主義心理学に傾倒
その理由は、役者をつかって喜怒哀楽と表情を緻密にみすびつけ、そのうえで表情が喜怒哀楽のうちどれを指示するかを当ててもらう統計実験をしたところ、個々人によりまったく表情の解釈が異なったため。それゆえ、喜怒哀楽といった心はまったく分からない(表情と感情の同一性がない)、と結論し、心の研究は客観的に記述可能な行動の記述によるしかないだろう、と考え、行動主義に注目するという。
ただし個人をとらえるときには行動主義の統計では問題があると補足はしている。
後述するがこれは現代分析哲学、ポストモダンらの言語分析で嫌というほど問題になった基礎的な議論の再現であり、とっくに結論が出ている話なので後にきっちり解説する。この考えには多くの問題があり、誰かが批評しないといけないと思う。
個性や独創性とは非独自的、非個性的であり存在しない
養老孟司は多くの場で、個性、独創については身体が個性であるという留保をつけたうえではあるが、個性は存在しないという。
その理由は、もし独創的なものが本当に独創的=単独的であれば誰にも理解できない。アインシュタインの理論も他の人が理解可能で一般的、普遍的だからこそ評価されている。よって個性や独創というものはない、という具合だ。あるいは個性的ファッションといったってそれが受け入れられるには既存のルールや枠に従っているともいえるだろう。
これは典型的な帰謬論による論証でありデリダの脱構築の手法や哲学的懐疑主義の手法をもちいたレトリックとなる。
今回の記事では行動主義への移行、個性の不可能性の提示の養老思想の2つが実はまったく同じ認識論的誤謬によって結論されていることを論証してゆく。
行動主義と養老孟司
行動主義とは心理学派の1つで、心を客体に還元し、客観的に記述するもの。
したがって喜怒哀楽といった客観的に観測できないもの(主観、心)は無視して、客観的に観測可能な行動を記述し、その統計をとることで心を分析する。
これは言語論に置き換えると、言葉の意味を外的客体や表象思念に還元する意味の還元主義に相当する。
つまり行動主義とは、主体と無関係に記号や記号の差異体系に言葉の意味が内在すると見なし、それにより記号の外部にあるコンテキストを不問とする現代言語学、英米分析哲学のパラダイムにある。フレーゲ、ラッセル、初期ヴィトゲンシュタイン、オースティンなどはその典型だ。
つまり、行動主義と形式論的言語分析とは密接に対応しており同じ認識論的パラダイムを前提とする。
養老孟司の限界点
心の基礎論
ではさっそく養老孟司のどこにレトリックが隠されているか見てみよう。
まず、彼が引用する喜怒哀楽と表情(行動)との一致を確認する実験について。
この実験は言語論でいえば意味の実体化、イデア的本体化に相当する。怒りや悲しみという感情がそれ自体として対象的、客体的にあり、その本体としての喜怒哀楽を行動記号(表情)の意味とする。表情というシニフィアンが喜怒哀楽を指示すると考えるわけだ。ここでは表情記号は指標機能をもち、指示される対象(喜怒哀楽)が言葉の意味と見なされる。
このとき表情=シニフィアン、と喜怒哀楽は一対一で対応する。このような前提をおいて、心を記号に還元し分析しよう、というのが養老孟司の参照した実験の論旨である。
※このスタイルは真理の鏡像理論やヴィトゲンシュタインの写像理論などに典型される
この実験では実験心理学的、形式論理的に心を客体化して、分析しようという目的意志がある。
※なぜ近代にこのような目的意識が学問的潮流をなしたかは割愛する、これについては竹田青嗣の本に詳しく書いてある
さて、そのため養老孟司は喜怒哀楽を独立した表象として措定してしまっているがこれは間違い。
喜とか努とかはそれ自体としてあるのでない。感情の解釈記号(喜怒哀楽)とは差異の体系であって、だから喜怒哀楽は物、表象、イデアではない。
※イデアとは理念的、観念的実体のこと、たとえば正三角形とか一とか。正三角形はその語から誰もが同じ図形を想起するからイデア的な同一性=反復可能性がある、という
余談だが喜怒哀楽は明らかに心理学的分離と関連しているので主体の構造化と対応させないとまったくその本質を捉えることができない。喜怒哀楽について普遍的な条件を求めるなら現象学を行使するしかないが、養老孟司は現象学以前の認識パラダイムにあり、デリダ的相対主義の壁に阻まれ考察を前進させることができなくなっている。
本題に話をもどすが、まず喜怒哀楽、心、あるいは意味と呼ばれるものは、対象や物体や客体ではない。観念的表象でもない。
また心は脳などの物ではない。
これについては当ブログ記事のシミュレーション仮説の記事などを参照して欲しい。そこでクオリアとしての心について、詳しく解説している。
心は関係であり、対象を対象化する力である。これを力への意志とか気遣い、欲望と呼んでもよい。心とはいわば主体性のことで能うということ、能動性のこと、欲望のこと。
だから空間的なモノ、対象ではなく時間的なコトに属するのが心である。しばしば心は存在しないというアホな論客がいるが、それは心を事物表象や対象と混同することで生じる誤謬である。
そもそも心は対象ではないから対象として措定することは不可能。
それでいて言葉は対象ではないところの、つまり客体ではないところの主体を心とか私と名付け、対象化してしまう。
これにより非対象の心(関係)とシニフィアン(名)とは差異が同一される構造をなす。これを存在論的差異と呼ぶ。
それは心(時間)とモノ(空間対象)との差異である。
ちなみに言語学における意味の観念論(主観主義)VS実在論(客観主義)の問題も意味を観念表象に還元する間違った発想から引き出されている。
さて心の基礎論についてはきりが無いのでこのくらいにして、次に還元主義的、イデア的な意味論をとる養老孟司の問題の核心に迫ろう。
養老孟司とデリダ
さて、本当は近代哲学(観念論)への唯物論者による観念論的形而上学批判の誤謬、デリダの形而上学批判、フッサール批判、音声中心主義批判、エクリチュール論、後期ヴィトゲンシュタインの形式論理主義批判、ヘーゲルの哲学史講義などについて解説したいのだが、長くなりすぎるので割愛し、結論のところだけを簡潔に示す。
※これらについては竹田青嗣の『哲学的思考へ』に網羅的に説明がのっている
養老孟司が喜怒哀楽などの実験から心を分からない、というのは背理である。
これは心の本体論といわねばならず、いわば養老孟司はカントの物自体を前提とする世界観を無根拠に絶対化し前提している。
※カント自身は相関主義的に普遍認識を目指した哲学者で評価できるが物自体モデルには問題もある
ここに全ての問題の根っこがある。
カントは理性批判において、形式論理的分析を徹底することでアンチノミーを取り出し、形式論理思考=理性には絶対的な限界があることを示し、この限界点としての物自体の提示を介して、スコラ哲学的形而上学を批判した。
養老孟司も、心を客体化、表象化、本体化したうえで、実証主義的な観点から、その本体への到達不可能性を提示し、だからこそ、本体=心は分からない、あるいは心は存在しない、という結論を引き出す。
これは認識問題におきかえるとわかりやすい。つまり養老孟司は客観(行動)のみを実在として措定し、そのうえで客観(心)は存在しない=到達不能、という結論を引き出している。
これはジャックデリダの思想のコピーであるから確認しよう。
デリダの声と現象におけるパロール批判は、表情(記号)には感情(表現者の意)は存在せず、客体記号としての表情と、その表情を受け取る人だけがあるという。
このモデルによって表現記号がいかに表現者の喜怒哀楽=意を伝達するかという形而上学的問題設定を解体すること、ここにデリダの狙いがあった。
※形而上学とはアリストテレスに起源をもち中世では神学と結びいた哲学の形式の1つで世界の究極的原因や真理を解き明かそうとするもの、そのため神という世界の絶対根拠への問いも形而上学となる、また形而上学では二項対立と形式論理的な論理学思考が要請される。なぜならイデア的でスタティックな真理をとりだす場合、原理的に論理学的論理思考が要請されるからだ
つまり表現者の意(喜怒哀楽)を本体的、客体的に措定し、それが言語記号(表情)と一致すると考える場合、これは形而上学的野心と結びつく。つまり言語認識が客観的な相手の意や感情に一致することになるので、ここでは認識と客観の一致が生じることになる。
しかし認識と客観は、一致しない。これについてはいかなる自然科学も反証可能性を放棄できないことを考えよう。もし自然科学的認識が、客観的事実に一致するなら反証可能性は必要ないことになる。
あるいは、誰も自らの身体的な主観、精神的な主観の外にでることはできない。認識像としての客観とは意識現象のうちで主観的なものと客観的なものが分離し信憑されているに過ぎず主観の外にあるのではない。この現実が夢でないことを誰も論証することはできない(映画マトリックスのようになってないとは誰もいえない)、ということを考えればよく理解できよう。
もし客観と認識が一致するならば、世界の客観的真理の記述は可能ということになる。だから形而上学では主客の一致が絶対的に論証されねばならない。つまりたとえば、私以外の人は私の言いなりになるのが絶対的な客観的正義であり真理であるという形而上学的独断論があったとき、これを絶対的真理として証明するには、この考えが客観と一致することを示す必要があるわけだ。
このときそんなこと証明できない、とその一致の論証の矛盾を取り出して形而上学的独断論を砕くのがポストモダンや懐疑主義の狙いだった。
そんなわけで形而上学的独断論の実現には主客の一致の証明が要請される。
以上から言語は話し手の意と一致できないという発想はデリダの形而上学批判のための拠点となる。
まとめよう。
養老孟司は感情と表情、意味と記号は一致せず、感情は不可能で分からないと考える。
これによって心はないという方向にむかい、行動主義という記号客体だけを分析する心理学に傾倒する。
このあり方はデリダのフッサール批判、音声中心主義批判とまったく同じである。ポストモダニストもまた言語には発語主体の意は存在しないと考え、言語を客体として形式論理によって分析し、意味のアポリアを取り出す思弁的遊戯に耽ることとなった。
よって
ポストモダニスト⇒言語の形式論理主義、養老孟司⇒行動心理学主義は同じなのだ。
つまり客観的なものや記号(行動)しかないと前提し、そのうえで客観(心)には到達せず客観(心)は不可能であり存在しない、というニュアンスを含む。
養老孟司のいう心はカントでいう物自体やラカンの欠如した主体に近い。だから心はないという養老孟司の考えは心は客体であると仮定し、その仮定が破綻する状態を参照して心はない、と結論している。心を不可能な物としているといってよい。これは50年代ラカンの欠如としての欲望論の変奏ともみなせる。
※ただしラカンは50年代の時点でも存在論的差異(フリュストラシオン)をとらえており、一概にはいえない。また50年代ラカンでは欠如が客観系である象徴界の根拠と洞察されており養老孟司よりも数段レベルが高い
表情と感情の不一致の謎
養老孟司が引用した表情と感情の実験のレトリックを解説する。
まずコンテクストなしの表情はその意味(感情)が分散してしまい収束しない。こんなこというまでもないことなのだが、養老孟司レベルでさえ理解できてないようだから小学生でも分かるようにオリジナルの解説をする。
※追記:厳密には以下の吊り橋効果の構造は、原ドキドキ感(初期直観、思念、行為的感覚)⇒原ドキドキ感の自己了解としてのドキドキ感⇒ドキドキ感の意味としての恋愛感情、ハラハラ感となります。ドキドキ感の場合、それは他者性(予期せず生じる性質)が強いので自己内で他者の表現としてドキドキ感を受け取りコンテキストからドキドキという記号の意を他者の意として信憑了解する、というような構造があるかもしれません
つりばし効果を考えよう。吊り橋効果とは吊り橋を渡るドキドキ感が恋のドキドキ感と錯覚されて恋愛感情が誤認される現象だ。
吊り橋効果が明らかにするのは恋のドキドキも吊り橋のドキドキも同じだということ。つまりハラハラ感と恋愛感情は、表現・表情としては同じドキドキであり差をもっていない。では恋とハラハラ感は何が違うのか。
それは状況コンテキストである。コンテキストによって同じドキドキという記号(生理的反応)が恋愛を意味したりハラハラを意味したりする。だから解釈された感情とか意味というのは、コンテキストに相関してあるのであって表情(記号)それ自体に独立して内在しているのではない。たとえばもし一人で吊り橋を渡ったなら吊り橋効果は生じない。吊り橋効果の発生条件は、異性と吊り橋を渡るという状況コンテキストなしにはありえない。
よって吊り橋効果とは記号であるドキドキが誤読されているのではない、コンテキストの側が誤読されて生じているのだ。つまり感情や意味の多義性は記号にあるのではなくコンテキストの複数性や関係における自己の了解可能性、存在可能性にある。
養老孟司のいう文化によって喜怒哀楽がないという話も、それは文化コンテキストの差異のために表情の意味が変っているというだけの話に過ぎない。いい加減、心を客体化する間違った考えは本当にやめて欲しいというのが本音だ。
ヴィトゲンシュタインの写像理論や要素命題の論考が無効となった理由もこの一点に集約できる。感情(心)とはまず物ではない、それは関係としてのコンテキストによって限定される関係それ自体の自己了解である。
そもそもゲーデルの不完全性定理からも明らかなように、感情と表情を一義的に結ぶことは不可能だ。この場合、感情の多義性のアポリアが生じる。そしてそこから言語規則の無限遡行(ルールのルールの・・・)のために意味を確定するコンテキストを厳密規定することはできないという結論が引き出される。
この議論は前世紀末の言語論論争でアホのように繰り返されており、養老孟司はその議論を知らない。
補足しておくと言語の意味とは、最初の思念や直観が表現にもたらされ、その表現に収束するとき、その表現との一致に疑義が生じるときに問われ生じるのである。初期の直観や思念は言葉の意味ではありえない。
たとえばそれはどういう意味ですか?と問われることで、表現と初期思念や直観とのズレが生じて、そのズレを補正するために言語表現の意味が別の言語によって紡がれることになる。
だから、むしろ初期思念は言語表現によって意味づけられているというべきである。
吊り橋効果の例を考えてもこのことはよく分かるだろう。ドキドキそれ自体は一義的な意味(解釈)を持たない。これはシニフィアンとシニフィエの結びつきに必然性がないということでもある。結びつきを規定するのはコンテキストだ。
だから、ある言葉の意味とは、表現と意との一致の信憑が崩れ、そのズレが意識されて生じるのであり、したがって言語の意味とは一致の信憑関係の弁証法的運動にある。よって意味(解釈された感情)をスタティックな実体として考えることはできない、そのことは意味の多義性のアポリアからも明白である。
※補足のおまけ:事物の意味は、道具的存在として事物が対象化されることで実存の連関構造として、自己の存在可能性の了解として生じるが、言語の意味もまた、言語表現が関係企投的な道具的存在として発話され、そのことでズレの再一致へと向かう言語的な意味を生じうる。だから意味は自己了解や一致の信憑の運動である
この構造の本質は養老孟司が参照する表情と感情の実験心理学にも当てはまるだろう。
養老孟司(デリダ)と心のアポリア
いよいよ養老孟司の心のアポリアを解き明かそう。
とそのまえに改めてここまでの内容を要約しておく。
まず養老孟司は、心を客体本体としてそれ自体で存在するモノと前提し、次にその本体としての心に行動や記号が到達しないことを論証。
これにより心の不可能性を主張し、心を到達不可能とか、あるいは存在しないと主張することで、行動主義を評価する。つまり行動記号には表現者の感情(意)は含まれない。そして世界には記号行動しかない、だから行動分析をするのが正しいという理屈。
このやり方はデリダの現象学批判と同じ手法であった。
デリダも記号には発言者や著者の意はないといい、これを作家の死と呼ぶ。そうやって言語記号から発言主体の意を抜き取り記号を客体的に分析し、そこから意味の一義的確定や意味を確定する言語規則の規定の不可能性を暴き立て、その不可能性を繰り返すわけだ。こうして心は分からない、というレトリックが展開される。
しかしこれがトリックであることは前項で解き明かした、つまり行動表情から感情が一義的に確定できないのはコンテキストを無視して表現行動を客体的に分析するために生じる白痴どもの仮象に過ぎない。
養老孟司は客体としての心本体を前提に、主観と客観の不一致を証明して、客観はない、といっている。しかも主体(心)を客体化(イデア化、表象化)してその不可能性を暴くことで、同時に客観しかない、モノしかないといってるわけだ。
この主張は論理的に成立していない。背理である。そもそも心は客体ではなく関係であるから、関係を客体化できないのは自明である。
つまり客体化すると感情は状況コンテキストという相関性・関係性を喪うのでコンテキストが消え去り、これにより意味の多義性のアポリア=感情のアポリアがねつ造される。
そもそも心がないというのと心は存在者ではないというのは違う。この違いが理解されていない。
これは客観はない、と背理法で論証して、客観的認識の不可能を示すデリダの反復である。
だから不在という資格で客観が実体化している。心がないというのと心は存在者ではない、が違うように、客観がないというのと客観は主体から独立した客体・客観ではない、とは異なる。この異なりがデリダや養老孟司ではまったく理解されていない。
その意味でこれは否定神学的形而上学でしかない。哲学的にいえばカントが物自体に貼り付けた神という名のラベルをペリッと剥がすのがデリダであり養老孟司といえる。
さて心をないといっても意味が無い、それでも人は心を確信し心と心ならざるモノとを日常において峻別しているからだ。だから、では心とよばれるもの、客体とされるモノは本当はなんなのか?を問わねばならない。
ここで念のため補足すると養老孟司のいう、心は個人的なもので僕たちが感じる他人の心は全て思い込みに過ぎず、相手の心は絶対に分からないという主張は背理だということ。そもそも相手の心は自己の主体と無関係にある客体ではないから、相手の心は分からない、というのは養老孟司のいう意味ではまったく成立していない。
たとえば心が通いあう瞬間、相手は怒っているなと確信する瞬間が、日常生活では当たり前にある。このような超越(他者の心)に対する信憑のことを客観的な相手の感情と僕たちは確信する。だから客観の実際の条件構造と、一般的な客観概念の条件構造とにズレがある。このズレを理解せず、一般的な客観に対する認識(誤認)を正しいと思い込んでるから、養老孟司は行動主義だと言い出しているのだろう。
前述したように、現実が夢でないことの論証はできない、けど夢と現実を日常では区別してるわけだから、ポストモダニストが前提するような客観は、ないとか不可能という意味においてすら存在していない。あるいは、客観とは内的な信憑によって成立しているもののことである。
であるから相手の心は信憑がある限り理解されている。しかしそれは客体実体ではないので信憑・確信という枠を出ることがない。だから客観的な相手の心には訂正可能性があるわけだ。
そしてその確信条件というのは行動主義によっては実際的にも原理的にも取り出すことができない。普遍的な確信条件は現象学によってのみ取り出せる。
現象学は、客観や心がないのであれば、しかしそのように呼ばれ識別されるものは実際には何なのかを問い、これによって認識論的誤謬を解消する運動である。心と呼ばれる対象とは、対象化された対象ならざる関係である、というのが現象学的帰結。
養老孟司とデリダの問題をクリアにとらえるため、自由意志について考えよう。あらゆる想念はそれ自体として自生的でありヴィトゲンシュタインでいえば命題は命題自身に言及できない。したがって私が私を決定することは理論的にできず、自由意志は存在しない。
※自由意志がないことの論証は当ブログの自由意志に関する記事で小学生にも分かるように解説しています
このように言うことは簡単である。しかし、これは現実には自由意志とは私が私をコントロールすることではない、というだけで、自由意志がないというのは無効である。
自由ということの認識と実際の自由という体験構造とに差異があり自由への認識は誤認を孕む、そのように考えねばならない。だからここで相対主義的に自由意志がない、というのは、認識と体験とが一致しているという前提が、つまり主観と客観とが一致するという願望が潜んでいる。主客の一致を否定するデリダであり養老氏のその否定思想(不一致思想)それ自体のうちに一致の絶対的肯定と形而上学的野心とが既にその思索以前において、その思索に内在(痕跡)しているのだ。
養老孟司の個性論と心
さて、まだ養老孟司への批評にピンとこない読者もいるだろう。
なので、ここで養老孟司の個性論が既に指摘した、養老孟司の心の論と相同性があることを論証しよう。
あらてめて養老孟司の個性論を要約する。
個性や独創について、そう呼ばれるものは一般的であり単独的でない、よって個性や独創は存在しない。
これは心はないとするのとまったく同じ懐疑主義的論法でありレトリックに過ぎない。
前項の赤文字のところを読めば分かるように、ここでも認識と体験の一致が前提され、そのうえでこれが一致しないことが背理法で間接論証され、個性はない、という否定思想を形成している。
これはまったく背理としかいえない。不一致への拒絶としかいえない。
※これをラカンの排除からとって認識レベルの排除と呼んでもいいかもしれないが、ラカンはこの現象を想像的誤認と呼ぶ
だから個性も独創も単独的なもののことを言っているわけではない、それは誤認で、独創ということの条件(体験)は素朴な単独性とは別にある。そしてその条件は僕たちが凡作と独創的傑作とを区別する理由を了解的感覚のもとに取り出せるからには、現象学的に取り出せるのである。
もちろんそのように取り出された条件内容(本質観取)は信憑判断において普遍性をもちうるし、他者との対話によって現実的な普遍性を実現してゆく。つまりそれは訂正可能性のある客観認識として成立する。現象学的に客観の構造を理解する限り、現象学的な合意のもとにとりだされた普遍認識は可疑的である客観認識と等価だといわねばならない。
あらゆる事物の客観認識は弁証法的運動にあるのであって、スタティックな客観認識は、ないという意味においてさえ存在しておらず、それは誤認に過ぎないということ。
まとめるとこの一言につきる。
あと、現象学では条件のスタティックな真理はもちろんとりだせない、条件の確かめ可能性があるということ。つまり真理やそれ自体としての本体は存在しないという意味においてすらない、ということ。
おまけ:ラカンと現象学
おまけなので、少し専門的な説明をすると強迫神経症における幻想の引力圏(想像的誤認)を突破できずに、形而上学的誤謬に陥っているのがデリダと養老孟司だと考えられる。
ここまでを読むタフな読者にはもう説明はいらないだろう。
養老孟司の個性批判と行動主義とはまったく同じ認識論的パラダイムによって必然的に帰結していると考えると体系的に養老孟司の主張を理解できる。
養老孟司のパラダイムは突き詰めると、集団主義と個人主義とは反対概念(排中律)であり、個人主義者は集団を破壊するから、集団主義でいい、というメチャクチャな結論にも帰結しかねないと思う。反近代思想をポストモダン的な認識パラダイムから引き出すとこういう偏った危険な政治思想に直結しやすいと思う。
たとえば極端な古典主義なども個人と集団、近代とプレモダンといった形式論的二項対立と排中律によって、極端な結論に結びついていると考えられるだろう。
行動主義、形式論理主義(論理学)では実存の弁証法構造を捉えることができないので、人間の生き方や社会について、この考えで意見しだすと極端な結論がでてくる。
余談だが東浩紀の郵便的における複数性の欠如による象徴界モデルもまた、否定神学構造に絡め取られていて不十分と思う。
つまり単数性と複数性の形而上学的二項対立が要請され、案の定、排中律に頼って複数性を絶対化してしまう。ハイデガーの本来的、非本来的にあるような形而上学性があると思う。
そうではない。単数性というのはそもそも複数性によって可能となっている。騙されない者(誤認をひきうけない者)は彷徨う、とラカンは言ったが、だから単数性という誤認を誤認として受け入れる複数性の態度が必要なのだ。
またヘーゲルは僕のにわかなレベルの理解によれば、排中律を超える本質的哲学者の代表であり、昨今の白痴どもによるヘーゲル批判は無効である。
今回は割愛したがヘーゲルの哲学史講義の内容は素晴らしく、デリダの一歩先を行っていると思う。もっとも僕のヘーゲル理解の半分は竹田青嗣のうけうり、もう半分はユング派のうけうりなのではあるが。
ともあれ70年代ラカンにおける、父の名とはそれなしですむもののことである、は今回の議論では見逃せない。
この言葉の真の意味は僕の解釈によると、否定神学的な単数的欠如は、それ自体、存在しない誤認=幻想のことである、という意味であり、誤認としての単数性を複数性により支えようという狙いがある。
僕の理解では、あきらかにラカンの女の式は排中律を突破しヘーゲルへと接近している側面もある。
また現象学派に対するラカンの優位は、僕のにわか理解によると幻想における客観概念の誤認の構造を解き、これによりどうしてデリダのような近代批判者が登場したかを、近代それ自体の構造から取り出せる点にある。
つまり現象学では誤認を正すことでそれを引き受け、普遍認識を支える認識を開くことが可能となるが、後期ラカンではなぜ現象学が不当に否定されねばならなかったのかをカントやヘーゲルに見られる近代主体構造それ自体から引き出すことができる。
※僕はラカンを知る前から独自に近代に内在する反近代の構造を抽出していたのだが、ラカンの考えが僕のその抽出を理論武装するのに使えると気づきラカンを利用させてもらっている
といってラカンのが現象学より優れるというつもりはない。むしろ僕は逆だとすら思う。後期ラカンにしてなお現象学的な差異(今)の概念がもつ意義が取りこぼされ、シニフィアン主義を克服し切れていないからだ。ラカンの精神分析には明らかに欠点がある。
終わりに
ちょっといつもの記事よりハードになったかもしれない。ちゃんと解説しようとすると、いま僕が読んでいる本、竹田青嗣の『言語的思考へ 脱構築と現象学』の話を悉くしなければならなくなり、まだ二周目を読んでる途中なので、それはなかなか難しい。
この本は、僕が知る限り最高の哲学書である。この一冊を読み込めばポストモダンについての本質や言語学の問題から現代社会の問題まで一気に分かる。
ちなみに、この記事のオリジナリティはデリダの思想は後の認識と体験との一致の形而上学である、という指摘にある。
なんとかこの考察で記事としての一定のクオリティを維持できたと思いたい。
説明の仕方が定まらないまま、適当に書いたせいで分かりにくい記事だったかもしれない。
行動主義の問題などはいくらでも指摘できるし、統計主義の弊害もいくらでも論じられるが、ありきたりな基礎的議論はつまらないから割愛した。
ところで、いくらなんでも、もう少し言論のレベルをあげないとこの国はそのうち解体する気がしなくもない。さすがにどう考えても、この国の言論はレベルが低すぎると思うのは僕だけだろうか。
YouTubeを見ていても、政治や社会について騙る言論人よりマニアックな映画好きによる映画評論とかのが知的レベルがどう聴いても高いのである。
この記事で示し解消した認識論問題を解決しないと、どの社会問題も対症療法的にしかアプローチされず、本質的には何も解決しないと考える。また僕が理解してる程度のにわかな理解を国民の三割がすることができればそれだけで、社会問題は本質的な解決の運動を始めることができるという確信が僕にはある。


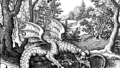
コメント