こんにちは!うたまるです。
※この記事は攻殻機動隊SACのネタバレを含みます
ここ最近は飲食テロやバイトテロが増えていますね。ところで、こうした飲食テロって攻殻機動隊S.A.C.のSTAND ALONE COMPLEX(笑い男の模倣犯)にそっくりではないでしょうか?
S.A.C.の世界で笑い男事件が起きたのが2024年なことを思うと感慨深い。
2002年公開の『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』は今の時代を20年も先取りしていたように思えます。こんな世の中だからこそ、批評性が高く哲学的で知られるS.A.C.をしっかり理解することには意義があるかも。
というわけで、こんかいは攻殻ファンであるぼくが、カルト的人気を誇る神山健治監督『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』を解説・考察。
この記事は他ではけっして知ることのできない、それでいて精度の高い独自の解説をしています。なので本当に攻殻機動隊SACが好きという人にこそ読んでいただきたいです。
またNetflixで2022年より配信されている『攻殻機動隊 SAC_2045』は攻殻機動隊SACの続編としてつくられており、攻殻機動隊 SAC_2045を楽しむ上でも『攻殻機動隊S.A.C.』の理解は欠かせません。
そのためこの記事を読むことで神山監督の攻殻機動隊シリーズの深さが体感され、より楽しむことができるようになります。
- 神山健治監督の狙いと思想、歴史観
- 攻殻機動隊S.A.C.のメッセージについて
- スタンドアローンコンプレックスの具体的な仕組み
- 笑い男とタチコマ、二つの物語の交差について
- S.A.C.の物語構成の基本となる三者構造について
- タチコマはいかにゴースト(個性)を獲得したのか
- 笑い男が書き加えた「or should I ?」の意味
- 並列化の果てに個を獲得するための好奇心について
- 攻殻機動隊S.A.C.シリーズが本当に好きだという人
- 我こそは攻殻機動隊S.A.C.を知り尽くしていると思っている人
- ググった内容をまとめただけの記事にうんざりしている人
- S.A.C.の解説や考察をしているブログや動画をいくつも見てきた人
- 『攻殻機動隊 SAC_2045』に興味がある人
- 神山健治監督が好きな人
- 攻殻機動隊の哲学に興味がある人
- 映画評論は町山智浩が好きだという人
- 攻殻機動隊に興味が無い人
- あまり頭をつかいたくない人
- 『攻殻機動隊S.A.C.』を全く知らない人
S.A.C.の特徴とポイント
ここではSACの特徴と物語を理解する上でのポイントを簡単に整理します。
STAND ALONE COMPLEXと各話の構成
SACの特徴は、全26話の物語がそれぞれに独立して完結しつつ、それら個別のストーリーが笑い男事件という一つの物語に関連し収束してゆく点。
つまり独立した各話がおりなす全体の物語の構成は、STAND ALONE(個別の) COMPLEX(複雑なつながり)になっています。
また複数の物語が三者構造を通じて、「現実の日本人にとっての敗戦のトラウマと日本人との関係性」を象徴しているのも特徴。
タチコマと笑い男の二つの物語の交錯
SACの主題はタチコマの成長と笑い男の成長という二つの成長譚に集約されます。
したがってSACの本質の把握に、この二つのストーリー展開の理解は必須。
最終話で二つの異なる物語は、問題提起とそれへの解答という形で交差します。
また米帝がどのように描かれているのかに注目すると神山監督の世界観がわかりやすい。
タチコマの物語
SACでのタチコマの位置づけは作品全体の意味を理解するうえで重要。
SACでのタチコマのストーリーはゴーストをもたない並列化された思考戦車の集団(タチコマ)がバトーとの接触をきっかけに経験をつみ、個性(ゴースト)を獲得するもの。
タチコマの成長の物語は、最終26話での笑い男(アオイ)と少佐の会話のなかで、笑い男事件と関連付けられ、スタンドアローンコンプレックスへの一つの解答として提示されます。
タチコマと個性と好奇心
タチコマがいかにしてゴースト(個性)を獲得したのかについて。
結論から言うとこの答えは作中の台詞で直接言及されます。
以下、最終回の26話での台詞の抜粋
少佐「情報の並列化の果てに個をとりもどすための一つの可能性を見つけたわ」
アオイ「ちなみに、その答えは?」
少佐「好奇心」
台詞から少佐は好奇心こそが並列化した没個性のタチコマたちに個性を与えたと考えています。
また少佐とアオイの会話は、スタンドアローンコンプレックスといわれる笑い男の模倣現象を克服する答えとして提示されます。
この最終話の会話の意味を以下に膾炙します。
アオイや少佐が語る並列化の問題とは、現代のネット社会がもつネットによる人々の並列化のこと。
そのため少佐らが論じる問題は、たとえばコピペばかりする没個性的な人や飲食テロを模倣する没個性のバカッターを生み出し続けるネットについて。
そして没個性の模倣者(スタンドアローンコンプレックス)を克服し、並列化したネット社会で個性を取り戻す問題解決の鍵は好奇心にある、と少佐は言ってます。
次に個性を取り戻すための好奇心はどのように生じどこからやってくるのかを確認します。
好奇心とはなんなのか
タチコマの好奇心がいかに生み出されたかを理解するには好奇心がなんなのかを知る必要があります。
これはSACの監督である神山健治が好奇心をどのように定義しているのかと同義です。
そこで神山健治氏がSACの物語を構成する上で、その骨子とする理論をみてゆきましょう。
結論からいうと、神山健治監督はジャック・ラカンの理論をSACシリーズの中核としています。
※ラカンはフランス現代思想の人で精神分析の人です
そのためタチコマの「好奇心」はラカンにおける「欲望」です。
「好奇心=欲望」
ここではひとつだけわかりやすいラカンをベースとする根拠をあげるにとどめます。
SACの15話でタチコマのセリフ抜粋
タチコマ「神ってやつの存在もちかごろはなんとなく分かる気がしてきたんだ。もしかしたらなんだけどさ数字の0に似た概念なんじゃないかなって、ようするに体系を体系たらしめるために要請される意味の不在を否定する記号なんだよ。そのアナログなのは神でデジタルなのは0。」
このセリフで言われている神や0の解釈は、ほぼ完全にラカンがいう「父の名」に対する定義と同じ。また父の名は父なる一神教の神に対応し、このセリフひとつだけ観てもラカンがベースにある可能性が高いです。
じじつラカンは父の名を、象徴的体系を体系たらしめるための意味の不在(存在)を否定し上書き(隠喩)する父の否であり名というシニフィアン(≒記号)であるという論旨の定義をしてます。
※「父の名」としての神への言及は『攻殻機動隊 SAC_2045』で極めて重要なものとして物語に組み込まれいます。
好奇心(欲望)はいかに生まれるか
ネットで並列化したスタンドアローンコンプレックスの主体が個性を獲得するための好奇心(欲望)。これがいかに獲得されるかを解説します。
ここでタチコマ、バトー、少佐の三人の関係を整理します。
タチコマを中心に観た場合、精神分析的にはバトーは母親、少佐は父親、タチコマは子ども、になっています。
- タチコマ=子、バトー=母、少佐=父
タチコマの欲望の最初のきっかけはバトーが自分の専用機に与えた天然オイルです。
しかし重要なのは天然オイルの成分ではありません。
ここで重要なのは、なぜバトーはタチコマに天然オイルを与えたのか。
バトーは自分の搭乗する機体を特定し、自分の専用機に対して天然オイルを与えています。
このことからバトーが天然オイルに託した欲望は、自分の専用機に並列化された他の機体と異なる、交換不可能な個性を獲得して欲しいということだと推測できます。
つまりタチコマの個性へいたる好奇心の源泉はバトーが天然オイルに託した個性を持って欲しいという欲望であったとわかります。
したがってタチコマの個性はバトーが天然オイルに託した欲望を受け取ってそれを自分の欲望(好奇心)としたことで生じます。
このような母なる他者の欲望を介した個性の習得プロセスをラカンは「人間の欲望とは他者の欲望である」と言います。この言葉の意味は他者(母)を欲望するという意味と自分の欲望がもとは他者の欲望であるという意味の二つの意味です。
ここまでが分かるとバトーの天然オイルは母親の乳房のメタファーになっていると分かります。
ポイントはバトーはタチコマに個性を欲望したこと。つまりなにか具体的なものを欲望したわけではないのです。
そのためタチコマたちはバトーが欲望する個性とは具体的になんなのかと感じ、さまざまな未知の対象に好奇心を発揮することになり、結果多様な個を発達させました。
12話「タチコマの家出」と死の獲得
タチコマの物語において決定的な意味を持つのは、12話「タチコマの家出」。
また12話以降、少佐は本格的にタチコマに禁止をかす父として登場します。
この回はミキという少女がいなくなった愛犬ロッキーを探し(欲望し)ているところにタチコマが遭遇し、一緒にロッキーを探す旅をする話。
注目して欲しいシーンは、タチコマがミキちゃんをコクピットに乗せて帰宅するシーンでのタチコマのコクピットのカットです。12分40秒~くらいのところ、ここでタチコマのコクピットのモニターに「to be – not to be」という文字が表示されます。
これはto be or not to beを示し、周知のとおりシェークスピアのハムレットの有名な一節です。
日本語訳では「生きるべきか死ぬべきか」と訳されます。
ハムレットの「to be or not to be」はラカン派精神分析における主体(神経症)の基本命題として有名な言葉です。
精神分析での「to be or not to be」の訳は「私は生きているのか死んでいるのか?」。
※「to be or not to be」はジャパニメーションや和ゲーでは頻出のテーゼです。たとえば地獄楽やニーアオートマタでもこの主題が扱われています。
「to be or not to be」は人間が個性をもった主体として誕生することで可能となる根源的問い(欲望)。
つまり個性を獲得することで他の誰でもない私という個人の死という概念が生じ、そのことで生と死が切り分けられることを意味してます。
無個性で並列化により自他一体の動物的な意識では、自分自身という個人の死は成立しないので死を理解できません。この意味で個人の死は極めて近代的な概念です。
ゆえにゴースト(個性)の獲得は本格的な死の不安の入り口でもあります。
次にタチコマはミキちゃんとの出会いで、なぜ本格的に個性と死を獲得するに至ったかを具体的に解説します。
「タチコマの家出」とゴースト(個性)
12話の「タチコマの家出」は複雑で、家出した犬が家出したタチコマに置き換わっていたり、ミキとタチコマやミキの両親と少佐の関係がシンクロする特殊な構造をもっています。
そんなタチコマの家出では、ミキが本当は愛犬が死んでいることは知っていて、親にそれを悟られないようにするために探しにいくふりをしていたことを告げるシーンがあります。
このシーンでは、愛犬ロッキーの墓前で涙を流すミキの姿にタチコマもオイルをこぼして涙をながします。
タチコマが涙を流すさいのタチコマのセリフを以下に抜粋し詳しく観てゆきましょう。
タチコマ「ぼくには死って概念がわからない。ゴーストがないからだと思うんだけど悲しいって概念も理解できない。やっぱりぼくが死ぬことができないからかな。」
死がわからないと悟り、悲しいという概念が理解できないと気づいたことで、タチコマは死と悲しみを理解し涙を流したと考えられます。
なぜ死が分からないことが死という概念の獲得につながるのか理解するには、「タチコマの家出」をさらに深く読み解く必要があります。
まず重要な前提として、ミキは愛犬が死んでしまい、もう二度と会うことができなくなりました。
そして、両親は娘を案じてロッキーは遠くにでかけている、探しに行ってはいけないという禁止をミキに課します。
この経緯が非常に重要。
まずこのような不可能な欲望の対象(死んだ犬)を禁止することをラカンは父の名と呼びます。
ここで注目して欲しいのが、ミキが両親に課せられる禁止の物語は、家出したタチコマが9課に戻ったときに、少佐に天然オイルを禁止にされてしまったことと対応していること。
またこれまでに説明したようにタチコマにとっての天然オイルは、バトーがタチコマにたくした個性をもって欲しいという欲望でもあります。
よって天然オイルが少佐によって禁止にされるということは、タチコマがバトーの欲望を直接満たすことを禁止されたということです。
つまりタチコマは天然オイルをバトーから直接手にすることができなくなったのです。
このことは子どもが成長し乳ばなれの時期になって、父親から母の乳房(天然オイル)を禁止にされることに対応します。
そしてこの父の名による禁止こそが母離れを促し個性を獲得するステップに欠かせません。
よって先ほど抜粋した「死も悲しみも理解できない」という自らの不能を吐露したタチコマの告白は、バトーの欲望を直接満たす力が自分にないことを知ったことに対応します。
このことでバトーという母からタチコマは分離し、母から切り離された個として個性の獲得に至ったのです。
すると不在のロッキーを探すミキちゃんと、ゴースト(個性)不在のAIであるタチコマが欲望する個性(天然オイル)が、きれいに対応していることが分かります。
タチコマの家出のひとつの結論は、タチコマがロッキーがじつはもういないことを知ることと、自分はバトーを完全に満足させるゴーストを持っていないことを悟ることがシンクロしていること。
「タチコマの家出」の対応表
| 欲望する人 | 欲望される対象 | 禁止する人(父の名) |
| 家出のタチコマ | ゴースト (天然オイル) | 少佐 |
| ミキちゃん | 家出した犬 (家出のタチコマ) | 両親 |
| 子ども | 母の乳房 | 父親 |
笑い男事件でもこれと全く同じ構図が出てくるのでこの表は注目しておいてください。
タチコマの涙とゴーストの獲得
タチコマの涙の意味について。
涙、悲しみは、喪失によって生じます。たとえばミキちゃんがロッキーの墓を観て、ロッキーを喪ったことを実感して涙するのもそのため。
しかし喪失の悲しみは、たんに喪ったことを意味するのでなく、涙はつねに喪失と同時に喪われたものの獲得を示します。
つまりミキちゃんであれば、愛犬ロッキーの喪にふくし涙を流すことで、ロッキーが自分にとってどんな存在だったのか、その意味を獲得したわけです。
大切なものは喪ったときにはじめて自分にとっていかに大事だったか知るもの。なので喪失により喪われたものの意味が獲得されるといっても過言ではないでしょう。
涙を流すことで喪失の傷が癒えるのは、喪失それ自体のうちに喪われたものの、意味の次元での回復がインプットされているからに違いありません。
だからこそタチコマの涙はゴースト(個性)がないことを悟ることで、つまり、ゴーストが自分には喪失していることを認めることで、これらの概念を獲得することを示します。
よって悲しいを理解できないことを受け入れたことで、タチコマは喪失した悲しみをオイルの涙として理解したわけです。
タチコマの涙はとくに『攻殻機動隊 SAC_2045』と関連性があるのでその意味でも重要。
次にタチコマが獲得した個性がどのような方向に向かうのかを観てゆきます。
第15話「機械たちの時間 MACHINES DESIRANTES」
「タチコマの家出」で急速に個性を伸ばしたタチコマは、そのあとタチコマを兵器であり個性はいらないと考える草薙素子と軋轢を生じます。
また「タチコマの家出」で少佐が天然オイルを禁止したことと少佐がタチコマの個性を消し去ろうとしたことは対応しています。天然オイルが個性(ゴースト)であることがこのことからも分かります。
少佐のタチコマへの命令と禁止はタチコマの個性と衝突し、15話「機械たちの時間」でついにタチコマは反抗期を迎えます。この回では、タチコマが少佐をやりこもうとするも、少佐はすべてお見通しで、タチコマをラボ送りにしてしましいました。
無料放送版では「ドナドナ」を、DVDやVODでは「赤い靴」を歌うタチコマの姿はSACでも名シーンの一つとして有名です。
というわけでタチコマの個性と少佐の命令の関係を具体的に見てゆきましょう。
まず少佐に天然オイルを禁止され、バトーの欲望を直接満たすことができなくなったタチコマは、少佐の厳しい規則にしたがってバトーの欲望(タチコマの個性)を欲望せざるえなくなります。
またタチコマと一緒にいるときでも、バトーは少佐に呼ばれれば少佐のもとへゆき、少佐を優先しますし、バトーは少佐に憧憬の念を抱いていてもいます。
そのためタチコマにはバトーの欲望や関心の秘密は、少佐が握っているように見えるのです。すくなくとも精神分析ではそのように考えます。
こうして母であるバトーの欲望を父である少佐から探り、こんどは少佐の秘密(欲望)を欲望してゆくのです。またタチコマは少佐を内面化し少佐のようになろうともします。このようにして内面化される父の像を自我理想とか超自我と呼びます。
ところが少佐はそんなタチコマの好奇心(個性、欲望)が気に入りません。そのため少佐はタチコマに明確な命令をだすことでタチコマの好奇心を潰そうとしました。
つまり、主体は他者の命令に従うだけになると、主体性のないロボットと同じになるわけです。
このような命令は乳児がないているときに、ミルクを飲めといって哺乳瓶を押しつけているのと同じ。
これではゴーストは生じません。子どもがなにかを欲求したら、命令ではなく「どうしたのかなぁ?お腹が減ったのかなぁ?それとも外に行きたいのかなぁ?」と言えば、親の子どもに対する要請は疑問形となり、その要請(欲望)の謎に直面して子どもは謎の答えを探し個性(好奇心、欲望)を獲得するわけです。
するとバトーの天然オイルはまさに、曖昧な問いかけになっていることが分かるでしょう。バトーは個性について、お前はガリ勉になり云々というような具体的なことは何も命令していないわけです。
このあいまいな問いかけ、それこそが個性を生じるためのタチコマの好奇心(欲望)の正体でした。
よって少佐による天然オイルなどの禁止の命令はタチコマのバトーからの自律に必要ではあっても、その度が過ぎれば、かえって個性は潰されてしまうわけです。
しかし15話での少佐による公安9課からの追放(禁止)は、タチコマの回路に少佐を父の名として刻みつけることにもなりました。
ところで、現代社会はマニュアル管理され、社会の言葉は命令に満ちあふれています。たとえば広告やCMのメッセージはこの商品を買え!というだけのもので、なにも曖昧さがありません。
バイトなどの労働もマニュアル化し、ロボットのような接客が求められる時代です。このような時代ではバイトテロなどのスタンドアローンコンプレックスが生じるのも仕方ないのかもしれません。
STAND ALONE COMPLEX
概ねタチコマの解説が終わったので、ここではいよいよ笑い男とスタンドアローンコンプレックスついて解説してゆきます。
笑い男事件とは、アオイというスゴ腕ハッカーが電脳硬化症のマイクロマシン療法に関する不正を知り、その不正をただすために行ったセラノゲノミクス社長の誘拐事件。
およびそのあとに続いた企業テロ、警視庁暗殺事件などの一連の模倣犯のことです。
笑い男であるアオイは挫折し一度表舞台から消えると、次々に笑い男を名乗る模倣犯が発生し、その模倣犯による笑い男の模倣行為をスタンドアローンコンプレックスといいます。
笑い男(アオイ)とセラノゲノミクス社長の父子関係
少年ハッカーのアオイはセラノ社長(アーネスト瀬良野)を誘拐し不正を公にするように迫ります。その姿は父と父に反抗する息子の構図そのものです。とくにカフェで議論する姿は親子にしか見えません。
どこか少佐とタチコマの関係を彷彿します。
じつは一連の笑い男事件のきっかけとなるセラノ社長と村井ワクチンとアオイを巡る三角関係は先ほど「タチコマの家出」でしめした構図と全く同じ構図になっています。
ここではセラノ社長が禁止する人、村井ワクチンが欲望される対象、アオイが欲望する人になっているわけです。以下にあらためて表にしておきます。
| 欲望する子ども | 欲望の対象 | 禁止する父(父の名) |
| アオイ (笑い男) | 村井ワクチン | セラノ社長 |
| タチコマ | 天然オイル (個性) | 少佐 |
| ミキ | 家出した犬 (ロッキー) | 両親 |
重要なのはアオイは自身が電脳化を徹底しているために電脳硬化症を恐れていることを作中で吐露していること。そのため今来栖尚によって不当に不認可にされた電脳硬化症の特効薬である村井ワクチンはアオイの欲望の対象になっているのです。
また村井ワクチンも不認可の印を押され表向きは消え去っています。なのでSACでの欲望の対象は全て欠如し禁止されていることが分かります。
この消え去った対象をめぐってアオイやタチコマに好奇心(個性、欲望)が生じているわけです。
またセラノ社長に対するアオイの犯行は15話の「機械たちの時間 MACHINES DESIRANTES」でタチコマが少佐に反抗することに対応しています。
ちなみに見てはいけないものを覗くという窃視のメタファーであるハッカーのアオイが覗いた最初のファイルはまさにトラウマと呼ぶにふさわしいものです。
スタンドアローンコンプレックスとエディプスコンプレックス
禁止をかす父に抵抗するも少年ハッカーのアオイは、セラノ社長に裏切られ挫折することになります。
さらには厚生省、中央薬事審議会元理事の今来栖や与党幹事長の薬島などの大物の関与も相次ぎ、アオイの正義感は折られてしまいました。
このような禁止された対象、この場合は村井ワクチンですが、これをめぐって父と争い挫折を味わう、という一連の人間心理の発達プロセスをエディプスコンプレックスといいます。
これは、子どもが反抗期に親や社会に挑戦し戦い、挫折をとおして成長するというモデルでもあります。
このことはSACの続編にあたる2022年にNetflixで独占配信された『攻殻機動隊 SAC_2045』との比較でも非常に重要になるので解説しておきました。
※そのうち気が向いたら『攻殻機動隊 SAC_2045』の解説も記事にしときます。
スタンドアローンコンプレックスの仕組みとメインテーマ
ではここからいよいよスタンドアローンコンプレックスの仕組みを見てゆきましょう。
スタンドアローンコンプレックスとは最終話の26話「公安9課、再び」でのアオイと少佐の会話によると、オリジナルの不在がオリジナルなきコピーを作り出す現象のことを示しています。
これはもちろん、笑い男の模倣者の出現を指摘しているのですが、アオイはこの現象を「絶望の始まりに感じられてならない」と言います。
それに対して少佐が情報の並列化の果てに個をとりもどすための一つの可能性として好奇心を提示します。
このことからネット社会における没個性的な模倣者の出現という問題について、少佐が好奇心(欲望)がその問題を解決しうると言っていることが分かります。これこそがSACの主題といえるでしょう。
したがってタチコマの成長物語と笑い男事件の二つの物語は、基本構造を共有しつつ独立に並走し、最終話に至って初めて交差し、コンプレックスを結ぶ結節点を生じたのだと思います。
スタンドアローンコンプレックスとナナオ・A
笑い男の模倣者は本作では多く、少佐やトグサさえもが笑い男を模倣しているのは有名ですが、ここではナナオ・Aを扱います。
というのも、ナナオは多くの模倣者の典型であり、アオイが絶望したスタンドアローンコンプレックスの特徴をよく反映しているからです。
ナナオはその虚栄心から、世間で伝説的ハッカーとなりつつあった笑い男のオリジナルになりかわることで、人々からの承認を得るため模倣者となった人物の一人です。
つまりナナオ型の模倣者たちにとって笑い男は理想的な自己像のシンボルになっているともいえます。
そして、このような他者(親や世間)から欲望される理想的なシンボルといえば、タチコマにとっての天然オイル(個性)とも重なります。
つまり模倣者の問題は自己の欲望する理想の対象にそのまま到達しているという点なのです。
これでは欲望(好奇心)は死んでしまいます。
というのも、これまでに説明してきたように、欲望の対象は欠如し父の名によって禁止されることで、好奇心をつくりだし、個性(ゴースト)をもたらすからです。
ようするに、具体的な対象として、欲望の対象が獲得されてしまうとそれに満足してしまい何も考えなくなってしまうということです。
つまり思考停止して忠実に笑い男を模倣するということは、親(笑い男)の命令をそのまま実行するだけの個性のないロボットと同じなわけです。
するとタチコマが15話で「満足な豚より不満足なソクラテス」といった意味もよく分かります。
笑い男になりきって笑い男として自己実現するということは、満足な豚になるということです。
もっと別の角度からいうと、理想の笑い男になるということは、FFなどのロールプレイングゲームで最強の武器と装備を手に入れたら一気に飽きるという現象とも同じなのです。
理想の対象に到達し満足してしまうと人は飽きて欲望が萎えてしまい、気力を失い死んだ魚の目になります。
タチコマにしろ、アオイにしろ理想(欲望の対象)が消え去って禁止され、それが欠如したことで好奇心(個性、自己への問い)が継続していったといえます。
だからこそアオイは理想のヒーロー像である笑い男の役を少佐に譲るという決断をしたわけです。このことでヒーローとしての自己実現は断念され禁止されました。
よってアオイがスタンドアローンコンプレックス現象に絶望したというのは、究極の理想を諦めきれない幼児的な現代人が理想(笑い男)を直接自己実現することで好奇心(欲望)を失い没個性化する状況への絶望を意味していると考えられます。
ポイントはタチコマやミキ、アオイにあったはずの禁止(父の名)の消失によって、スタンドアローンコンプレックスは生じていることです。
このような直接に理想の対象を自己実現しようと競いあう状態のことをラカンは「想像的な関係」と呼んでいます。ラカンによれば想像的な関係とは、俺かお前か、という嫉妬的な理想(対象)の奪いあいにあるといいます。
このことは6話「模倣者は踊る MEME」での警視総監殺害未遂事件のさいに生じた大量の笑い男の模倣者のうち二人が取り調べを受けるシーンを見ると、よく分かります。
その取り調べで模倣者の一人は「笑い男。他の奴はみんな偽物なの、俺だけが本物なの!」と供述しています。このセリフは俺かお前かという想像的関係をよくしめしています。
またもう一人の容疑者は「笑い男からのメッセージだったんです。私に笑い男になれと、あの暗殺予告はそう告げていたんです。」と供述しているのですが、このような妄想は関係妄想といい想像的な関係の典型として精神分析では有名なものです。この妄想の真意は他の誰でもない自分だけが笑い男に選ばれた、ということにつきます。
こうして笑い男の命令を聞くだけの個性のないロボットになるわけです。
このことからSACでは多くの模倣者は、オリジナルの笑い男の座をめぐり競いあう想像的な関係にあることが分かります。
| 欲望する人 | 欲望の対象 | 父の禁止 |
| アオイ | 村井ワクチン | 瀬良野 今来栖 |
| 模倣者達 (ナナオA) | 笑い男 (ヒーロー) | × |
この表から父による禁止が機能しないことでスタンドアローンコンプレックスを発症することが分かります。
「Or should I?」の意味

笑い男がサリンジャーの小説『ライ麦畑で捕まえて』から引いた”I thought what I’d do was, I’d pretend I was one of those deaf-mutes or should I ?”
笑い男が残したこの文章ではオリジナルにはないor should I ?が付け足されています。
トグサの訳は「僕は耳と目を閉じ口をつぐんだ人間になろうと考えたんだ。だが、ならざるべきか?」
となっています。
実はこの文、精神分析的には「タチコマの家出」でタチコマのコクピットに表示される「to be – not to be」に対応しています。
よってこの文は「私は死んでいるのか生きているのか?」という欲望を持つ主体の基本命題になっています。
挫折により、理想が禁止され理想を直接自己実現することを断念しかけたことでアオイは成長し、このような問いを発したのだと考えられます。
「Or should I?」とトグサの推理
またトグサはor should I ?というこれまでのサインにはない一文が付け足されいるのを見て、これを書いた笑い男こそがオリジナルの笑い男だと推理します。
このトグサの推理は何を意味しているのでしょうか?
トグサの推理の本質をここで、わかりやすくかみ砕いてみましょう。
すると、模倣者は欠如のない完璧な理想の対象を忠実に模倣し自己実現するだけだから、オリジナルにはない一文は付け足せない。しかしオリジナルにとっては自己の理想(笑い男)は欠如しており、理想の存在は問いに付された。
そのために疑問符の一文がつけたされたのだろう、という感じになるでしょう。
このことからも模倣者が想像的であり父の禁止がないために個性を喪失し、オリジナルは父の禁止によって好奇心(欲望)を獲得したことで、自己の存在を問い、自らの個性を欲望していることが分かります。
またトグサのこの推理はトグサ自身が笑い男になりきって笑い男が直面している自己存在(正義)に対する問い(欠如)を欲望していることがよく現れています。このことから、この段階ではまだトグサがスタンドアローンコンプレックスを発動していないことを示しているのだと思います。
しかし最終回の26話で公安9課の消滅と仲間たちの喪失にともなう孤独(スタンドアローン)によってトグサもまた想像的な関係に陥りスタンドアローンコンプレックスを発動することになりました。
神山健治監督の思想と米帝
神山監督による攻殻機動隊の世界では、米帝は非常に重要な位置を占めていると僕は考えています。
SACでは米帝のCIAが10話「密林航路にうってつけの日 / JUNGLE CRUISE」で登場します。またこの10話の話は直接に『攻殻機動隊 SAC_2045』につながっていてその意味でも重要です。
そして、この10話はSACシリーズを読み解く上でも神山的歴史観を読解する上でも非常に重要になってきます。
「密林航路にうってつけの日 」サンセット計画と原爆投下
10話では米帝が戦時中におこなった「サンセット計画」という残虐作戦が表沙汰にされないよう隠蔽するためにバトーをたきつけて関係者のマルコを始末させようとします。
ちなみにバトーはサンセット計画の目撃者になっています。
※『攻殻機動隊 SAC_2045』でのあるキャラのトラウマの目撃者と対応させると面白いです。
ここで残虐作戦であるサンセット計画は心理学的にはバトーの心的外傷(トラウマ)を意味しています。そのため、サンセット計画というトラウマを隠蔽しつつバトーをトラウマの中に突き落とそうとするのが米帝CAIといえます。
じつは精神分析では、このような正義のために他者を抹殺せよ!という心のなかの衝動は超自我によるほのめかしだといいます。ちなみに超自我とは心の中で全てを規則や理想にしたがわせるため自他を罰したり禁止をかしたりする心の中の声の主(父の分身)です。
つまり10話では、米帝はトラウマを隠蔽し抑圧する者であると同時にトラウマに突き落とす者として描かれています。
ようするに原爆(サンセット計画)をぶちこんで、日本(バトー)をトラウマにつきおしておきながら、その闇を隠蔽するのがアメリカ(米帝)みたいな感じです。
ここで思い出して欲しいのが、12話「タチコマの家出」のミキの犬のことです。家出した犬のことは欲望される対象として解説してきましたが、重要なのはミキちゃんが「もう犬は飼いたくない」とタチコマに打ち明けたことです。
このことは愛犬ロッキーとの思い出がトラウマ化したことを示します。
つまり幸せな対象というのは、それが喪失され父により禁止されることでトラウマにもなるということです。精神分析ではこのように考えます。
したがってバトーのトラウマであるサンセット計画はタチコマの天然オイル(個性)やアオイにとっての村井ワクチン(の接種者リスト)に相当しています。
そのため米帝はバトーに快楽殺人をほのめかす超自我(父)の声であると同時に様々な禁止をかす父親でもあるといえるのです。そしてSACでは米帝は日本の同盟国でもあります。
このことから米帝(現実でのアメリカ)というのがSACでは日本にとって、かなり歪んだ父親として描かれているのが分かります。
三者構造の対応表:米帝と日本=瀬良野とアオイ
SACの直接の続編である『2nd GIG』でも米帝は登場しますが、『2nd GIG』ではより直接的に日本に禁止をかすサディスティックな父として米帝が描写されています。
これまでの分析から、SACでは日本人にとって心理的に形成されているアメリカとの親子関係の歪さとして現代日本の心的問題が描かれていると僕は考えています。
ここでこれまでの説明から得られるキャラクターの三者構造を表にまとめておきます。
| 子ども | トラウマ | 禁止する父 (超自我) |
| アオイ (日本) | 村井ワクチン (原爆・敗戦) | 瀬良野や今来栖 (アメリカ) |
| バトー (日本) | サンセット計画 (原爆・敗戦) | 米帝CIA (アメリカ) |
| タチコマ | 天然オイル | 少佐 |
| ミキ | 家出した犬ロッキー | 両親 |
表の上の二つでは禁止する父に位置する人が歪んでいることが分かります。いびつな父といってもいいでしょう。
米帝は同盟国としての優しさもある反面、非常に狡猾で子ども(日本)の個性を認めようとしないかのようです。
以上のことから、神山史観では戦後日本人の心理的な意味でのアメリカへの依存や権威主義の蔓延が、スタンドアローンコンプレックスに代表される日本的幼児性の一因と見なされているのかもしれません。
いずれにせよ、アメリカとの心理的な関係性によって日本人のあり方を考えていることは間違いないと思います。おそらく2002年時点での神山監督のメッセージはラカン的な意味で、日本人はアメリカから分離せよ!だと思われます。
SACに象徴される日本にとってのアメリカが『攻殻機動隊 SAC_2045』ではどのように描写されているのかは非常に重要になります。神山監督のメッセージは2045では全く違うものに変わっています。
またこのアメリカ像は現実のアメリカが横暴だとかいうこととは直接の関係はありません。
SACシリーズは、あくまでも日本人の心理的なリアリティとしてアメリカがどのように内的に位置づけられているかを表象しているということです。物語というのは総じて外的事実ではなく内的なリアリティを象徴するものです。
ここまでの結論をコンパクトに圧縮
ここまでをざっくりまとめると、まずネット社会で人々は孤独になり、その孤独を紛らわすように情報を並列化させています。そのような並列化によって笑い男のような偶像が自己の理想像として大衆に共有されます。
次に偶像のオリジナルが消え去ることで、その喪失を補うように、直接にその偶像になりきり笑い男に一致することでスタンドアローンコンプレックスとなるわけです。
この偶像の生成とオリジナルの消失は、個性を放棄したロボットのような模倣者(コピペ記事)を再生産し続けるというのがアオイの絶望の全容だと思われます。
そしてこの絶望を克服するための経路が好奇心(欲望)にあるということが少佐により示されます。
その好奇心を可能とする経路が、欲望する子、欲望される対象、禁止する父(父の名)という三者の構造を軸として巧みに描写されているのがSACの物語構造の基本となっています。
| 欲望する子ども | トラウマ (欲望の対象) | 禁止する父 (父の名) |
| 日本 | 敗戦 (原爆投下) | アメリカ |
| バトー | サンセット計画 (マルコ) | 米帝CIA |
| アオイ | 村井ワクチン (接種者リスト) | 瀬良野 今来栖 |
| タチコマ | 天然オイル (個性) | 少佐 |
| ミキ | 愛犬ロッキー | 両親 |
また、現代日本人のスタンドアローンコンプレックス的幼児性は敗戦というトラウマを契機として心理的に形成されたアメリカとの親子関係のゆがみにあると神山監督は考えているのかもしれません。
むりやりコンパクトにまとめるとこんなところでしょう。
ところで、こんかいの解説では「父の名」を強調しましたが、じつは『攻殻機動隊 SAC_2045』ではさらに父の名が非常に重要になってきます。
なのでその準備の意味も込めてラカンのタームである父の名を強調した解説をしていたわけです。また神山監督がラカンの父の名をベースにSACシリーズを組み立てているのはあきらかだと思います。
ちなみに『攻殻機動隊 SAC_2045』では映画マトリックスが非常に重要になってきます。酷評されることも多い『攻殻機動隊 SAC_2045』ですが、ちゃんと分析するとすごい名作だとわかります。
まとめ
ここではなんとかこれまでの内容のだいたいのところをまとめておきます。
- S.A.C.では笑い男事件とタチコマの物語が並走し最終話で交差する
- 情報の並列化した社会でゴースト(個性)を獲得する鍵は好奇心
- 好奇心とは欲望
- 欲望とは欠如した対象を求めること
- 完全に満足すると欲望は消えて飽きる
- 人は欲望(好奇心)が消えると個性も消える
- タチコマとバトーと少佐は子と母と父に対応する
- タチコマの欲望はバトーの欲望
- タチコマは少佐に禁止されてバトー離れし直接に欲望を満足できなくなる
- 少佐の禁止(父の名)でタチコマは欲望を生きつづけられゴーストを獲得する
- アオイと村井ワクチンと瀬良野の関係はタチコマと天然オイルと少佐の関係と同じ
- スタンドアローンコンプレックス(スタコン)は禁止がないことで好奇心が消えて起こる
- スタコンは想像的な嫉妬関係を生み出しヒーロー像を奪い合う
- タチコマや笑い男の「Or should I?」(to be-not to be)は欲望
- SACの物語構造は子ども、欲望の対象、禁止の三者構造でできている
- アオイは村井ワクチン、タチコマは天然オイル(個性)を欲望する
- 村井ワクチンは瀬良野や今来栖に禁止される
- 天然オイル(個性)は少佐に禁止される
- アオイと瀬良野や今来栖との親子関係は日本と米帝の親子関係
- 現代日本人の問題を神山監督は日米の親子関係に見ている
- 欲望の対象は禁止によりトラウマとなる
- ミキの家出した犬も天然オイルも村井ワクチンもトラウマ(サンセット計画)である
こんかいは以上です。かなりS.A.C.を見直して分析したので、この記事を書くのは本当に疲れました。
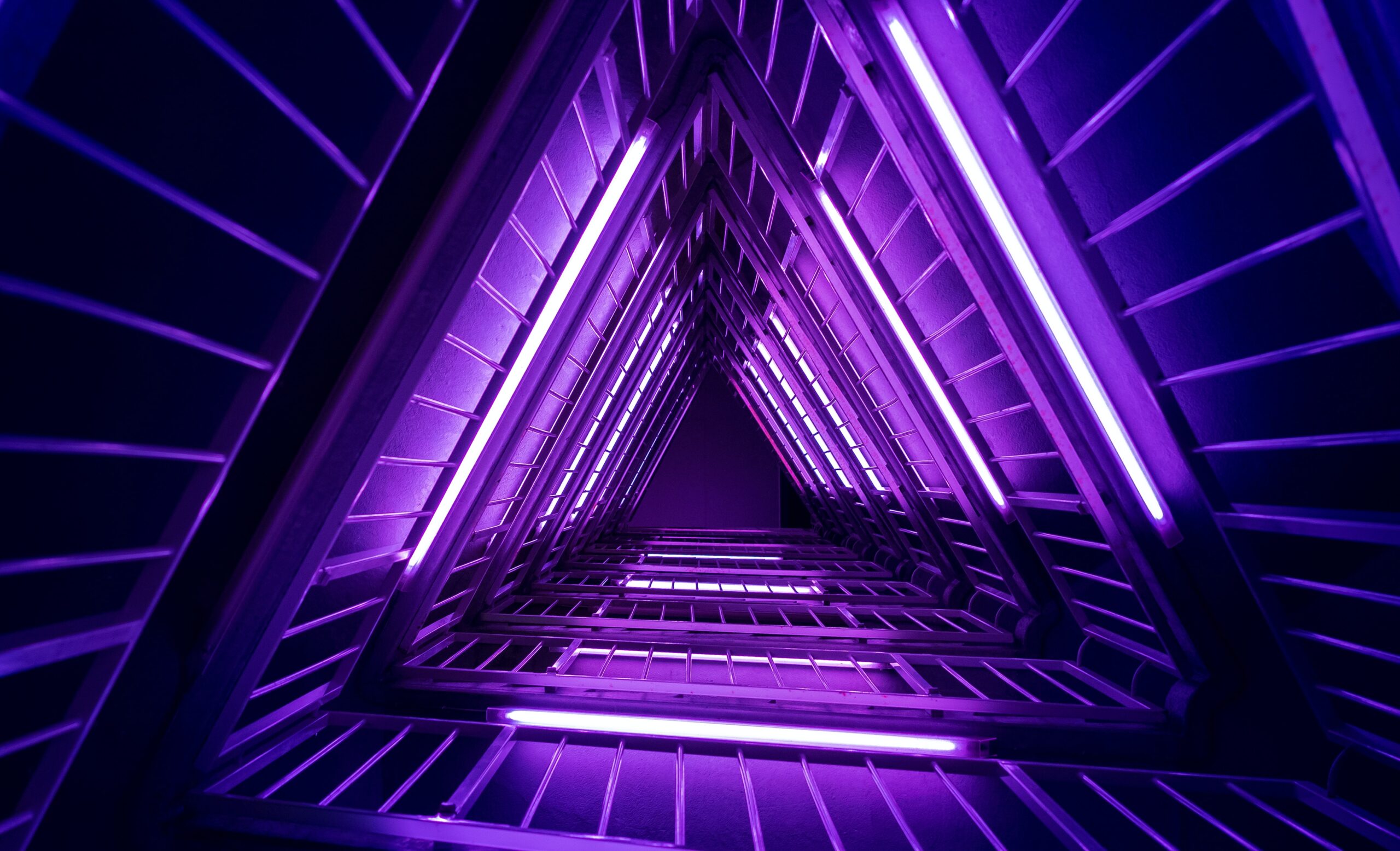


コメント
超絶ためになりました。
先程、最後の人間の映画を観てきたところです。改めて映画についての考察などもお聞きしたいです。