どうも!うたまるです。
※この記事は以下の作品のネタバレを含みます
こんかいは精神分析と木村敏の精神病理学の理論を駆使して異世界転生アニメ、『ブラックラグーン』『転成したらスライムだった件』『オーバーロード』『幼女戦記』を順に考察しその人気の理由を完全分析!
なぜ最近の異世界転生は主人公が最強なのか、異世界はロールプレイングゲーム風なのか、これらの疑問もすっきり解消する内容になっています。
また異世界転生作品の歴史的変遷と社会構造の対応も明らかにします。
異世界転生作品好きにも現代社会に興味ある人にも見逃せないここだけの内容です。
異世界転生作品の歴史
この記事では異世界転生作品を統合失調症型と躁鬱病型ないしは発達障害型に大別する。
初期の異世界転生アニメは統合失調症型の存在構造を持ち、現代主流のものは鬱病構造ないしは発達障害構造を持っている。
ここが分かると売れる作品の構造や条件から現代人の時間感覚、主体のあり方など多くのことを見抜くことが可能なのでそれを説明する。
ここに、異世界転生アニメを観れば、人類の精神がいかに変化しているか克明に分かることをしめそう。
ブラックラグーンと異世界転生
ブラックラグーンとは
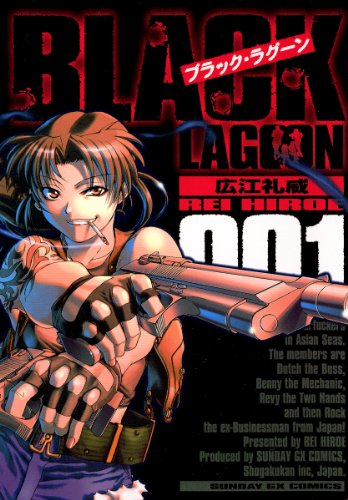
| 作品名 | BLACK LAGOON |
| 原作者 | 広江礼威 |
| 放送期間 | 一期:2006年4月9日 – 6月25日 二期:同年10月3日 – 12月19日 |
| ジャンル | クライムアクション |
アニメ好きでこの作品を知らない人はまずいないだろう。とくに現在30代という人であればなおさら。
本作は2006年を代表するアニメの一つ。当時の若者の心理を克明に反映している。
ブラックラグーンあらすじ
国立大学卒の新入社員、岡島禄郎は東南アジアに出張中、海賊「ラグーン商会」に拉致される。
タイの架空の犯罪都市の三大勢力が一つであるロシアンマフィア、ホテルモスクワの依頼で禄郎の務める大企業、旭日重工の密輸に関わるディスクを奪ったラグーン商会は身代金のため禄郎を拉致る。
ホテルモスクワはディスクをネタに旭日重工と交渉するも旭日重工は禄郎を切って、傭兵を派遣しディスクごと禄郎を海の藻屑にすることを決定。
旭日重工から派遣された戦闘ヘリに殺されかけ禄郎だが、機転を効かせかろうじてラグーン商会とともに敵のヘリを撃墜。
かくして禄郎は象徴的な死を体験したことで、岡島禄郎という名前を捨て新たにロックと名乗り東京の日常世界には帰らず、ラグーン商会に入会する。
ロックは非日常世界を象徴するタイの犯罪都市ロアナプラでスリリングな生活をすることになる。
ブラックラグーンの異世界転生性
いわずと知れた人気漫画原作アニメ『BLACK LAGOON』。一般にブラックラグーンは異世界転生作品とは言われていない。
しかし、物語の構造という側面ではブラックラグーンは紛れもなく異世界転成アニメなのだ。
このアニメは、国立大学から大企業へと就職した青年期の男が殺されかけ、象徴的な死を体験し、名前も生活の基盤もなにもかもを捨て去り、ロックとして異世界のロアナプラに転生する作品である。
異世界転生作品とは高校生から若手社員くらいの年齢の主人公が物語冒頭、交通事故などで死んで非日常的な異世界へと生まれ変わる、というプロットをもつ作品群のことをいう。
よってブラックラグーンはプロットのレベルで観れば、完全に異世界転生作品の構造を持っているのだ。
ブラックラグーンと統合失調症
ブラックラグーンは2006年の深夜アニメだが、同時期には竜騎士07原作『ひぐらしのなく頃に』も深夜アニメとして放送されていた。
実はひぐらしも統合失調症的な色彩が非常に強い作品として有名である。
したがってこの年代のジュブナイルの心性として統合失調症性の心理を想定すると面白い。
ここでいう統合失調症の心理とはぼくがこのブログでいつも持ち出すラカンやユングのいう精神病理論とは異なる。それはハイデガー存在論に依拠するヴィンスヴァンガーに起源を持ち、ブランケンブルクと近い立場にある木村敏の現象学的世親病理学理論に基づく。
木村の理論によると統合失調症の心性は思春期~青年期の心性に親和性を持つという。このような心性をアンテフェストゥム(前夜祭)という。
ようするに若者は革命を求め、全く新しい世界の設立を目指し、老人は保守的となり自分が今まで依存してきた伝統や価値観を延命しようとするのだが。
若者の挑戦的で新世界を望む革新的な世界意識をアンテフェストゥムといい、これが統合失調症者の性格の特性だという。
事実、統合失調症は好発年齢が思春期~青年期なのだ。
本格的な説明はハイデガー存在論や西田哲学を少し理解してるのが前提となり、一般読者にはキツいのでここではわかりやすさを優先した説明をしてゆく。
基本的にブラックラグーン型の2006年頃の初期異世界転生作品の構成はアンテフェストゥムであり、その特徴は「今まで」から切り離された、全く新奇な「今から」の確立といえる。
ブラックラグーンでいえば禄郎としての東京での暮らしが「今まで」であり、今までから断絶した新奇な「今から」がロックとしてのロアナプラでの暮らしといえる。
後の項で説明するがこれが2010年代頃になると今までのつつがない延長としての今からを生きる予定調和を好む老人の鬱病的時間意識ポストフェストゥム(レマネンツ)が基本となる。
統合失調症と異世界転生の親和性
アンテフェストゥムに彩られた統合失調症者の若者は、しばしば今までの日常性を嫌い、そこからの解放を考える。
そのため、統合失調症の人は、整形して別人になったり名前をかえ異国に引っ越すこともある。さらには性別を変更することさえ珍しくない。
(※ラカン精神分析ではシュレーバー症例などにある統合失調症の女性化にこれと異なる解釈をしている)
ところで思春期、青年期に発病して、顔も名前も生活基盤も一新するあり方、これ自体、異世界転生的といえないだろうか。
異世界転生作品が、思春期青年期にさしかかった若者のアイデンティティ形成について抱える不安や葛藤を象徴しているのはいうまでもなかろう。
とすれば、アンテフェストゥム的にまったく新たな自己を社会的に確立したいという思い、その心理的課題こそが異世界転生には描かれているのだ。
したがって本来の若年層の心理である、今までを否定した未知なる新たな今からを担う自己の誕生が転生した主人公ということになる。冒頭で死んでしまう日常世界の自分とは、今までとしての子どもの自分なのだ。
すなわち、異世界転生における死んで今までの日常性から脱却し日常の外部である非日常の新世界へと転生するというプロットはそれ自体、統合失調症者の夢でもあり、若者が直面する自己確立の葛藤の表れといえよう。
これを若者が大人へといたるイニシエーションの形式としてユング的観点から解釈してゆくやり方もあるのだが、長くなるのでそれは割愛する。
重要なのは異世界転生作品とは本来、そのプロットにしたがって普通に作品を執筆すれば、自然とブラックラグーンのようなアンテフェストゥム作品になるということ。
だからブラックラグーンでは、非日常からの帰還として東京を舞台とした話が存在し、ロックが自己存在を問う実存的なシーンが多くあるのだ。
個(今から)と普遍(共同体、今まで)を巡る葛藤がそこにはあり、むしろその葛藤こそが個と普遍を生み出す淵源なのである。
ブラックラグーンの特徴はロックが玉虫色的に悪(新世界ロアナプラ)に染まりきらず、日常(東京)にも属さない若者のあり方を見事に描いていることにある。
本作はロアナプラと東京、日常と非日常の彼我の境界が明確に描かれ、その境界線上での葛藤がテーマとなる王道のアンテフェストゥム構造をとっている。
若年層の鬱病化、転スラとオバロ
以上より異世界転生作品はプロットレベルでは統合失調症、アンテフェストゥムへと親和し、2006年を代表する転生アニメ、ブラックラグーンもアンテフェストゥムにあると分かった。
問題は2010年以降の作品である、今回はその中でも特に人気が高く、ゆえに若者の心理を的確に象徴していると考えられる転スラとオバロを取り上げ、その心性を明らかとすることで若年層の心理の変遷を確かめる。
オーバーロードとは

| 作品名 | オーバーロード |
| 原作者 | 丸山くがね |
| ジャンル | なろう系異世界 主人公最強系 |
| 放送期間 | 一期:2015年7月7日 – 9月29日 四期:2022年7月5日 – 9月27日 |
2015年を代表する人気アニメ、転スラと双璧をなす大人気なろう系異世界転生作品。
異世界転生といっても死んで生まれ変わるのでなくソードアートオンラインとか.hackのようにゲーム世界に閉じ込められるタイプの作品にも近い。
オバロのあらすじ
かつて一世を風靡したVRMMO-RPGのユグドラシルはプレイヤー数の減少に伴いサービス終了を間近に控える。
現実世界では鈴木悟というさえないリーマン、ギルドのアインズ・ウール・ゴウンのメンバー、モモンガは、一人孤独にギルド本拠地ナザリックに残り、サービス終了の時を待つ。
ところがサービス終了の時刻を過ぎても、モモンガはログアウトされず、ログアウトが不可能になりゲーム世界に閉じ込められる。
さらにはギルドメンバーが作成したナザリックのNPCたちが魂をもちしゃべりだし、自らを主人として従い崇める。
状況を把握すべくNPCにナザリックの外を調べさせるとそこは異世界だった。
オーバーロードと鬱病心理
オーバーロードはギルド本拠地ナザリックごと異世界に飛ばされて、ゲームキャラとして異世界で暮らすことになる話。
主人公のモモンガはことあるごとにギルドの仲間たちとの思い出にふけりノスタルジーにとらわれている。
リアルをとってゲームを辞めていったギルドの仲間との思い出にとらわれ、その喪失に感傷的になる主人公は、誠実かつ忠実な従者と化したNPCからよせられる期待にこたえるため、異世界で世界征服を開始する。
モモンガは典型的な鬱病親和性格だといえる。
今までの仲間との関係に拘泥し、他者との役割関係に自己のあり方、アイデンティティの全てを見いだすモモンガは軽度の鬱病を発病しているに等しい。
モモンガがかつての仲間との思い出にふけり、その喪失をなげく心理をポストフェストゥム(後の祭り)という。
ポストフェストゥムとはアンテフェストゥムと異なり、今までを好み今までのつつがない延長としての明日を生きる主体のことをさす。
未知の未だ来ない未来に憧れる若者のアンテフェストゥムと対をなすポストフェストゥムは、今までの延長として予定された将に来るべき将来を生きるのだ。
したがって鬱病の発病は今までの秩序の喪失によって起こる。じじつ引っ越しや転職で今までの人間関係が失われるとことで鬱病を発病することは非常に多い。
依存していた秩序、対人関係がそこなわれると鬱病者は予定していた役割関係をこなす自らのあり方と役割を喪失した現実の自分のあり方とのギャップで鬱になる。
つまり予定していた今までのつつがない延長としての理想の自己に現実の自己が遅れをとることで生じる自己自身に対する負い目感情(レマネンツ)こそが抑うつ気分の正体といえる。
この自己が自己自身に遅れをとることをポストフェストゥムとかレマネンツという。
鬱病は「今まで」への依存の強さから分かるように、老人に多い。老人は今までの積み上げで生きているので今までが失われたり通用しなくなると非常に弱いのである。
したがって失われた対人関係の哀愁を中心にその取り戻しとして異世界転生の物語が構成されるオバロは鬱病型の作品の筆頭である。
またオバロは異世界といっても魔法はゲームのときと同じように使うことができ、モモンガは最強で異世界人はNPCより遙かに弱い。
そのため異世界の非日常性は完全に漂白されており未知の世界の未知性は実質機能していない。雑魚しかいないので自分の脅威が出てこず、ゆえに全部自分の思い通りにできる世界ともいえる。
鬱病性格とモモンガ
鬱病性格者は対人関係への依存が大きいことが知られる。ふるくはクレッチェマーの循環気質論にもあるように、鬱病の病前性格は対人関係の良好さを特徴とする。
また鬱病者が自己のアイデンティティとして依存する今までとは、既存の役割関係に依存することが知られる。
役割とは対人関係において成立するもので、対人関係ぬきには成り立たない。
そのため自らの実存をかけた未知へと向かう恋愛をアンテフェストゥムとすれば、秩序的な役割関係へと落ち着く結婚生活はポストフェストゥム的である。
妻がいてこその夫、子どもがいてこその父、生徒がいてこその先生、部下がいてこその部長というように、鬱病者がアイデンティティのよりどころとして依存する役割は常に他者に依存する。
ここでモモンガの性格を思い出そう。彼はNPCから承認され、その期待に応えるために偉大な主人を演じることに没頭する。
過去の対人関係に思いをはせ、いまのNPCとの対人関係を楽しむ彼は典型的なポストフェストゥムといえる。
基本的にオバロの異世界とは、失われた今までの対人関係の理想的代換え物であって、異世界が本来持つアンテフェストゥム的未知性とは無縁と言える。
ブラックラグーンからオバロへ
ブラックラグーンからオバロへの変遷は何を意味しているのだろうか。
それは若者の心性がアンテフェストゥムからポストフェストゥムへと移行したことを示す。
現代人はますます予定通りの世界を生きるようになったといえよう。
鬱病化の原因
鬱病化はなぜ生じたか。2006年頃のブラックラグーンと2015年以降のオバロでは世の中の何が変化したのか、その答えはSNSにある。
ツイッター(X)やインスタ、オンラインショッピングなどの普及が鬱病化の一因となった可能性は否めない。
ツイッターなどで生じる対人関係では他者と関係する前から相手の主義や趣味があらかじめ分かっている。
またインスタの発展で旅行で行ったことのない土地に行くにも、どこのどのインスタスポットで撮影するかなどあらかじめ予定を立て既に知り尽くしてから旅行をする。
さらにはAmazonで購入すれば、今までの購入履歴にしたがい今までのつつがない延長として、購入すべきものがオススメされる。
またZ世代では映画のネタバレを読んで、これから観る映画を決めるのも普通になってきている。
かくして現代の情報化社会とは今までのつつがない延長の終わりなき継続を特徴とするのだ。
するとネットに依存する若年層は本来あるべきアンテフェストゥム的生を構成できず若くして老人のごときポストフェストゥム的心理へと頽落する。
このことがブラックラグーン型からオバロ型へと異世界転生の変質の一因である。
くわえて月並みなことをいえば、ツイッターなどは数値へと還元された他者からの承認が価値の全てである。
より多くの人からの承認を得ることが金を生じ、その人間のステータスとなる。このような他者からの承認を過度に重視するシステムそのものが他者からの依存を特徴とする鬱病に親和するのはいうまでもなかろう。
アンテフェストゥムで要請される対人関係が数字に還元できない一回性の我と汝の邂逅にあるとすれば、ポストフェストゥムで要請される対人関係は顔も名前もない社会的役割関係としての交換可能性の高い関係といえる。
そのため数値へと還元された承認への依存はどちらかといえば鬱病的なのだ。
(※ポストフェストゥムについて詳しくはハイデガー存在論の非本来的を参照のこと、また統合失調症では我汝の絶対的二者関係からの逃避が特徴となるが、専門的議論の一切はここでは割愛する)
鬱病化と多様性とHSP
オバロ的なポストフェストゥムの意識から、LGBTQやHSPの流行を説明することができる。
LGBTQもHSPも、現実世界で損なわれた役割の演じ直し願望として理解可能な節がある。
あるべき理想像として想定された十分な社会的役割を担う自己像に遅れをとることで生じる自己への負い目感情(レマネンツ)が鬱病心理であり、オバロは、その失われた過去の理想の自分を異世界で演じ直すという願望であることが分かった。
これと同じ構造がLGBTQやHSPにも観られる。
たとえばHSPは繊細で危機や異変にいち早く気づき群れに危険を知らせ人類を救世する存在だ、とか芸術的センスがずば抜けた選民だと定義されている。
とりわけ欠かせないのがHSPは病気ではないという文言。
正直、精神の問題というのはなにが病気で、何が病気ではないなんてことは、はっきりしないし一概に規定することは不可能なのは常識である。
そもそも病気の定義からして曖昧なわけで、病気ではないという規定は非常に奇妙である。
心理学には様々な性格の類型学があるが、これは病気ではないなどと率先して主張する類型学概念は寡聞にして知らない。
病気とは、おおむね社会的な役割関係における役割の毀損を意味する概念であり、そのために病気は鬱病的負い目感情の一つである。
その証拠に鬱病の三大妄想の一つに心気妄想があるほど。
ゆえにHSP概念では、鬱病的な負い目が忌避され、病気ではない、という奇妙な文言が付け加わったと考えられる。
病気か否かへの固執、人類救済という大仰な社会的役割の主張、HSPを特徴づける奇妙なこの二つの概念規定が、損なわれた役割の演じなおしとしての転生を意味するのは明らかだと思う。
かつて仲間に囲まれ信頼されていたモモンガが、仲間を失って鬱病になる。すると今度はNPC達から崇拝され、NPC達から世界征服という絶大な役割を期待される。ここにあるのは失われた役割(理想自己)の過大な取り返しに他ならない。
そしてこの構図は、HSPが不満足な鬱病親和者に選民的な人類救世という社会的承認と役割を与える構図とぴったり一致する。
ゆえにHSPやLGBTQの流行は異世界転生作品の鬱病化と密接に関わっていると考えられる。
ようするにかつてのゲーム仲間との理想的な役割関係が損なわれ、異世界で役割の演じ直しが起きるオバロの構造は、現実世界で自己が自らに望む理想の役割をこなせず苦悩する人がHSPとして転生することで人類救済の役割と承認を社会的に獲得する構図と同じだと言うこと。
よってオバロや転スラに典型させる鬱病構造の異世界転生の台頭と流行はそれが現代人の心性と時代精神に合致しているからに他ならない。
ちなみにHSPが人類に危険を察知し知らせる選民云々という理論は、解釈であって科学的な主張ではない。人類に対する役割みたいなことは人間の解釈でしか規定できず、科学的には実証のしようがない。
またHSPは情弱ビジネスであり、高額のカウンセリングでこってり金をしぼられる被害が続出しているので、注意してもらいたい。
人気異世界転生作品で見る現代人
ここまでの話で観たような統合失調症から鬱病へという単純な変遷でかたずくのであれば苦労はない。
じつはもっと複雑なことが起きている。
なのでここからはオバロの他に現代を代表する異世界転生作品をざっくりと分析し現代人になにが起きているのかを解説する。
結論から言うとたんに鬱病へではなく、鬱病性からの発達障害へという変遷が観られる。
転スラと甘えの構造と日本文化
つぎに紹介するのは転スラ、いわずと知れた昨今一番人気の異世界転生作品であり、現代人を象徴する。
転スラとは
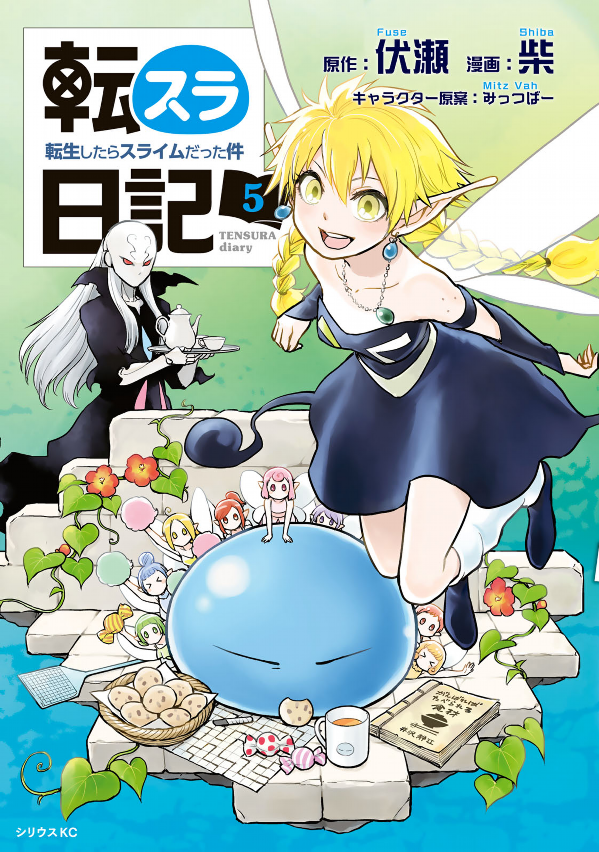
| 作品名 | 転生したらスライムだった件 |
| 原作者 | 伏瀬 川上康樹 みっつばー |
| ジャンル | なろう系異世界転生 主人公最強系 |
| 放送期間 | 一期:2018年10月2日ー3月26日 二期:2021年1月12日ー9月21日 三期:2024年春予定 |
転スラのあらすじ
サラリーマン三上悟は後輩をかばい通り魔に刺され異世界へスライムとして転生。
転生して何日かすると封印されている暴風竜ヴェルドラと出会い友達となる。
ヴェルドラからリムル=テンペストの名をもらうとスキル捕食者を使い封印ごとヴェルドラを体内に格納する。
その後、ゴブリンを助け、ゴブリン族と牙狼族が共生する村を興す。
さらに女性転生者シズと出会い、紆余曲折ありシズを取り込み、リムルは生前のシズの姿へ変身する能力を得る。
鬱病性心理と転スラ
転スラもまたオバロと同じくポストフェストゥム的な要素が強い。
転スラでも対人関係、社会的な役割関係が主人公(リムル)の動機や行動の中心となる。
鬱病者の夢といっていい内容となる。
精神分析と甘えの構造
土居健郎(精神分析家)が日本人の精神の特徴として取り出したものに「甘えの構造」がある。
土居によると甘えという言葉は日本語に固有で西洋にはそれに相当する単語は存在しないという。
甘えとは人類に根源的な感情であり母子や師弟のような上下関係をその基本とする。
たとえば日本社会の基底をなすイエ社会では、中根千枝の縦社会論にあるように、ヨコの連帯よりタテの連帯、したがって上下のつながりが基本となるが、この関係の中核をなすのが甘えだという。
対する欧米社会ではフランス革命が同じ第三身分同士のヨコの連帯による革命であったことからも明らかなようにヨコの連帯が基本となる。
また徒弟制度やお家騒動、日本の運動部の先輩後輩関係に典型される日本の上下の結びつきの根底にはアニミズム的な母性原理の作用がある。
つまり始原の母子一体の状態を理想とする甘え的なアニミズム的民族性がタテの連帯を中心とする日本社会の基盤となっているのだ。
甘えとは言うなれば始原の母子一体への回帰ないしは、その一体関係の満喫。海外には甘えに相当する言葉がないので、受け身的対象愛みたにな感じに訳される。
甘えと転スラ
ぼくは土居の甘えの構造を初めて読んだとき、まるで転スラの解説書じゃん!と思ったほどで、転スラと土居の甘え論は親和性が高い。
というわけで、日本人の心性に根ざす甘え理論と転スラの強すぎる関連性をここでは紹介する。
まず一般的に転スラの設定を精神分析的に解釈すると、死んでスライムになるのは、幼児退行を示す。
ポストフェストゥムとして観るならば、現実での対人関係など何らかの破綻から鬱病となって退行した感じ。
不定形で性別の曖昧、未分化なスライムは重度の退行を示すと解釈される。
次にスライムの最強チートスキルである捕食者、これはスライムが相手を取り込み食べて相手の能力や容姿をコピーするスキル。
じつはこのスキルを精神分析では同一化という。
土居は同一化と甘えの親和性を指摘し、明治維新後、日本が欧米文化を模倣し、技術をトレースして猿真似と言われながら、飛躍的に発展したことを甘えによる同一化の作用によるという。
リムルの象徴する捕食者のスキルは、その他の要素と照応して総合的に分析すると、甘えによる同一化を示すのだ。
またリムルは様々な種族を助け、慕われ長としてあがめられる。
そしてオバロと同じく仲間たちとタテの主従関係で強力に感情的紐帯を結ぶ。
そのため敬語によるコミュニケーションが基本となる。
土居によると敬語はタテ関係の結びつきの強さを示し、その本質は幼児語にあるという。
たとえば子どもをあやすとき、「お坊ちゃまはどっちがいいですか?」みたいな言葉づかいになる。
この言葉遣いは非常に敬語に似ていると分かるだろう。
つまり子どもという目下のものをあやすときと、目上のものに敬語で話すときで言葉遣いが非常に似ているのだ。
この上下の不思議な言葉遣いの同一性、目上の者を接待するのと子どもをあやすのとの同質性に甘え的同一化の核心がある。
母子一体の同一化とは互いが互いに呑み込まれ呑み込む上下関係の相互性を特徴とするのだ。互いに依存するカップルなどを観てもこのことは確認できるだろう。
一見して上下関係とは上と下で固定されているようでも、関係が依存的で同一化が強まると、お互いに束縛され相手にコントロールされてしまう、この相互支配性、相互主従関係が上下の逆転を引き起こす。
その最たる例が幼児語と敬語の奇妙な類似性なのだ。
日本人は母子一体の関係を至上とする幼児のごとき甘えを重視する。タテの関係、主従関係はそれ自体、甘えの産物だとえる。
ところで退行したリムルは、主人として頼られる関係のなかで役割的なアイデンティティを形成し、シズという少女の容姿を獲得するが、これも子どもっぽい見た目である。
リムルと天皇
土居によると日本人の象徴である天皇はまさに母子一体を愛でる甘えの核であるという。
天皇にはもともと補弼(ほひつ)というのがあった。
補弼とは天皇のそばについて、公務や政治の助言をする存在であり、ある意味で母である。
また天皇は純粋なる存在であり、子どものメタファーだと土居はいう。
するとリムルと天皇の同質性が明らかになる。
リムルはスライムでありシズと取り込んでからは好んで中性的な子どもの姿をとる。
さらにリムルにはスキル大賢者という業務や生活に必要な知識を助言する補弼のような存在がついているのだ。
尊き存在として敬愛され敬語で話しかけられ、補弼役のスキルを持つ子どものような姿のスライムであるリムルは天皇と酷似している。
余談だが天皇としてのリムルは鬼滅の刃でいう上限の二の鬼とも非常に似ている。
またアニメ二期ではリムルが仲間のために人間を虐殺するシーンがあるがこの種の残虐性はユング派のいうプエルエテルヌスとして論じることができるが長くなるのでそれについては割愛する。
転スラと甘えの意味
なぜ2006年時点ではアンテフェストゥム的だった若者の意識が2010年を超え出すたあたりから、加速的にポストフェストゥム的になるのか、さらには単に鬱病性格というより日本的な甘えが目立つのか。
じつはこれには日本人の近代主体の解体が関連している。
もともとアンテフェストゥム的な葛藤は、少年少女が大人になるにあたり自らの実存(アイデンティティ)を自己決定せねばならないという事情からくるもので、極めて近代的葛藤の産物だといえる。
つまり中世では農民の子どもは農民、武士の子どもは武士、結婚相手も自由恋愛などなく家と家の取り決めで決まってしまう。
そのため自己決定を基本とする自由意志をもった近代自我・近代主体といったものは形成されない。
したがって今までと切り離された新しい今からの自分を、自分の力で見つけるというアンテフェストゥム的な思春期の課題は中世にはほとんど存在しない。
ゆえに異世界転生アニメの鬱病化と甘え化が意味するのは、自由意志を持つ近代主体の解体である。
甘え的なイエ社会的日本人のあり方はそれ自体、中世的といえよう。
こうした近代主体の解体は世界レベルで進行していると臨床心理学の多くの論文で指摘されており、とりわけ日本人はその傾向が強いのだ。
もともと伝統権威主義の日本人は今までのつつがない延長を好み歴史的権威を絶対視し、新しい挑戦をあまり認めないところがある。
統合失調症から鬱病、そして甘えによる中世化、近代主体の解体については後の項目で総括する。
幼女戦記と精神分析
これまでブラックラグーン、オバロ、転スラとその変遷を観てきた。そして2006年頃まではあった統合失調症性の心理が近代主体における青年期の自己決定に根ざす葛藤であることを確認した。
さらに2010年以降はそうした青年期的アンテフェストゥムな自己決定の課題は消失し、SNSの既知的で予定可能化したライフスタイルの侵襲にともない鬱病性心理、ポストフェトゥムへと若年層の心性が変化したことを突き止めた。
そして転スラの分析から、ポストフェストゥム的な変化が近代主体の解体を示し、中世日本的な甘えの心理の支配力の強まりと密接不可分の関係にあることが判明。
というわけで、次は幼女戦記を分析することで、ラカン的な視点から現代人の心性を論じようと思う。
幼女戦記とは
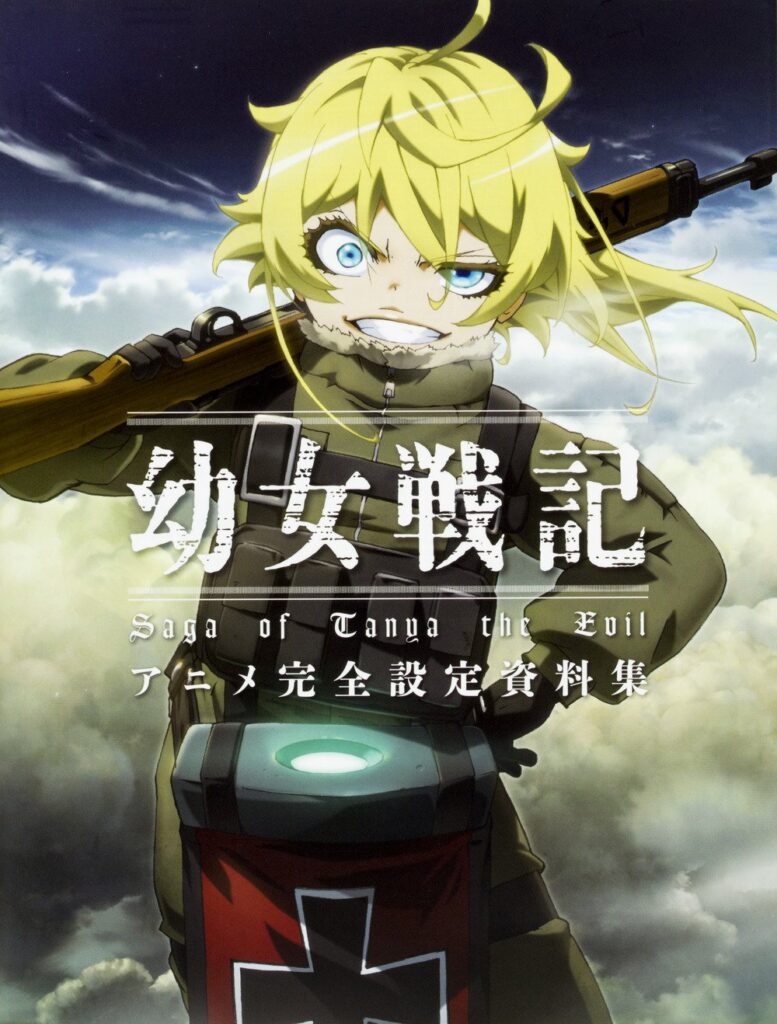
| 作品名 | 幼女戦記 |
| 原作者 | カルロ・ゼン |
| ジャンル | 異世界転生 戦記 ダークファンタジー |
| 放送期間 | 1期:2017年1月6日 – 3月31日 |
いわずと知れた大人気ラノベ原作の異世界転生アニメ。ちなみにぼくはオバロ、転スラ、幼女戦記のなかでは幼女戦記が一番好き。
この作品、誰がどう見てもエディプスコンプレックスが主題で、深層心理学好きにとって非常に興味深いのが特徴。
幼女戦記のあらすじ
合理主義の鬼畜エリートサラリーマン(30代)の主人公は同僚からの逆恨みで突き飛ばされ電車にひかれ死亡。
すると神を自称する超越的存在が出現し、神は「最近の人間は信仰心がたりない」といい現代合理主義の神無き時代に怒り、信仰心を抱かせるため主人公を戦乱の異世界に転生させる。
合理主義の主人公は無神論であり神を認めず存在Xと呼称する。
異世界には魔法があるが現実世界の20世紀初頭に近く、転生先はその当時のドイツに似ている。
女性ターニャ・フォン・デグレチャフとして転生させられ9歳で将校となり戦争の前線に送られる。
本人は安全な後方勤務で悠々自適の生活を目論むが、全てが裏目に出て戦争の最前線で戦わされ、神の思惑のもと終わりなき戦乱に巻き込まれてゆく。
エディプスコンプレックス
エディプスコンプレックスとはギリシャ神話にあるオイディプス王の悲劇の物語に由来する。
その内容は、子どもは最初、母親に対して母子一体の願望を持つが、父によってその願望を禁止にされ、もし母子一体を断念しないなら、去勢するぞ!と脅されることをいう。
そのため有名なエディプスコンプレックスとは、母子一体の願望と父の脅しによる去勢不安との葛藤を示す。
幼女戦記とエディプスコンプ
鬼畜リーマンとして神を恐れぬサディズム的な生き方で人生を謳歌していると神によって、主人公は幼女にされてしまう。
この構造は、信仰なき現代的幸福の追求(母子一体)を父なる神に禁止にされるも、その禁止を無視したため去勢されて幼女化したものと解釈できる。
ターニャは去勢されてなお存在Xを否定し挑戦的態度で父殺しにあけくれる。
たとえば劇場版幼女戦記での最大の敵であり、本作のもう一人の主人公ともいわれるメアリー・スーは父アンソン・スーの娘である。
そんな父アンソンをターニャは殺している。それゆえに父の娘であるメアリーから命を狙われる。
現代の合理主義をニーチェが神殺しといったことは周知のことであろう。現代とは人に禁止をかす父なる神を殺すことでなりたつ。
したがって幼女戦記とは、終わりなき父殺しと父に去勢され殺されたいという、根源的なエディプスコンプレックス的願望の結実とみることができる。
神(父)を殺したいという合理主義者の意識的願望の背後に父に去勢(禁止)され殺されたいという隠れた願望が潜んでいることを本作は示しているのかもしれない。
倒錯者の幻想と幼女戦記
幼女戦記の主人公は非常にサディスティックな存在として描かれている。
物語冒頭、同僚に首を宣告するシーンからして同僚を去勢する父のごときサディズムに満ちている。
ターニャの性格からして、全てを自我の思うがまま理性のもとに屈服させようという意志に満ちる。
これをラカン的な意味での強迫神経症とみる手もあるが、ここではサディスト(倒錯者)として論じる。
サディストの幻想とは一般に禁止を消し去って母子一体、つまり禁止された対象を手にすることが目指されると考えられている。
しかし幻想とは真実を隠すものであり、その幻想が真に求めるものは、禁止をつくりだすことだとラカン派のフィンクはいう。
たとえばマゾヒストの倒錯者は、相手の言いなりとなることで相手の身体の一部のごとくなり、他者と一体になることを目論むのだが。
しかし実際には相手に際限なく依存し服従することで相手から、これ以上は無理だという拒絶(禁止)を引き出すことがマゾヒズム的な幻想に隠された真の願望なのだ。
サディズムも同じで相手の大事な物を破壊し禁止することで相手に禁止を作り出し、相手の禁止に陶酔しているといえる。
ターニャは神を殺し全てを自我の理性のもとに支配し、合理的な幸福(母子一体)を夢に見ている。しかし、その夢(幻想)の背後には神よって禁止をかせられたいという願望が隠されていると考えることもできる。
ちなみにターニャが神に逆らい悠々自適な後方勤務を画策して一喜一憂できるのは神にそれが禁止されているためである。アニメで後方勤務を確信して踊って喜ぶ様、その歓喜はそれ自体が神の禁止によって作り出されているのだ。
もし神が邪魔だてせねば、達成感はなく幸福感もないことは誰の目にも明らか。
幼女戦記と倒錯の意味
哲学者ジジェクによると現代人、インターネットイデオロギーとは倒錯的だという。
じつは幼女戦記に観られる倒錯的幻想、あるいは強迫神経症者の幻想は、自己決定の根拠となる近代主体を解体してしまう。
そもそも近代的な自己決定とはフランス革命に象徴される。それは啓蒙主義であり神の死を意味する。
神の死(神の否定)が起きる前は個人の存在理由も神が決めていた。
その神(存在X)を殺し否定することで、神に代わって人間が人間の生きる目的を決定し、自らが自らの根拠となるにいたる、そのことで生じたライフスタイルが職業選択の自由や自由恋愛である。
したがって英語の主語である(I)とは、僕の理論によるとかつての神の座なのである。
つまり英語では肯定文の場合、文頭は原則として主語がくる。ということは主語の(I)は全てに先立って、決定する主体でありデカルトでいうコギトのことに他ならない。そのようなあらゆる事象に先行する文頭主語(I)はかつての神の位置に他ならない。
ここで自由恋愛についての奇妙な受動と能動の入れ替わりを確認してみよう。
僕たち、というか主語がくどい英語では恋に落ちることを「Fall in love」(恋に落ちる)という。
落ちるというのは能動的ではなく受動的であり、恋が自らの意志を超えて生じるところのものを引き受けることで生じる現象だと分かる。
恋に落ちるとは理性的な予定をつねに超えているのだ。
にも関わらずその落ちる体験を、彼らは自由恋愛であるという。
ここに奇妙な受動と能動の顛倒がある。落ちたにもかかわらず登ったのだといわんばかりに自らの意志で相手を選んだと考えるのである。
ここに、これまで論じた主体構造の変遷の根幹となる要因がある。
すなわち自己決定とは自らの意志を超えた神(他者)の意志を受け入れ、それを自らの意志とすることでなりたっている。
にも関わらず、僕たちはその経験を振り返るとき、主語を遡行的に文頭に持ってきて、他者の介在を抹消してしまう。
(※この〈他者〉の介在の抹消をラカンは強迫神経症(男、科学)の幻想S◇aと記述する。だからラカンは強迫神経症(大学)のディスクールを批判する)
本来、自由意志とは他者の意志に震撼されること、恋に落ちるようにそれを引き受けることなしには成立しない。だから引き受けることが能動性の根拠なのだ。
にも関わらず最初の引き受けを抹消し(I)という主語を文頭に遡行させることで、引き受けたという事実が消去されてしまう。
ターニャが消し去ろうとするのは、自己の根拠となるその最初の他者性としての神と考えることができる。ここに倒錯的な幻想がある。
ところで恋に落ちるとき、落ちるという最初の神(他者)の一押しを引き受けないとどうなるだろうか。
その場合は恋に落ちたことが否定されるので、人間はいつまでたっても恋することができないのだ。
もはやそこに自由意志はない。
かくして自己決定は不可能となり近代主体は解体する。恋に限らず人は何かを決めるとき、自らの存在を他者(神、存在X)から引き受けねばならない。
自分で好き勝手に選べるものは自己の根拠とはならない。その最初の自己決定における自己の根拠となる自己存在の引き受けをラカン派では禁止とか父性隠喩という。
したがってサディストが表面的に目論む禁止の消去は自由意志の主体としての自己存在そのものを逆説的に消去してしまうことが分かる。
だからこそ倒錯者ターニャは幻想の背後で神からの去勢(引き受け、落ちる)を願望するのだ。したがってターニャが去勢されて幼女となるのはターニャ自身の無意識の願望といえる。
幼女戦記まとめ
以上の議論から、幼女戦記は近代主体の解体へと向かう異世界転生的現象を啓蒙主義的な合理主義における神殺しとして示す。
したがってブラックラグーン→オバロ、転スラへの移行に神なき時代の倒錯的な幻想が関与しているといえよう。
厳密に言うとブラックラグーン(近代主体の葛藤)→幼女戦記(倒錯者の幻想)→オバロ・転スラ(近代主体の終焉)という構図を取り出すことができる。
異世界転生総論
ここからは、現代主流の異世界転生アニメに共通する特徴をとりあげ、現代人の主体の具体的な構造を解明する。
異世界転生とゲームプレイヤー的主体
昨今人気の異世界転生作品の多くはドラクエやFFのようなロールプレイングゲームのフォーマットに即しており、主人公は自らの能力値の数字をステータス画面で確認したり、今後の取得スキルの一覧を見れるものが多い。
そのためレベルアップや経験値の概念、MPやHPといった概念もある。
ゲームのステータス画面とはプレイヤーが閲覧するもので、ゲームのキャラクターにとっては超越的でありメタレベルの情報という側面がある。ステータスとは本来は世界外(ゲーム外)のプレイヤーのための情報である。
そのため、異世界転生者は異世界に対して客観的(プレイヤー的)なポジションにいるといえる。
自己の能力とは本来一義的に数値化できるものではなく状況や基準によっても変わる。
たとえば賢さならば、何を基準にするかで誰が賢いのかは変わる。学校のテストの点数なのかIQのスコアか、創造的な学説を生み出す力か、普段の言動や行動の合理性の高さか、どれを基準にするかで誰が賢いかの序列はいくらでも変化する。
しかし異世界転生作品では客観的な数値として一義的に規定されるのが特徴といえる。
ゲームのステータス情報は、一義的に絶対化された数値によって能力値を一様序列化するのが特徴。
したがって、ここ最近の異世界転生に共通する特徴は異世界のロールプレイングゲーム化といえよう。
ロールプレイングゲーム化の理由
異世界のRPG化は何を意味するのだろうか。
それは世界の外部にいるゲームプレイヤーの視点、異世界物語をその外部の客観的世界から眺める視聴者・読者の視点が、操作キャラクターである主人公の視点と同一化していることを意味する。
現代人はSNSでアカウントを持ち、何らかのキャラクターを演じ(キャラクラークリエイトし)、そのキャラクター(アカウント)をスマホ端末で操作することで現実を生きている。
またスマホの中にはあらゆる情報がつまっており、ググればスキル大賢者のごとく、なんでも教えてくれる。スマホを観れば世界中のリアルタイムの様子も確認できる。
スマホはいわば世界との接面であり、スマホの中に世界がつまっている。スマホ画面を外部から除きこむ人類は、世界を外部から操作する神の視点と変わらない。
たとえば神は天高くにおり世界を見渡す存在とされるが、GoogleマップはGPSによって天空の視点から自己の場所を表示する。
現代人の生き方はまるでゲームをプレイするようにスマホ内の分身(操作キャラ、アカウント)を操作することで成り立つ。このようなライフスタイルであり意識が反映された結果、異世界転生作品はことごくロールプレイングゲームプレイヤー化していると考えられる。
ゲームプレイヤー的主体の誕生
ゲームプレイヤー的意識は人間の主体にどのような変化をもたらすだろうか。
この理解のためには近代主体との比較が分かりやすい。
近代主体の構造はいわば、プレイヤー(神)の視点が操作キャラの視点によって限定され、神の座から引きずりおろされることを特徴とする。
つまり、自分は~な人間だ!と自己を俯瞰し、自己理解したとしても、~な人間だ!という自己理解もまた自己の主観に過ぎない、と考えるのが近代主体であり、その特徴は自己言及的な再帰性にある。
対するゲームプレイヤー的主体は自らを俯瞰し自分は~な人間だ!と自己理解するとき、自分は~な人間だ!という解釈が絶対的で唯一の客観的事実という認識を伴う。
いうなれば自らを俯瞰する自意識が、自ら(操作キャラ)へと限定されず、神の視点に固定されてしまうわけだ。
この種の意識の典型としてひろゆきなどが上げられる。ひろゆきはしばしば~は頭が悪い!と連呼するが、頭が悪いというのは主観的な感想に過ぎず頭の善し悪しに客観的基準は存在しない。
強いて言えば知能指数の高低は客観的な基準かもしれないが、彼は知能指数という指標を否定しているので、個人的な感想をおしつけているのが分かる。
このような短絡的な言動の氾濫は、自分の個人的な価値観が客観的な神の価値観と癒着しているといえよう。
世界の外の神の視点へと同化した主体構造がゲームプレイヤー的主体の特徴とえいる。
ファクトチェックを叫び客観性に拘泥して攻撃的となる現代人のあり方は、自己の価値観が客観的真理と同一化可能であるというゲームプレイヤー的認識によって惹起されたキケンなイデオロギーに過ぎない。
しかしこのようにいうと、現代人だって個人的な意見や価値観を持つという反論があるかもしれない、それについて言えるのは、現代人が自己の価値観を相対化して個人的な意見といったところで、今度は自己の価値観を相対化し個人的と規定する自己俯瞰意識が神の視点と癒着すること。
だからどこまでいっても現代人の意識は外へ外へと逃げてしまい限定されることがない。
ところでこのようなゲームプレイヤー的主体のことを臨床心理学では、発達障害とか非定型発達と呼ぶ。
ステータスと一様序列
異世界転生作品では一義的に規定された数値化されたステータスを閲覧できるが、このことは現実世界での一様序列化に相当している。
たとえばSNS時代の人間の価値は収入と承認数によって規定される。
フォロワー数という数値が唯一の価値になりつつある。
フォロワー数は金になるため、フォロワー数は現金等価物ともいえるだろう。実質的に価値基準が一つしかないため、人間の価値はフォロワー数によって一義的かつ客観的に記述できるのだ。
かつては多様な価値観があり、お金や承認とは異なる個人的な価値観というものが認められていたがSNS時代ではあらゆるインセンティブは承認と金に還元される。
したがって一義的に人間の性質も数値化して記述可能となる。自分と異なる価値観は実質的に現代には存在していないのだ。
このような現代社会のおける価値の一様序列化も、ゲームプレイヤー的主体化の要因である。
多様性社会とはその本質は一様序列化社会に過ぎない。各人が自らの価値を絶対的に客観的な価値として主張することで多様性が叫ばれているとうのが実態である。
したがってLGBTQやHSPなどあらゆる属性は一つの主人公キャラとしての社会的承認コードに過ぎない側面もある。
はめふら
ここでは近年のゲームプレイヤー的主体性を特徴付ける異世界転生作品、通称はめふら『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった』について、簡単に触れる。
はめふらは2020年にアニメ化したなろう系異世界転生ジャンル。
主人公のオタク女子高生が生前好きでプレーしていた乙女ゲームの世界に転生してしまう話。
主人公はゲームをクリア済みのため、異世界のこと、さらにはそこで次に何が起こるかを知っており、そのプレイヤーとしての知識を生かして困難を乗り越えると言う話。
もう説明はいらないだろう、これが現代人のゲームプレイヤー的意識なのだ。世界の外部の視点をもってこの世界を生きている、それが現代人であり、スマホの画面世界の境界なのだ。
主人公最強化
最近の異世界転生の最大の特徴に主人公が最初から最強という設定がある。いわゆる俺つぇーものが多い。
オバロも転スラも典型的なチートスキル持ち主人公。
最初から完全無欠に近い最強の絶対的存在へと到達している意識は現代人の特徴といえる。
このような完全無欠の最強キャラ(神)となり、多くの仲間から絶対的な信頼を寄せられる主人公を特徴とする昨今の異世界転生作品のあり方もゲームプレイヤー的な意識によって説明可能だ。
プレイヤー(神)として世界の外部の視点に同一化する現代人の意識とは、自らの欠如(禁止)の否定によって生じる。
つまり自分の価値観が客観的な絶対的価値観(神の価値観)ではないことを自覚するためには自己否定が必要となる。
自らを俯瞰し自己規定する現代人の意識が依拠する一様序列的価値観を、一つの個人的な価値観に過ぎないとすることは、自らと異なる他者の価値観を自己と対等に認めることで可能となる。
自己の価値観を唯一絶対とする限り異なる価値観は敵となり、俺かお前かどっちが絶対の価値観かということで争いを生む。
かくして自分の価値観を個人的な価値観として限定することは、自己否定を意味する。そこにあるのは、もはや自分の価値観は絶対ではない、という否定の意識である。
ところで、ぼくはアジア人だ、というとき、この自己決定はヨーロッパ人ではないといった自己の不可能性によって支えられる。
もしアジア人こそが万能で最強、という認識であれば、アジア人の外部は無(価値)に等しい。
そうではなく、自己の限界を引き受けること、限界を知ることとして、自分がアジア人だと受けいる場合、アジア人はヨーロッパ人ではないという不可能性、ヨーロッパ人であることの禁止によって成立する。
つまりアジア人という境界は禁止による自己否定によって可能となるのだ。
よって自らの価値観を個人に限定し、異なる価値観の他者と等し並みに扱う人権意識もまた自己否定(去勢・禁止)によって可能になると言える。
そのため転スラのリムルが、あらゆるスキルをコピーできることは自己否定(不可能)の否定ととることもできる。
自己否定を持たないゲームプレイヤー的な意識において、自己像はなんらの限定も被らない不定形のスライムのような状態が理想なのかもしれない。
どんな形にもなるスライムはあらゆる可能性の総体(最強)であり、ぼくは~である!というような具体的な限定(禁止)を一切引き受けない現代的主体と言えるだろう。
鬱病からゲームプレイヤーへ
統合失調症から鬱病へと変遷し、鬱病性心理がゲームプレイヤー的主体(発達障害)と親和することを確認した。
ここでは旧来の鬱病と異世界転生に観られるゲームプレイヤー的な鬱病心理との差を簡単にまとめておく。
昔の鬱病の事例
精神医学の巨人、木村敏が多くの論文で紹介する事例を取り上げる。
中小企業の社長のお抱え運転手の中高年男性。
彼は長年、社長お抱え運転手として働いており、会社が成長して大きくなってきたので、社長にそろそろ車も高級外車にしませんか、と進言する。
社長は高級外車に買い換える。
これによって運転手は鬱病を発病。車が立派になり責任が増し荷が重くなったという。
鬱病の変遷
上の事例では、今まで慣れ親しんだ車の運転手という役割秩序(インクルデンツ)が崩壊したことで発病に至っている。
鬱病というと降格とか離婚とかをイメージするかもしれないが、じつは昇進も鬱病の要因となる。
この例から明らかに、旧来型の鬱病における今までのつつがない延長としての理想の自己像とは、現実に即した分相応の自己像であることが多かったのだ。
ところがHSPやオバロ、転スラなどを観ると非常に大仰というか非現実的なレベルで肥大した役割関係が渇望されているのが分かる。
このような大仰さは再現のない承認欲求を求める現代人の意識の特徴なのかもしれない。
ゲームプレイヤーが神の視点に同一化するように、全知全能の神としての究極の理想自我が求められているのだ。
この点については主人公の最強化の項目での説明がそのまま当てはまるだろう。
ゲームプレイヤーの彼岸
最後にゲームプレイヤー的主体の行く末について簡単に解説する。
異世界転生に限らず昨今は主人公最強作品が多い。
枚挙にいとまがないが、たとえば『勇者、辞めます〜次の職場は魔王城〜』や『ワンパンマン』はその典型だろう。
こうした作品は、神と化しゲームプレイヤー化した現代人が、自己否定(禁止)のまったくない最強の状態から物語りが開始する。したがってその物語のミッションは禁止なき現代において自力で自己否定を作り出し、近代主体として新生するため試みであるとも解釈できる。
こんご禁止を欠いたポストモダン(ゲームプレイヤー)の主体が、どこへ向かうのか、その答えは主人公最強系作品に託されていると言えよう。
ここではブログ用に本格的な解説はさけ、駆け足で異世界転生の歴史を概観し現代人の心理を探ってきた。
読者になんらかのインパクトを与えたと願いたい。
ここまでの結論を圧縮
2006年頃はアンテフェストゥムという今までを否定し全く新しい今からを生きようとする若者らしい心理が異世界転生の中心であり、その最たるモデルがブラックラグーンである。
異世界転生の死んで全く未知の非日常の異世界で新しい人生を生きる、というプロットは、通常はアンテフェストゥム的な心理に親和し近代主体としての葛藤を示す。
しかし2010年以降、異世界転生作品がポストフェストゥム化する。ポストフェストゥムとは、鬱病者の時間意識で、今までのつつがない延長としての予定された今からを生きるという保守的な意識になる。
SNS時代では、あらかじめ予定された世界を生きるようになってきており、そのことが鬱病化の進展の一因。
日常秩序の予定された公共世界を生きることが重視され、それゆえ鬱病では日常性の基本となる他者との役割関係への依存が強くなる。
オバロも転スラもその意味でも鬱病的で、現実世界での役割関係の不満から鬱となり、失われた役割を異世界で演じ直すことが志向される。
こうした鬱病性の異世界転生心理はHSPやLGBTQと同型である。HSPにおいては負い目ある人々に、新たな役割をあてがい人類の救世という大仰な社会的役割を与え、HSPへ転生させる。
また転スラは土居健郎のいう甘えの構造を持っておりリムルは天皇のメタファーといえる。転スラの対人関係は母子一体のタテの繋がりの強さを基本とし、甘え的な関係性を示す。
よって日本的なイエ社会的対人関係が現代人の心性としての鬱病心理の背後にある。
幼女戦記は倒錯的であり、現代人のあり方は倒錯者の幻想に近い。また引き受けることを拒絶し能動性と主体性が受動なしに成り立つという誤認によって逆説的に近代主体性は解体してしまう。それゆえの主体を巡る受動と能動のアンビバレンスが幼女戦記には観られる。
異世界転生の共通点として数値化されたステータス画面の閲覧と主人公の最強化がある。
数値化されたゲームのようなステータスの可視化は、現代社会の一様序列化(フォロワー数だけが価値)とも関連し現代人の意識がゲームプレイヤー化していることを示す。
ゲームプレイヤー化した意識とは自己を俯瞰する自意識が世界の外の神の視点(絶対的客観性)と融合する意識である。
現代人のSNSアカウント(操作キャラ)をスマホ画面を操作することでコントロールする意識と、世界外の知識や視点(ステータス参照)を持つ最近の異世界転生の主人公の意識は近い。
一様序列や歪んだ多様性によって自己の価値観が自己という個人の価値観に過ぎないという限定をうけず、俺の価値観=唯一絶対の客観的価値観という癒着を引き起こす。
この限定を受けないあり方は幼女戦記でターニャが神(存在X)に象徴される他者性を引き受けないことにも対応する。
主人公の最強化(神化)もこうしたゲームプレイヤー意識の一側面に過ぎない。
異世界転生作品のゲームプレイヤー的鬱病化は、自己否定のなさ、限界と禁止の否定、情報化社会の既知性などによって生じている。
禁止、自己否定、限界、境界といったものをもたない現代の主人公は最初から最強とならざるえない。
ワンパンマンなどの主人公最強系作品が、いかにして自力で禁止を見いだすかを分析することで、袋小路の現代人の行く末が分かる。




コメント