うたまるです。
今回は松本卓也著の『創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで』を紹介します。
この本、古代ギリシャのプラトンの詩人狂人説から始まり、20世紀後半から現代にかけて影響力を持つドゥルーズの表層の芸術論までを包括して、人類史における芸術と芸術論の歩みを人類と狂気との関係性において体系的論じた名著。
アート志向の方から、文学者、脚本家、映画や漫画、ゲーム好きの人にとって本書は、とくに興味深い内容となっているので、この記事ではその内容を要約、解説して魅力を紹介します。
本書の概要
| 発売日 | 2019年3月13日 |
| 頁数 | 384頁 |
| 出版社 | 講談社 |
本書は最初に古代ギリシャ時代における狂気と芸術の関係をプラトン主義を中心に論じる。
次に3世紀後半にローマで力をもったキリスト教によって古代ギリシャ的な創造と狂気がいかに変化したかを概観。またプラトン主義的な芸術狂気論が近現代の病碩学における統合失調症至上主義の原典であることを示す。
次に15世紀にフィチーノがメランコリーに創造を見出した論考を参照し、そこからデカルトのコギトと狂気の関係を示す。
さらにカントにおける神と狂気の疎外を詳しく論じ、ヘーゲルによって狂気が克服されてしまったことを明らかとする。
しかしその一方でカントやヘーゲルが処理したプラトン的な狂気が理性へと回帰し世界初の統合失調症者で詩人のヘルダーリンが現れる。ヘルダーリンに典型されるように排除され克服された狂気が芸術や創造、人間の真理として回帰してきた歴史を捉える。
またヘルダーリンの狂気と創造がハイデガー哲学における否定神学的な構造のベースとなったことを確認しラカン、ラプランシュ、ブランショ、ヤスパース、フーコーなどを参照しつつ近代における狂気が主体をめぐる自己欠如にあることを洞察してゆく。
天の神にあった狂気は深淵の地下であり欠如としての神へと移行し、これによって統合失調症と近代主体とが可能になったことが解かれる。
さらにドゥルーズの芸術論を中心に近代的な統合失調症モデルの狂気と創造、芸術を深層のアートとし、現代の芸術およびこれからの芸術を表面のアートとして発達障害(自閉症スペクトラム)を中心に読み解く。
またこれと関連して草間彌生を深淵のアートであり近代の統合失調症モデルに、横尾忠則を表面のアートとして読み解きその具体的なあり方を確認する。
最後はドゥルーズにおける意味の論理学から批評と臨床への移行を深層からの表面の分離と表面への移行として論じ、表面に留まりつつ偶発性によって不可能なもの、深淵へとアクセスする可能性を探る。
神々の狂気にはじまり、アリストテレスやルネサンス期に見られたメランコリー(鬱病)と創造との関連を解く論考にも触れつつ、近代以降の統合失調症や神経症における芸術表現のモデルを確認し、ドゥルーズによる他者なき自己完結的な表面のアートへの移行を示す。
かくしてプラトン主義への抵抗を主眼とする芸術論が述べられる。
本書は人類における狂気の空間的位置づけの変遷によって芸術や創造がどのように変遷してきたかを解き明かし、そのことでアートの行く末を示すものである。
概要のまとめ
プラトン主義⇒アリストレテスの鬱病論⇒反プラトン主義としてのデリダとドゥルーズ紹介⇒一神教アウグスティヌスによる狂気と神の切断⇒デカルト→カント→ヘーゲルによる狂気の排除と克服⇒ヘルダーリン=統合失調症の誕生と病碩学の統合失調症中心主義(プラトン主義)⇒統合失調症の否定神学とハイデガーの存在論と真理⇒ラカンの否定神学的構造主義とダリのパラノイアクリティックとフーコーによる外の思考⇒デリダによるラカンとフーコーへの批判⇒ドゥルーズによるプラトン主義の乗り越えとしての自閉症スペクトラムのアート論(表面のアート)
古代ギリシャの創造と狂気
古代ギリシャではプラトンが狂気を神々に通じる正統なものと、神々と関係ない堕落したものとに二分する。このような正統と非正統を分ける考え方をプラトン主義と呼ぶ。
プラトンは芸術家である詩人の創造をダイモーンから与えられる言葉によってもたらされると考えこれを詩人狂人説と呼ぶ。とつぜんにダイモーンからの啓示を受け、そのインスピレーションによって創作をなすのが詩人とされる。
ここでは狂気とは日常の意識に、その断然として突如、侵入してくる声であり表象のことに他ならない。したがって詩人の狂気はここでは自己の連続性の切断であり、自己の意識に脈絡なく生起する他者(ダイモーン)の声だとえる。
直観的に世界の真理を告げる神の声、これを古代ギリシャの人々はダイモーンと呼んだ。ダイモーンとは天の神々と大地の人々をつなぐ天と地の間の大気中に位置する媒介者のことで空気中にある聖霊のようなもの。
※天の神々⇔ダイモーン⇔地の人々
人から神への献身や神から人へのメッセージをつなぐのがダイモーンなのだ。
したがってプラトンは、神々と繋がるダイモーンによる狂気のみを創造や芸術と関連付け価値をあたえ、神々と繋がることのないアル中やメランコリーといった水平方向の狂気を三流の狂気として創造から切断してしまう。
プラトンが三流としたメランコリーは鬱病のことで、黒胆汁病を意味する。プラトンはヒポクラテスの四体液説をベースにしてメランコリーを解釈している。
四体液説とは人間の心身の健康が血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4つの液体のバランスによって支えられ、これらのバランスを欠くことで心身に異常を来すというもの。
メランコリーは肝臓で創られる黒胆汁が排出されずに体内に鬱積することで生じると考えられ、そのために黒胆汁病=メランコリーと名付けられた。
またギリシャの身体観は理性の頭、情熱の胸、獣の腹、の三分割からなり、腹のもっとも底にある肝臓は獣の器官とされ、否定的に捉えられた。しかしプラトンは低い価値の肝臓に予見を与えるという肯定的価値を見出してもいた。
またプラトン主義の正統と非正統の二項対立、血統主義的な考えは、プラトンがエクリチュール(書かれた言葉)よりパロール(話される言葉)に絶対的な価値を与えたことにも表れる。
このような正統と非正統、神々の垂直と大衆の水平、話言葉と書き言葉などの価値の二元論は近現代の病碩学に主流となる芸術と創造の統合失調症中心に通じる。近現代の病碩学では芸術はもっぱら統合失調症者の特権として論じられる傾向が強く、本書はそのような統合失調症主義を悲観主義的パラダイムと称し、デリダらを引用してこれをプラトン主義と重ねる。
さて古代ギリシャでもプラトンの弟子のアリストテレスは、メランコリーに創造性と芸術の可能性を読み解き、メランコリーを高く評価した。ところがそれきり鬱病と芸術が結びつけられる論考はなりを潜め、両者をつなぐ論考は15世紀のフィチーノまで待たねばならない。
しかしそれも19世紀のヘルダーリンの登場を契機とした統合失調症の誕生によって一蹴され、20世紀以降は統合失調症がアートと創造の中心として論じられることになる。木村敏の芸術論も統合失調症中心主義のパラダイムに属する。
さてプラトン主義を否定したのがデリダであった。
デリダは脱構築の手法をつかってプラトン主義を内在的に批判する。プラトンは前述の通り話し言葉の優位を語るのだが彼は話し言葉の優位を魂に刻まれた言葉だから話し言葉には価値があるという言い方をする。
つまりデリダは話し言葉には魂に書き込まれた書かれた言葉があるから価値がある、とプラトン本人が話し言葉に対する書かれた言葉の優位を認めている、という指摘をしたのだ。
このように外在的に書き言葉のメリットを語るでなく、内在的にその矛盾をついて主張を覆す手法を脱構築という。
またプラトン主義の特徴はプラトンのイデア論にも見出される。プラトンのイデア想起説ではカニを見たり食べたりして、それをカニと認識できるのは魂が天界にいたころにカニそのもののイデアを見ていたからで、そのイデアのコピーである現実のカニを見たり食べることで、カニのイデアを想起して、それをカニと認識できるという。
ここではカニはカニのイデアのコピーに過ぎず、イデアに絶対的な価値がおかれる。
これについてドゥルーズはカニカマのようなものを考え、それをシミュラークルと呼び、イデアから独立した価値を持つという。つまりカニカマはカニのイデアのコピーではないのでイデアとは関係がなくそれ独自の産物であって正統的なカニのイデアの系譜から切断されて独自に存在するというわけだ。このようにポストモダンではプラトン主義的な正統な系譜は解体され、非嫡出的なもの、カニカマなどに価値が置かれる。
プラトンであればカニカマは無価値なものと呼んだだろう。
僕なりにわかりやすくまとめると、たとえば天皇は父系をたどることで神武天皇にまで系譜を遡ることができ、天皇は父系の血統の正統性によって価値づけられている、このようなあり方がプラトン主義であり、イデア想起説から詩人狂人説にまで一貫して見られるプラトンの根本的な思考の形式となる。
そしてこのプラトン主義が近現代における病碩学の統合失調症中心主義のパラダイムに重なるという。
そんなプラトン主義の否定者としてデリダ、ドゥルーズが登場したのだ。
キリスト教と狂気
プラトンにおいて評価されたダイモーンは3世紀にローマがキリスト教化するとキリスト教の力によって変形させられる。
キリスト教では神、悪霊、人間の三つ組みがあり悪霊は天の神と大地の人間の中間の空気中にいる。しかし悪霊はダイモーンと異なり神から排除された悪しきもの。
そのため修行中の人間をたぶらかし怠惰に陥らせる。修道士の厳しい禁欲の修行で想起される喪われた過去の生活、喪失感が人を怠惰にさせ禁欲生活の妨げとなる。
このような喪失感とかつての誘惑をもたらすものとして悪霊がいるのだ。
アウグスティヌスはこの悪霊をダイモーンと重ね合わせ、ダイモーンこそが悪霊であるといい、デーモンに変えてしまう。かくして神からダイモーンは切り離されたのである。
悪霊による怠惰のあり方はメランコリーに一致する。
喪失を嘆き無気力となるあり方はメランコリーのあり方の基本だからだ。メランコリーでは自分だけが遅れていて時間感覚も遅くなることが知られる。
このような怠惰がいかに創造へと結びつくのか。
メランコリーは黒胆汁が鬱積して高密度に一カ所に留まることでなるのだった。このような引きこもって留まるあり方は、じっくりと一つのことを考えたり周りの意見にノーを突きつけて独自性を打ち立てることに通じると考えられる。
また、喪失したものはそれが喪失していることによって、目指すことができる。そして怠惰は正しいことが知られているからこそ可能となる。だから弁証法的に怠惰は真理へと通じているともいえる。たとえば人間が理想を目指せるのは、現実から理想が欠如することによってであるし、希望が見出されるのも、現実における欠如によってである。
人は始原の自然との連続性、神々との連続性を喪ってこそ、それを弁証法的に目指すことができる。このような喪失をめぐる高次の獲得への運動をなす喪失感としてメランコリーは創造性と関連付けられるのだ。
デカルトと狂気
デカルトは病碩学ではスキゾイドだとされる。スキゾイドとは統合失調症ではないが統合失調症的な性格をしている人のことをいう。
そんなデカルトは方法序説によって近代の科学的な世界観を確立した偉大な数学者兼哲学者である。
方法序説とは明証、分析、総合、枚挙によって世界を認識せよというもの。明証は日本人が大好きな権威様が言ってるから正しいという土○的な判断を禁止し、権威によらず自分の頭で理論的に判断しろ、ということ。
分析は物事を判断するとき、細かく分割して考えろということ。総合は分析を繰り返し細かく積み立てた推論を総合して全体を明らかにしろということ。
枚挙は総合によって得られた結論に満足せず、再検証やチェックをやり続けろということ。
方法序説は学問的思考の基本となる。
さて、デカルトのコギトといえば一般には科学的な世界認識を可能とする基礎づけの主体のことだと理解されていえる。
※基礎づけは普遍認識の確立を意味し、反基礎づけは相対主義を、ポスト基礎づけは両者の止揚を示す哲学用語
しかし、それは違うらしい。
本書ではデリダや内海らの論考を引用してそのことを分かりやすく示す。
コギトはそもそも悪霊に取り憑かれ欺かれる可能性を考えることによって初めて可能となる確信の主体だ。一般には客観が主観と一致せず可疑的なために何一つ確かなことが言えない、という問題を克服するために疑いえない存在としてコギトが取り出されたと思いがちだが、そうではなく悪霊に取り憑かれるたびに、その悪霊を自己であると考え悪霊にコギトの御札を貼ることで辛うじて成立する自我としてコギトは取り出されている。
本書ではこれをデカルトの三つの夢の分析を軸に論じてゆくが、ここではコンパクトな要約のために、本書とは少し異なる説明も交えてこのことを示そうと思う。
ようするにコギトとは私は悪霊に幻覚を見せられているだけかもしれない、夢を見せられているだけかもしれない、という懐疑が前提となって、そのように疑い思うところの自分は疑いえないというもの。
私を欺くところの悪霊がみせる幻覚や想念、これがダイモーンに相当することは明らかであろう。
つどの想念が私でなく他者によるものだという不安がこの疑念にはある。
これは後のカントの統覚の解説を見るとよく分かるのだが、ここでは単純化するために意識を想念の生じる場と考えてみよう。
するとたとえ悪霊の想念が意識の場に生じたとしても、意識という場それ自体は私とされる。
つまり意識(主観)という場にどんな悪霊が取り憑いたとしても、そのような悪霊に取り憑かれる場それ自体は私である。
※場としての私は、今この瞬間の主観性(今ここ)を私とする限り他者とはなりえない、場たる主観性をこそ私とする限り絶対に場は私である、ただし悪霊に取り憑かれるだけの場所には能動性がないので基礎づけの主体(主語)とはならない
そして、私という場において生起する想念は、どんなに断絶的で闖入的、異物的であろうと私という場においてある限り私の想念である、このように考えるのがデカルトのコギトなのだ。
その証拠にデカルトは「私に(於いて)は、私は熱を感じる、と思われる」というような中動態的内省からコギトを取り出している。
つまりデカルトのコギト論とは、つど他者性を内在しうる自己のうちに生起する悪霊の声をして、その声に取り憑かれるところの意識なる場、それこそが主観=私なのだから、それはどんなにダイモーンに思えても私の意志なのだ、というギリギリの防衛を演じている。
デカルトのスキゾイドの性格に鑑みてもこのように理解するのが正しいのは論理的に疑いえない。
だからコギトは亡霊に取り憑かれることを疑い考えることによってしか確定しない。そもそも悪霊であり狂気とは意識の断絶であった。だから亡霊に自己性の御札を貼り付けるだけのコギトは確信の主体ではあっても、科学を基礎づける主体とはなりえない。
コギトをつど可能とする内省的懐疑そのものが一つの想念に過ぎないのだから、まったくもってコギトとは頼りなく基礎づけの主体とはなりえない。場に取り憑く悪霊が疑い考えるという想念を不可能にすれば、そこまでの話なのだ。
まとめよう。デカルトは方法序説によって近代の科学的世界観を準備し、ダイモーンに取り憑かれることによって辛うじて成り立つ主体としての自我を提唱した。
よってデカルトは狂気にコギトの御札を貼り付けることで他者と分離されたコギト=我を可能とした。
カントと狂気
デカルトの弱々しいコギトを本格的に近代化したのがカントだ。
カントは病碩学的にはノーマルとされる。
カントは主観と客観の不一致の問題に挑んだ哲学者で神を人間の世界から追放することで、主客の不一致問題を解こうとした。また機械論的な自然と形而上学的な精神との統一もカントの問題意識となっている。
そんなカントは純粋な客観(物自体)は神だけしか認識できず到達不可能だという。
そのため世界は人間の認識装置である感性ー悟性ー理性に相関して表れるという。このとき完成ー悟性ー理性は人類に共通しているから、自然界から物理法則のような普遍的規則を取り出すことができるという。
※人間の認識装置とその志向性によって世界を捉える哲学を相関主義と呼ぶ、なお本書で触れられるメイヤスーは相対主義と相関主義の区別がついていない
また道徳に関する精神の徳をなす自由もまた感性ー悟性ー理性によって認識されるのだから同じく普遍的法則を取り出せると考える。
つまりカントは人間の認識できる全てを神から切り離している。そもそもカント以前の認識装置ではアクィナスの感覚ー理性ー知性があるが、知性は人間の理性より高次に位置づけられる。ここで知性とはカントの悟性に対応するもので感覚対象に与えられる意味であり神々から受け取る直観として現れる対象の真理。だから知性とは神の知に対応する。
ところがカントでは知性=悟性は人間の理性の下に位置づけられ神から完全に切断されてしまう。
かくしてカントは神(父)を人の世界から追放してしまったのだ。
これにより狂気も人間の外部に排除された。じつはカントの哲学は狂気に対する防衛の運動として捉えることができる。
というのもカントはヒューム(因果律の主観性の論考)やルソー(スキゾイド)などの狂気の可能性に触れ、狂気についての論文をいくつか残す。カントにとって狂気は大きな問題だったと考えられる。
じじつ人間の理性の内なる狂気に対する防衛の運動として見るとカント哲学の変遷がうまく説明できる。
たとえばカントは脳病試論において人間の狂気を3種類にわけ、それを感性、悟性、理性、それぞれの異常に対応させる。
感性の異常(幻覚)を狂気、悟性の異常(関係妄想など)を狂疾、理性の異常を錯乱、と呼ぶ。
そして悟性も理性もない動物には錯乱する条件がないという、つまり理性ある人間とは錯乱しうることを条件とする、と言ってるに等しい。つまりカントは脳病試論では理性という人間の内側に追放したはずの狂気を回帰させているのだ。
ところがカントは理性のうちの狂気への不安から後にこれを超越論的統覚の理論によって排除してしまう。
統覚とは人間のあらゆる想念にはアプリオリに「私は考える」という自己性が刻印されるという考え。
つまりつどの想念にもし私が考えるが刻印されねば、思い浮かんだイメージや言葉は他者によるもの、悪霊によるものとなってしまい自意識が解体してしまう。
つどの想念から自己性が消えれば他者のものとなるわけだ。ダイモーンの声を聴いたというソクラテスには、私は考える、が刻印されない他者性の言葉が生じ、それがダイモーンと呼ばれていた。
カントはアプリオリに統覚が生じるというが、これは明らかに無茶である。まず子どもが排除されている。カントの世界には子どもは存在しないことになる。子どもは人形や縫いぐるみに魂(主体)があると思い込んだり、自分の考えが親にバレていると思い込むことが知られている。
子どもにとってつどの想念表象は他者が考えるでもあり私が考えるでもあるような未分化な状態であって統覚など成立していない。
だから人類に内面の自他の分離(統覚)がアプリオリに前提されているのなら、子どもは人間ではないことになる。私とか他者が分離しきっていないからこそダイモーンやアニミズム的な物の魂が生じるのは言うまでもない。
つまりカントは脳病試論でとりだした理性に内在する狂気の可能性を統覚によって再び排除したのだ。
しかしその防衛には限界があり、やはりカント哲学の中に人間の狂気の可能性は回帰することになる。
それが人間学。人間学はカントが統覚を提唱したあとに書いた狂気論である。
人間学では統覚は破棄され、構想力というイメージを産出する力によって4種類の狂気が検討される。
アメンチア、狂気、狂疾、錯乱、ヴェザニアである。ヴェザニアは脳病試論での錯乱に対応する。
構想力は人間に固有のイメージする力、想像力を支えるものでやはり狂気は人間の理性へと回帰しているのである。
さらにカントの第三アンチノミーも狂気への防衛の痕跡がある。第三アンチノミーについて、本書では説明があまりないので、僕なりに勝手に解釈したものを以下に示す。
第三アンチノミーは理性の限界を論じるもので、決定論的な物理世界に生きる人間は物理的な運動方程式に支配され自由意志はないと考えられる。
しかし自由意志がないとすると因果律的な自己の運動は無限の過去よりきたる現在を説明できない。永遠に決定論的な因果連鎖を遡れるなら今現在にたどり着くことがない。
因果の鎖に始点を想定してみても何もない無からは何も始まれない。このとき始点というのはそれ以前の状態からの断絶であるから原因のない独立した主体であり自由意志に相当する。
つまり自由意志の否定によって因果連鎖を断ち切る始点としての自由意志が要請されるが、そもそも何もないところからは自由意志を含め何も始まれない。
概ねこんな感じが第三アンチノミーだと想像する。
※第三アンチノミーはヘーゲルや現象学で解ける、カントのように理性をスタティックに捉える限りアンチノミーは解けない
カントはこのアンチノミーに対して、理性の限界だといい考えるのをやめてそういうものだ、と結論してまう。
じつはこのような思考放棄こそが狂気に対する近代的な防衛の典型とされる。じじつ第三アンチノミーは緊張病の統合失調症のあり方に対応している。
緊張病では自由意志によって主体的に行為しようとする瞬間、決定論的な運命が作動して、自由意志とその否定とが相克することで行動不能の緊張状態になる。
つまり自由意志の「成立と不成立」のアンチノミーによって主体がロックされてしまうのだ。カントはこうした近代の理性に内在する狂気を思考放棄によって乗り越えている。
このような克服は近代人が自らを交換可能であると同時に交換不可能であることを深く考えずに自明とすることに対応する。
交換可能とは因果律の社会で社会の決められた因果的連関構造に組み込まれることを意味する。つまり会社員なら会社員、狙撃手なら狙撃手という交換可能な社会の因果連関の歯車に組み込まれつつ、同時に一切の交換可能性に還元できない単独的で個別的な因果性の外部としての属性をもち、そのアンチノミーについて、気にしないでいれるのが近代人ということ。
主語的な同一律が優位で物とのアニミズム的連続性が遮断された近代言語空間において、このアンチノミーが生成され、このアンチノミーのために統合失調症が可能となるといってもいい。カントのアンチノミーという狂気=穴に対する思考放棄は見事な近代的狂気への防衛であり結界といえよう。
またカントは主客の不一致の問題を神の追放と認識装置の普遍性によって解決しようとしたがドゥルーズはカントについて、主客の不一致の問題は感性(ノエシス)と悟性(ノエマ)の不一致の問題に移っただけで解決などしていないという。
※この指摘は鋭いと思う、この問題に取り組んだのがフッサール現象学ではなかろうか
また統覚以前の無人称性の、おそらくは中動態的な主体性への着眼がドゥルーズにはある。
統合失調症について補足すると、統合失調症は水平方向の交換可能性の世界によって主体が埋没することを嫌い、未来先取り的(アンテフェストゥム的)に垂直軸の未知性の未来へと超越することで、自己主体を確立しようとする。
しかし超越的理想への早急な到達というミッションはまず成功しない。そのためそのような跳躍的な主体の確立は挫折にいたる。かくして水平方向の日常性の前に主体は呑み込まれ、自由意志なき隷属を余儀なくされる。
このように統合失調症では、水平方向と垂直方向との矛盾が問題となる。この二つが弁証法的(矛盾的自己同一)に統合されないことで統合失調となるのだ。
ヘーゲルと狂気の克服
デカルトが狂気に御札を貼り付けて自他の分離を辛うじて達成し、カントが悟性と統覚によって狂気に結界を張って近代主体(主語としての私)の完成に迫ったのだった。
さてカントの後、ヘーゲルによって近代主体が完成されることになる。さっそくその歩みを確認してゆこう。
ヘーゲルは狂気を弁証法によって克服。つまり自己性を否定する他者性や、自己を否定する他者にこそ自己の真理があると考えるのだ。
一度排除した狂気(自己否定)を真理として再び自己化する、自己の否定を介した自己肯定という弁証法をなすのがヘーゲルだ。
排除した狂気がアンチノミーとして理性の内に回帰するが、その狂気に真理を見て自我に再統合するのがヘーゲルといってもいい。
つまり自己を否定する敵が現れたとする、しかしこのとき自己存在は敵との関係性によってこそ定義されうる。
敵とは相手への主観的認識であり自他を峻別する境界に過ぎない。そしてこの境界によってこそ自己存在を定義しうる。であれば境界(関係)こそが自己の中心であるわけで、敵を自己(関係、概念)として見抜くことで自己は敵を統合して運動できるというわけだ。
カントが抑圧した狂気である断絶性や自己否定性にこそ自己の真理をみることで、精神分析が症状を解釈して症状を解消してゆく運動のように、狂気(自己否定)を統合して自己を肯定するに至る、というのがヘーゲルのモデルとなる。
ヘーゲルはこのような分離と統合の運動の果てに歴史の完成を見出したのだったが、いうまでもなくスタティックな意味での歴史の完成など原理的にありえない。
そんなわけでラカン派のジジェクはヘーゲルの弁証法から歴史の完成を消し去り終わりなきプロセスとして読み替えることでヘーゲルを肯定していたりもする。
※ヘーゲル弁証法は運動のことだから個人的にはヘーゲルが本当に一概にスタティックな歴史の完成を唱えていたのかは疑問がある
またジジェクはミレールの全体と無の議論を参照し、理性の裂け目としての空(狂気)を中心に終わりなき弁証法のプロセスを考えた。
※全体と無とは、全てを全てとして対象化すると必ず全てとその外部の無とに分裂して無が全体の外部に生じる、この無を全てに入れるとまた無が生じる。ここでの無が無意識の主体に対応し、この運動には理論的には終わりがない
そんなヘーゲルにとって狂気は完全に克服可能であり、会えない日々が愛を強くする、というでも言うかのように狂気(会えない日々)を新たな正常に至る過程に貶めてしまう。
狂気はその克服のためのダシにされてしまうのだ。
そんなわけでヘーゲルの芸術論は表象可能なもの、解釈可能なものしか問われない。これによってヘーゲルの芸術論では芸術の終焉が宣言される。
本書ではヘーゲル芸術論についてあまり説明がないので僕なりの想像と解釈で解説する。
ヘーゲルは芸術を象徴的芸術、古典的芸術、ロマン的芸術の三段階に分ける。象徴的芸術では力などの理念が適切な形をとれずライオンなどに象徴される。
古典的芸術にいたって人間にそれが表象され、ロマン的芸術では理念の精神の有様が表現される。
つまり理念が絵画などのイメージによって表象されえた段階を人類は終え、そのことで芸術は終演を迎えると考えたのだろう。しかしヘーゲルの宣言に反して現代も芸術は残り複雑化している。
※ヘーゲルの弁証法では闇夜の世界というアニミズム的なバラバラの表象中心主義が弁証法的な発展によってカントの統覚的なコギト(自己意識)を形成し、さらにそのことで回帰する狂気を止揚してゆき、認識装置の弁証法的ダイナミズムが取り出される
じじつ芸術は表象可能なものだけをテーゼにしているわけではない。理性の裂け目である表象不可能なものとの関係を描くものも多い。
ヘーゲルの哲学には表象可能であることにおける表象不可能なものへの着眼が欠けているのだ。あらゆる狂気を克服可能とする近代への肯定性のために見逃されたものもあるといえるかもしれない。
まとめよう。
ダイモーンと呼ばれた狂気はキリスト教によって悪霊にされ、デカルトはその悪霊(狂気)に取り憑かれることで辛うじて自他の分離と自己の同一性を主張するコギトを提唱した。
狂気にコギトの御札を貼ったのである。
次にカントは統覚によって悪霊に結界を張る。
最後にヘーゲルは結界から漏れ出す狂気を弁証法によって克服する。
こうして綺麗さっぱり克服された狂気は、ヘーゲルらによって排除されたことで逆説的にも理性へと回帰することとなる。
その存在がヘーゲルの友人であり詩人のヘルダーリンだ。
ヘルダーリンは人類最古の統合失調症であり、狂気を排除、克服したことによって、古代のダイモーンが回帰して可能となる狂気だ。
そのためヘルダーリン以前に統合失調症は存在しない。そもそもアンチノミー的な構造が言語空間に存在しないので統合失調症になりたくてもなれないというべきなのだ。
あるいは神が生きているうちはアンチノミーの裂け目は神によって守られているので統合失調症が生じないとも言える。
さて、ヘルダーリンは統合失調であり狂気に取り憑かれてゆく。彼はヘーゲルが全てを表象可能性に還元する仕事を達成する傍らで皮肉にもヘーゲルが見逃した表象不可能なものを中心とした芸術を生み出していた。
かつてダイモーンの時代では神々の声は天から具体的な真理を聴かせてくれた。しかし神なき近代における狂気は、理性の裂け目であり言表不可能の欠如を知らせる。根源的な理性主体にあいた裂け目を真理として知らせるのだ。
かくして近代以後の芸術はとりわけ表象不可能で理性にぽっかりと空いた穴が主題化されることになる。理論的にも自己の理性にあいたアンチノミーの穴は神がいた場所であり、不在の神の座に他ならないだろう。
このような穴を巡る否定神学的な芸術観が近現代における病碩学のプラトン主義であり統合失調症中心主義の本体なのだ!
※統合失調症は自己関係におけるヘーゲル的な弁証法構造の否定としても理解できる
ハイデガーと否定神学
ヘルダーリンの詩をベースに哲学を考えた人にハイデガーがいる。
ヘルダーリンは神の不在を自らの作品のテーマとし、神の不在の痕跡に留まり痕跡を名付ける詩人だ。このような世界構造の根拠をなす神などの単一の絶対者が不在となり、その不在をして未来の神の到来を予感したり、世界の構造を安定化することを否定神学と呼ぶ。
否定神学には神は人知を超えているから人の知に対する欠如としてある、というようなニュアンスがある。
ヘルダーリンの作品における否定神学構造はハイデガーに重視され、ハイデガー存在論はケーレ以後、とりわけ否定神学構造を重視することになる。
※ケーレとは存在と意味の現象学的問いから存在と真理の問いへの形而上学化を示す
ハイデガーの否定神学を示すものにゴッホの『古靴』という百姓の靴の絵を評論した有名な文がある。
ハイデガーはゴッホの靴の絵では隠された靴の存在が露わとなり、靴の既存の秩序が刷新されたという。このような靴に対する意味を捉える視点の移動=逸脱にこそ真理があり、その真理を暴くものこそが芸術だという。
ちなみにハイデガーは芸術を、外界の模倣→対象のイメージ→神による存在者(道具的対象)の描画→神なき存在者の描画、の4段階に分け最後の段階の芸術を論じている。
そのため神なき時代の西洋社会の危機に対して、神なき真理のあり方と芸術の意義を論じているふしがある。
さて、ハイデガーのロジックの要諦をまとめよう。
まずハイデガーはヘルダーリンの作品分析を中心に神亡き時代の創造と真理を考える。
そこでは移動=逸脱が重視される、視点の移動によって、既存の概念体系を刷新する隠された存在(欠如した意味)を露呈させるが創造だという。
このような移動による創造は否定神学の構造を持つとされる。そしてヘルダーリンやニーチェなどの統合失調症の狂気によって移動と逸脱がなされると考える。
既存の真理は知と外界(客観的事実、物自体)との一致とされ、写真のように正確に外的世界が描写されるような事態を示していたが、神亡き時代のハイデガーにおいて真理とは隠された存在を露呈し刷新することとされた。
しかしハイデガーはヤスパースやヘルダーリンにはあった欠如の周囲の痕跡にとどまって不在を語るという倫理を逸脱して穴に入り込みそれを塞いでしまった。
それゆえナチスを正当化する発言をしたり、大学ではゲルマン民族主義を称揚してしまう。
このような神の不在によって生じた空隙に耐えられず民族主義的運命によって性急に穴を埋め立てる姿勢がハイデガーをナチズムに向かわせたと考えられる。
ラカンと否定神学
ダリとラカン
ハイデガーの否定神学的哲学を参照したラカンは、否定神学を構造主義によって構造化し自らの精神分析理論に組み込んだ。
※フランス現代思想では否定神学の構造がしばしば見られる
またラカンはシュールレアリズムと関係が深く、ダリの芸術を語るうえでも欠かせない。
ダリはパラノイアクリティックという技法を自らの作品の賭金とした。
ダリの絵には溶けたような時計が木の枝にぶら下がったようなものがあるが、これはパラノイアの妄想構造をトレースしている。
パラノイアの関係妄想などは、新聞の記事を読んで、その内容を正確に把握しているにも関わらず、その文言から、奇妙な別の解釈を妄想的に生じることがある。自分と無関係の記事なのに自分と関係づけて妄想的な予感を読み解くのだ。
ここには一般的な意味と妄想的な意味(欠如した意味)の二層の構造があり、両者はまるで繋がらない。
このようなパラノイアの構造をトレースすると時計に対して、時計とは無関係なまったく異なる意味表徴(タオルなど)が妄想され、木に布きれのようにぶら下がる時計が描かれる。
ここで重要なのは、パラノイアの妄想は知覚の一次障害ということ。
つまり正常に対象や文章が知覚されて、その後にその知覚内容について妄想的な意味が解釈されているのではく、対象の知覚が立ち上がるのと同時に妄想が生じているということ。
これは人間が対象を欲望に相関して対象化することを考えると分かりやすい。カオスな感覚与件に触発されて欲望が生じて対象を結像するのだが、このとき欲望が日常的な対象概念への限定から逃げてしまうことで欲望が言語外の妄想的意味概念を形成するのがパラノイアの基本となる。
つまり自己主体を言語的世界に留めることができず自己主体が言語外に弾かれてしまう。しかし主体は自らを言語的に主体化することを目指すので妄想的な言語世界が構成されるという感じである。
細かく説明は尺の都合で無理なのでこの簡易的な説明で納得して欲しい。
ここで重要なのは、ダリの絵は時計によって象徴的にタオルを示しているのではないということ。
ある表象を使って真の表象を示す象徴ではないのだ。このような置き換えによる象徴表現は精神病ではなく神経症に属する。
たとえば仮面によって虚構を示したり、蛇によってファルスを象徴させたりというのは神経症的であり、パラノイアクリティックではない。
そうではなくパラノイアでは象徴において機能している置き換え(隠喩)の停止が問題となる。だから妄想には決定的な意味の欠如がある。何か分からないがとんでもないことを予告しているというような感じになりやすい。
もっともこれは初期の妄想においてであって、そのうちに具体的な意味付けが生じることになる。具体的に意味づけられた妄想を妄想性隠喩と呼ぶ。隠喩(置き換え)とは自己の主体を言葉に置き換えること。妄想によって自己主体を言語に置き換えるから妄想性隠喩と呼ぶ。
※転移も根源的な隠喩である、隠喩とは言語にたよる自己同一性の実現とそれにともなう時間の構造化に他ならない
というわけでダリの絵にこれは何を意味(象徴)しているのか?と問うのは無効で、そのような問いは作品に神経症を前提しているに過ぎない。
※古代の象徴表現については神経症(父性)隠喩でなく妄想性隠喩に近い
ラカンの父の名
さて、ここではラカンの精神病理論がハイデガーやヘルダーリンの否定神学をいかに構造論化したかを簡単に示そう。
ヘルダーリンはシラーという一なる父の登場によって発病する。
統合失調症は、神の不在を基礎づける父の名の排除によって構造化され、父の名の排除が露呈することで発病するのだ。
このとき父の名のなさを露呈する契機を一なる父と呼ぶ。
一なる父とは対になる父を持たないことを示し無対を意味する。ここにいう父とは自らの言葉で自らを語る父のこと。
人は自らの言葉で自らを語る場面において父の名を参照することになる。たとえば結婚するとき、社会人になるとき、子どもの父になるとき、人は自らの言葉で自己を言語に基礎づけねばならない。
子どもが生まれれば子の父として振る舞わねばならず、父としての主体を要請されるということ。
このような語りの出立において父の名のなさが露呈して発病するわけだ。
言語の意味(原因)というのは意味(原因)の意味(原因)というふうに無限に遡及できるが根源的な意味には決して到達しない。だから言語体系にはそれを基礎づける根拠が欠如している。
この単一の欠如を言語的に基礎づけるのが父の名のシニフィアンと呼ばれる。
言語は根源的意味が欠如するが、このことで主体は言葉を語るときに、自らその欠如した意味を考えるという仕方で、主体的に言語を語れるようになり、主体を言語の世界に定着させることができる。しかし欠如が父の名によって安定化されない場合、言語の欠如が露呈して意味世界が崩壊し、父の名によって体系的に連絡していたシニフィアンがバラバラとなって穴に落ちてしまう。
このバラバラとなり言語外の穴、神の不在の穴に落ちて意味喪失した言語外の言葉が精神病の幻聴を形成する。
父の名は幼少期に父的な存在によって、子どもを呑み込む母を去勢して子どもに承認を与える父であり、このような父が欠如していると後に父の名を要請される段階で精神病を発病するという。
よって精神病には転移がない。本来であればシラーのような父的な人に出会っても幼少期の父との関係をシラーとの関係に重ねる父性転移によって乗り切れるが、そのような父の体系を欠いていたヘルダーリンはシラーに転移する父を持っていないから転移が形成されない。
このように対となる父の不在によって父の名の不在が露わになるから、ヘルダーリンにとってのシラーのような父を一なる父、無対と呼ぶのだ。
本気で解説すると長くなるからこれで納得してもらいたい。ちなみに本書でもこの辺の理論的説明は少ない。
※転移のなさは隠喩のなさと同じ
ともかくラカンの精神病論では言語世界を秩序化する単一の欠如としての父の名が提唱される。先ほど確認したハイデガーやヘルダーリンの神の不在の議論とそっくりなのが分かると思う。
ラカンの弟子のラプランシュはラカンの理論とヘルダーリンの詩の否定神学が同じ事を指摘し、ヘルダーリンの芸術における彼が精神病であったから芸術をなしたのか、精神病であったにもかかわず芸術をなしたのか、とのヤスパースの問いは無効であるという。
つまりヘルダーリンの作品は神の不在という否定神学構造によって生じており、当の精神病であるヘルダーリン自身が父の名の不在という否定神学構造にあるわけだから、作品と狂気は相同的関係にあるというわけだ。
このラプランシュの考えを評価したのがフーコーになる。
フーコーの芸術論
フーコーは作品と狂気とは同じもの(否定神学構造)によってこそ問いうるという。
同じものを取り出すことで、作品と狂気という問題系を等根源的に扱えるというわけだ。
またこのうような否定神学的な形而上学的深淵のアートは、近代において可能となるという。
かつてギリシャの時代では神の声は直接に意味を伝え、狂気は天の神とダイモーンで繋がっていた。
しかしフランス革命や啓蒙思想によって神は死に、世界の根拠と真理は底抜けすることになる。もはや声は精神自動症のように、具体的な意味を喪失したバラバラの無意味のシニフィアンが到来するばかり。
かくして近代は神の不在を告げ、自己の根拠のなさ、深淵の穴を暴露する。このようなアートがヘルダーリンの詩に代表される近代アート論の基本となる。
さらにフーコーは近代の文学を外の発見に見出す。一般に近代文学とは他者と切り離された内面が発見されたことに特徴されるのでフーコーの文学論は独創的だ。
外とは父の名のことで言語の外、言表不能、表象不能なものとの関係を示す。
またかつて外は神学の伝統における否定神学にあり、否定神学が外となって生じたのが近代だという。
さらにブランショはこの外を無人称性の場とすることで狂気を特異的=単独的なものとする。
たとえばヘルダーリンは後に詩の著名にスカルダネリという名を使うが、これは現実の自己身体(ノエマ)の歴史的連続性から切断されたまったき現在性において未来を打ち立てる名であり、つど現在において単独的な自己と未来を生きる真の名だという。
このような欠如の痕跡にあてがわれる名は無人称性に関わる。
※名(対象)である限り二人称的あるいは一人称的な気もするが無人称らしい
まとめよう。
つまりヘーゲルによって完成した狂気の克服と近代主体の完成によって生み出された表象不能なものはヘルダーリンとして主体の構造に回帰することになる。
そしてハイデガーは自らのケーレ以後の哲学をヘルダーリンの詩の否定神学によって構築してゆく。
さらにヤスパース、ラカン、ラプランシュ、フーコー、ブランショらが統合失調症の型として否定神学構造を定式化し、これをラカンは父の名の欠如と呼ぶ。
かくして狂気と芸術は外在的な因果関係という隘路を突破しフーコーで言う同じもの(否定神学構造)によって構造に対して両者を内在的(等根源的)に捉えることが可能となる。
されにブランシュにより言表不能の外は、個別的ではなく無人称的な特異性、単独性として論じられるにいたる。
かくして20世紀の西洋哲学は否定神学構造を中心化し、統合失調症を真理のモデルとして確立されるに至る。
デリダによるフーコー批判
さて、このような否定神学モデルによる創造の統合失調症主義を批判した人物にデリダがいる。
デリダは狂気にも関わらず創造をなした、とする狂気から切り離して創造を健康に還元する発想と、狂気によって創造をなしたとする、狂気を創造の原因として外在的に論じたり、作品を症状に還元する見方を鋭く批判する。
さらにフーコーのような同じもの(否定神学構造)を取り出して、その定まった型に創造を嵌入するパラダイムも批判する。
つまりひとたび統合失調症主義によって創造を論じ出すと、どのような人の作品も作者がスキゾイドや統合失調症であるとなれば、父の名の要請によってその欠如が露呈して訪れる一回きりの神秘体験とその体験における欠如の痕跡にとどまる態度として画一的にしか作品が解釈されなくなり著者もただの無個性な範例に過ぎなくなるという。
たしかにブランショは特異的だといったが、それでも否定神学構造に依拠して論じる限り結局のところただ特異的といってるだけで、実際にはお決まりのパターンを押しつけて作品や著者の特異性を去勢してしまうというわだ。
芸術家のアルトーは統合失調症でありラカンを批判したことで知られるが、デリダによるとアルトーは身体のなかで器官が暴れるという。
つまり器官が統合されて一個の身体イメージとして全体性をもった自己イメージが形成されるが、そのような全体的な身体には一つの欠如があり、アルトーはそのような身体の欠如を嫌って欠如なき身体を目指している。
アルトーのラカンら精神医学への反精神医学的批判は、そのよう欠如の回避に対して一つの欠如をおしつける初期ラカン(プラトン主義)への抵抗だという。
ドゥルーズの創造論
深層と表面、アルトーとキャロル
デリダによる統合失調症中心主義(否定神学構造)への批判を経たわけだが、では創造と狂気はどのように論じられるか。この問いを考えたのがドゥルーズだ。
ドゥルーズは統合失調症主義、悲観主義の芸術のパラダイムを否定し異なる論理を提出する。
さて、統合失調症主義はヤスパースの過程にはじまる。
過程とは父の名の不在が露呈したことで言語の連関構造や連続性が解体して、自己の時間的な因果的連続性が断絶する一回切りの神秘体験を経て、その神秘的な啓示のもとに人によっては欠如としての真理をつづる芸術をなし、そのあとは人格が崩壊して廃人に至ることを指す。
※過程とは非連続、断絶、悪霊の闖入のこと
これに対してドゥルーズは過程を一回切りとは考えない。むしろ断絶の体験が精神医学的な統合失調症の隔離によって壁にぶち当たり、そのことで破滅が生じると考える。
そして最初の断絶の経験のあとにも、つど断絶があって変化することにこそ着目する。
いわば歴史的身体における過去を引き受けず、つど自己の歴史性と過去との束縛から逃走するあり方に新しい芸術と人間のあり方を見出す。
このようなあり方を逃走線と呼ぶ。逃走線は一回こっきりの単一の欠如への固執ではなく、そこからのつどの逃走が重要となる。
僕の理解だと、おそらくドゥルーズにおいて時間の連続性(アイデンティティ)とは、つど現在の偶発性という裂け目に晒されているのだと思う。
単一の欠如、つまり時間の連続性を根拠づける時間の始点(根源的原因)の欠如を想定するのが否定神学構造だとすれば、ドゥルーズの逃走線は時間の現在性がもつ非連続にあり、そのつど連続性には偶発性(確率現象)という欠如(非連続)が潜在するということだろう。
余談だが逃避線の考えは否定神学的な生か死か支配か隷属かの対立を偶然か必然かの対立に移行して偶然性を賛美する議論であって、カントが主客の一致を感性と悟性にすり替えたのと同型の問題があると思う。
ただしくは人は逃避線のような無限の裂け目としての偶然性を引き受けて必然となすのであり両者は対立しつつ結合する関係にあるだろう。
※否定神学構造は否定される対象ではなく、その否定を介して肯定される対象であり、そのことをドゥルーズらポストモダニストは理解していないと思う
ドゥルーズの芸術論を具体的に観てゆこう。
ハイデガーがヘルダーリンをその哲学の基礎としたように、ドゥルーズはアルトーとルイスキャロルをその思想の基礎とした。
アルトーは統合失調症であり、ヤスパースでいう形而上学的深淵にもぐってゆくタイプだからこれを深層のアートとドゥルーズは呼ぶ。
対する不思議の国のアリスで知られるルイスキャロルは病碩学ではアスペルガーであり、そのアートは表面だという。
表面とは言語的な意味だけの世界をいう。否定神学モデルが外の思考にあり言語的意味の外にある無意味の穴をめがける運動だったことを思い出そう。
自閉症スペクトラム型の表面のアートはこれと対蹠的で、言語内でありその表層にのみ留まり垂直的な深度を持たず、言語的意味において自己完結する。
本書に書かれているわけではないが、僕の理解によるとたとえばゴジラー1.0やオールウェイズを手がけた山崎監督は典型的な表面の映画監督と思う。
これについては当ブログのシンゴジラの記事で解説しているので興味ある人はその記事を参照して欲しい。
※ゴジラの記事は僕が表面のアートという概念を知る前に書いた記事だが、ドゥルーズの表面論と似たような記述になっているのが分かる
ともかく表層とは既知の意味だけの世界であり言語外を持っていない。そのため抑圧もないし他者もいない。
たとえばルイスキャロルはカバン語と呼ばれる機械的に単語の文字を組み替えて新しい言葉を創っていたが、これは統合失調症の新作言語(コードの幻聴)とは違う。
ドゥルーズはアルトーの深層の芸術について、キャロルの全てをもってしてもアルトーの一頁にも及ばないといい、その深さを高く評価している。
しかし、キャロルの表面についても、表面には意味の全てがあるというようなことを言っており高い評価を与える。
草間彌生と横尾忠則
ここでは具体的に深層のアートと逃走線のアートを確認しよう。
深層のアートはあの水玉の草間彌生が典型だ。草間は統合失調症であり、その症状がアートになっている節がある。とても否定神学的なアート。
草間の代表作のソフト・スカルプチュアは、彼女に去勢を迫るシニフィアンである男性器がむき出しで表現される。ダリのくだりで解説したように統合失調症では象徴的な隠喩を形成しないから、去勢の脅威が何か別の物に置き換えられることなくそのまま提出される。
たとえば一般の絵画であれば去勢の脅威としての男根は、傘とかに置き換えれ、傘の意味をたどることで男根のメタファーして理解されて精神分析的な読みが成り立つ。しかし草間は去勢の脅威である根源的トラウマのシニフィアン(表象)がむきだしで示される。
生か死かとの言語の主体をたちあげるさいの切実な葛藤が、何かに置換されることなくそのまま回帰してしまう。パラノイアクリティックは作品そのものが既に解釈されたものであり、背後に隠された意味がないように、草間のソフトスカルプチュアもまたそれ自体で完結しており象徴性はないのだ。
彼女は男根を複製し大量にぶちまけ、その男根の山に自らが横たわることで作品を完成させる。
去勢であり死の不安をなす男根を大量に複製し反復することでなんとか死から防衛しようというのっぴきならない葛藤が出ており、作品は草間の生の格闘そのものを成している。
矛盾(第三アンチノミー)なき一人の自己を立ち上げ、その身に起きた去勢の脅威の到来に切実に向き合い、死に対峙するあり方は作品に本人が責任をもって一つの欠如と向き合う姿といえる。
たいする横尾忠則の作品への態度は真逆だ。
彼は作品に責任と持たないという、責任はイメージであり作品の側にあって自らは感知しない。
彼は湧き上がるイメージを模写しそこに遊び心を加えて作品をつくってゆく。
一つのヴィジョンに固執して責任をとり一貫した自己を析出することに固執する草間とは逆に、そうした責任から逃げてゆく。一貫性のある一人の自己を放棄して、解離や多重人格にあるようなその場その場でのつどの不都合や葛藤を場当たり的に処理するあり方に近い。
こうして責任をとらずに逃げてゆく態度のために横尾の精神には病理的なところがない。いわば健康に属するアートといえる。
統合失調症主義のアートが一回の神秘体験と引き換えに真理に到達して人格の破綻に至るという悲観主義のパラダイムにあったのとはまったく異なる。
また横尾のアートは男と女、生と死などの対立の反転を特徴とするという。これは、そのつど柔軟に逃避するあり方と見ることができるかもしれないし、ヘーゲル的な狂気の克服における弁証法ととれるかもしれない。
いずれにせよ、生と死の断絶のなか主体の服従か支配の断絶した二項対立を苦しむ草間とはまるで違うのがよく分かるだろう。草間にとっては生きているのか死んでいるのかはどちらかしかなく男も女もどちらかしかない。
そんな二人は対談したことがあるのだが、横尾が自らのイメージを能動的かつ言語意味的に語るので草間は憤慨して対談をうちきろうとしたことがある。自らのアートの体験を既知の言葉によって置き換えられてしまうことへの怒りがあったのかもしれない。
ともかく怒った草間は、脈絡なく過去に自分がニューヨーク?だったかでなした業績を語り、ウォーホールとかにも影響したとかみんなソフトスカルプチュアを真似たとか言い出したらしい。
つまるところ自己の確立が横尾の言葉で危ぶまれたから、自己主体の誕生の契機となった過去の話をして防衛せざるえなくなったのだろう。
※ちなみに僕は芸術のセンスがないらしく草間彌生の作品はただの水玉模様にしか見えない。そもそもバンクシーとか一部の例外を除き僕はモダンアートは一切認めない派
ドゥルーズの表層への移行
さて、ドゥルーズは『意味の論理学』においてアルトーとキャロルを論じ二つを深層と表面に対応させたわけだが後の『批評と臨床』では表面のキャロルにこそあるべき創造を託すようになる。
これによりヘルダーリン的な垂直軸にあるプラトン主義、統合失調症主義を顛倒し、表面の狂気論を打ち立てる。
改めて表面の創造を確認しよう。
表面とはビリヤードにおけるショットや勝敗といった言語化された意味を示す。
これはラカンの象徴界に対応し言語的意味の世界といえる。対するビリヤードの盤での現実的な物質の玉の物理運動を深層と呼ぶ。深層は現実界に属する。
現実の物理的な物質の運動があってそれに対してルールを構築して勝敗といった意味を構成するわけだから深層と表面の主従関係は明白に思われる。
しかしドゥルーズは両者を切り離し、現実なしの表面を主張する。つまり頭のなかでビリヤードのゲーム進行を想像したり、プログラミングでビリヤードゲームをプログラムできるように深層から自律した表層が可能であるという。
この切断はアルトーとキャロル、統合失調症と自閉症の切断にも対応する。
※周知の通り自閉症は最初、統合失調症とされたが現代では統合失調症から切り離されている
キャロルのアートは現実なしの、深層なき表面のアートといえる。
不思議の国のアリスでは確かにアリスは深淵の穴に入ってゆく。しかし深層の世界をキャロルは表層化し水平に横滑りして回避し、そこから逃避してゆく。
たとえば不思議の国に登場するトランプの兵隊は現実的な物質的厚みのないトランプ=数字であって表面的である。
このような表面化によって深淵に落ち込むことなくそこから逃避する健康的な逃避線のあり方が表面のアートの特徴となる。
そんな表面のアートは発達障害に関連する。
自閉症スペクトラム(発達障害)とは〈他者〉と対象aのなさとして規定される。
※〈他者〉は言語の主体であり大文字の他者、対象aはここでは〈他者〉の欠如を埋める〈他者〉の欲望の対象のこと
※自閉症は縁の上の対象aの回帰として自分の声を自分の耳の縁に向けて回帰させ自閉的に対象aをループさせるモデルでも説明されることがある
対象aとは具体的には眼差し、声を示す。まなざしは欲望の視線であり〈他者〉の主体性(欲望)において対象化されるところのまなざされる対象を示す。
だから視線の先にあるものが対象aとなり、まなざしもまた対象aとなる。このまなざしの主体を〈他者〉と呼ぶ。子どもをまなざす母などは〈他者〉の典型だ。そして言語の主体であり言語の体系もまた〈他者〉と呼ぶ。
言語とは三人称性によって意の伝達を実現するわけだが、三人称的な彼の視点とは私に対して〈他者〉であるということ。第三者としての他者の構成と自己化なしに言語はありえないといってもいい。
〈他者〉の声やまなざしといった対象aの断絶と他性の闖入を排除することで自閉症は母国語(母の言葉)への参入を拒絶し自己性に閉じこもるのだ。
※ハイデガー的に説明すると存在が何らの他性も持たないような存在構造を持つのが自閉症スペクトラムで存在に他性がないからこそ言語への疎外=参入が生じない
たとえば窃視症や週刊誌のカメラマンは相手を対象aとして覗くが、覗いているところを覗かれたり話しかけられると途端に狼狽する。これは眼差しや声によってカメラマンが対象aにされてしまい他者が闖入してくるため。
つまり子どもは母=〈他者〉の眼差しによって対象aが闖入し、対象aとしての自己存在を母の言葉(母国母の欠如)に探さねばならなくなり母国語の世界へと疎外されて言語をマスターする。
しかし表面の自閉症では対象aも〈他者〉もないのでどこまでもトートロジー的に、ないしは論理学的に言語内部で自己完結する欠如なきオルタナティブな国語(合成他者)を生成しこれによってディスコミュニケートしてゆく。
そのため自閉症スペクトラムでは、言葉に文脈がなく字義的で辞書的な解釈をしてディスコミュったり、言語の法についてルールはルールですからという自己完結的ロジックで杓子定規にルールを守ったりする。
文脈は行間にあたるもので行と行の間の空であり言葉の欠如、言語外に属するが、発達障害ではこの欠如がないので言語に文脈が存在せず字義的に理解されてしまうわけだ。
※日本人は昔からルールはルールですからが多く、もともと発達障害的な民族性が強い、また最新の臨床研究によると、日本人の過半数が非定型発達化しており後天的に発達障害に近い主体水準に至っているという
この本の結論をここで先んじて示すと、本書は垂直軸にある神=〈他者〉の言葉をポジ的に語るプラトン的狂気でもなくネガ的に語る否定神学的狂気でもない、ポスト統合失調症の狂気=創造として発達障害を提唱するもので、表層のアートの可能性を強く主張するものである。
さて、じつのところキャロルの不思議の国のアリスのセリフは、発達障害的な字義的な解釈によるディスコミュニケーションと意味のズレが徹底して描かれている。
そしてこのようなディスコミュニケーションによって作品をつくることでキャロルは少女たちとのコミュニケーションを逆説的に実現する。
このディスコミュによるコミュニケートが表層の可能性の一端を示す。
また前述したカバン語は表層の世界において、表層のうちに深層へと通じる可能性をもつ。
深層なき言語的意味だけ、表面だけの世界で表面の言語を機械的に組み替えることで国語の内部に意味を超えた外国語を屹立させる、ここに表面のアートの狂気があるとドゥルーズはいう。
欠如の深淵に落ちて言語外の言語である神の欠如した言葉を名付けるアルトーやヘルダーリンとことなり、表面のデータベース化した言葉をAIのように機械的に組み替えて、楽しげな言葉を創作するASDに来るべきアートのあり方をみたのがドゥルーズなのだ。
このような表面の内部によって表面の秩序を脅かすカバン語やコラージュ、生成AI型のアートは、その偶発性によって深淵な言葉を投影する可能性があるとドゥルーズはいう。つまりプラトン主義的な父とつながる正嫡的な狂気を否定し、天にも深淵にも通じない非嫡出的な表層の狂気を称揚することで、プラトン主義や否定神学といった正嫡主義を否定するところにドゥルーズの狙いがある。
※表層アート論は健康という意味では意義もあろうが他者なき世界の危険性についてあまりに無批判すぎると思う
また本書によると東浩紀の理論では萌え文化はデータベース化しており萌え要素の順列組み合わせ=表面だけでできているという。さらにネットには誰かが掲載しようとしたことしかアップされないから表層しかないという。そんなネットでは新しい検索ワードを見つけるのが重要だという。
※僕が思うにネットにもネットの都市伝説があり、欠如は事実ある。都市伝説は欠如に対する意味妄想だから垂直性を含みうる、垂直軸はそんなにいきなり消滅したりしない
深層につながる表層の論理
ドゥルーズは表層が深層に関わりうることを提示した。
それはいかにしてか。これを探るため芸術家のルーセルを確認しよう。
ルーセルは19歳のときに体験した栄光の感覚なるものに心酔し、生涯その一度きりの喪われた感覚を目指して文学を創造した。
彼は栄光の感覚という一度きりの青年期の体験とそれによる異常のために病碩学では統合失調症とさてきた。
しかし、彼の暮らしや性格、文学を分析すると明白に統合失調症でなく自閉症スペクトラムだと分かる。
彼は表層のアートをなし言語の内部で言語の組み替えを行っていたのだ。
そんな彼の栄光の感覚は、しかし不可能なものであり言表不能なものであったと考えられる。つまりルーセルからは深層の表現や否定神学に頼らない不可能なものへの接近が取り出せるのだ。
そんな表面のアートはいかに深層へと接続可能か、その答えはウルフソンという別の表面の執筆家にある。
ウルフソンは当時、統合失調症とされたが現代の視点ではASD(広汎性発達障害)だという。
そんなウルフソンにも言語外の不可能なものの体験があり、それを真理の中の真理の啓示を得たと彼はいう。
アルトーとキャロルは深層と表面に分離されたがルーセルやウルフソンは表面に留まりながら栄光の感覚や啓示をえる深層の世界に到達。
そんなウルフソンは〈他者=母〉の言葉、母国語を嫌い、母の話し声に嫌悪する。
表面にとどまって〈他者〉なしに不可能なものに関わるのがウルフソン。彼は言語外へと超えでて穴に落ちることもあるアルトーのような否定神学型の詩人と異なり、言語の内側で〈他者〉=母国語との関係を構築するという。ここでは此岸の健康にとどまって彼岸の不可能なものに触れたかもしれないという可能性が見出されている。
後にウルフソンはタッチパネル式の表面の賭け事(偶然性)にはまり、大もうけするが投資でポカって破産したという。
※このような賭博癖は統合失調症ではありえない、賭博はドストエフスキーやスサノオのような癲癇性格者によくある
最後に論旨をまとめよう。
神経症は深淵たる不可能なもの、フーコーのいう外について、これを隠喩によって異なる表象に置き換えることで関わる。神経症のアートでは象徴的な読みが重要。
統合失調症では不可能なものを示す神の不在の座である穴に落ちることでそれと関わる。統合失調症のアートでは象徴解釈は成立しない。
自閉症スペクトラム(発達障害)では、表面に留まりつづけ偶発的な言葉遊びのなかでギャンブル的にそれと関わる。表面のアートにも象徴解釈は成立せず、通常は字義的な意味しかないが、偶発的に深淵が開示されうる。
現代の創造は自閉症化しているという。
ドゥルーズは母や父と繋がらない表面の言葉の偶発的な攪乱に来たるべきアートを見出したのだ。
終わりに
なんとか15000字におさめたかったが2万を超えてしまった。後半はまとめるのにかなり手間取ったので迷ったが投稿することにした。
この本、ヘーゲルまでの内容は哲学をほとんど知らない僕でも、簡単に理屈を推理できて筋もシンプルで記憶に入りやすいが、ハイデガーやラカン、フーコー、ドゥルーズあたりの記述は、どういうわけか筋を記憶しにくいところがあって少し難解に感じなくもない。
とくにドゥルーズの表面が深層に確率によって繋がりうるという話は微妙にレトリカルでいまいちしっくりこない。疎外を否定しても文明が滅びるだけとしか思えない。本の記事はいつもはほぼ完全に記憶任せで一気に書き上げるのだが、今回はドゥルーズあたりの記述は、がっつり本を見返しながら要約をかくはめになった。
そのくらいピンとこない。栄光の感覚とか真理の啓示とかいわれても他者性がないなら意味が無いと思う。そもそも自閉症にある私的言語S1の反復(依存症)が不可能なものなのでは?と思わなくもない。他者不在の世界を肯定しても文明が終るだけで合成他者のみの社会には破滅しかないと思う。
ただ不思議の国のアリスは面白いし表面の芸術も芸術であって一概に深層に劣るとは言えないとは思う。音楽も生成AIだろうが人がつくっていようが、曲が良ければ問題ないわけで。
あと深層のアートが消えるという話には疑問がある。新海誠は現在進行形で流行ってる深層のアートだと思う。それに人気漫画アニメのメイドインアビスも深層のアートで深淵の穴の奥深くの母の言葉が物語の主題となるプラトン主義作品。メイドインアビスについては木村敏の境界例理論がぴったりくる深層の作品。
僕は表面を特権化する態度はどうにも現実と合っていないと思う。表面主義には疎外の運命への想像的な恨みがあるのではないかとさえ思える。
全部表面になったとして、〈他者〉なしで文明がどうして可能なのか訳がわからない。動物園みたいになるのは目に見えてると思う。既に動物園の動物みたいな言説で溢れて政治も混乱してる。
この現実が眼に入っていないのだろうか。
さて、本書はまったく人文知の知識がない人でもある程度は読めるのだが、この本を読むなら深層心理学か哲学のどちらかを少しかじっていた方がいいと思う。ラカンを少し知っている人ならそれだけで十分に読める。
この本、狂気との関係から哲学の歴史をまとめてもいるので、非常に分かりやすく記憶しやすい部分が多い。
本当に面白くてオススメの本である。
二回読むことを推奨する。もともと詳しい人は別として僕のような哲学や思想はほとんど知らんという人は二回読まないと内容を頭に入れるのは困難と思う。
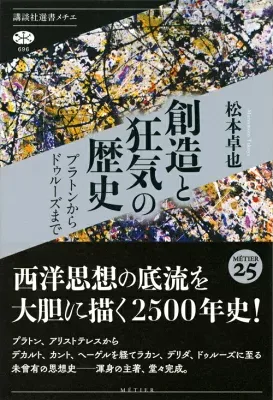


コメント