うたまるです。
こんかい紹介する本は新進気鋭の若手言論人、松本卓也著『享楽社会論ー現代ラカン派の展開』(人文書院)!
この本、4つのディスクール+資本主義のディスクールについて、ずば抜けて分かりやすく洗練された解説がしてあります。
本書は現代ラカン派における現代社会論の解説・入門書の決定版です。著者は現代思想界で今話題のあの松本氏!
そんな本書は、ラカンの思想の変遷と現代ラカニアンの思潮を概観し、読者にその見取り図を提供してくれます。そのためラカンの理論を理解する上でも本書は強力な羅針盤となるのです。
まさに深層心理学好きならば必見の書!
また本書は、ラカン好きなら聞いたことがあるだろうラカニアンレフトなるラカン派左翼がどのようなものなのかも明らかにしています。
今回はそんな享楽社会論の魅力をコンパクトに凝集し、本書の概要を紹介します。
享楽社会論とは
| 題名 | 享楽社会論ー現代ラカン派の展開 |
| 著者 | 松本卓也 |
| 出版社 | 人文書院 |
| 初版発行日 | 2018年3月10日 |
| ページ数 | 296頁(単行本) |
本書は、ラカンをある程度知っている人にとっては非常に分かりやすく、類い希なほどに優れたラカンの解説書となる。
ただし、ラカンについてまったく知らないという人がいきなり読むには、まったく向かない。なので本書は最低限度ラカンを知っている人に適した本だと言える。
ラカンの基礎を学びたい人は以下の記事を参照ください。
特質すべきは、僕がこれまで読んできたラカン関連の本の中では、突出して4つのディスクールについて詳細かつ分かりやすい丁寧な解説がしてある点。
僕はこれまで4つのディスクールをラカン関連の本で何度か学んできたが、だいたい本を読んでから一月を過ぎると細部を忘れてしまっていた。
ラカン派でない人にとっては、そのくらいディスクールの式と意味は、情報量が多いわりにピンとこなくて記憶にとどめておくのが大変なのだが、本書の圧倒的に分かりやすい解説のおかげで、今は完全に記憶に定着させることができたという手応えを感じている。
また本書の注意点として、第三部の政治に話がおよぶと、世間一般の認識と比較して若干左よりの歴史観が散見されるように感じる。そのため保守的な歴史観や政治観の方にとって第三部を読むと抵抗が生じるかもしれない。
基本構成
本書は、後期ラカン理論およびそこから発展したミレールや現代ラカン派の理論を中心に論じる。
そして三部構成からなる。
第一部では
後期ラカンの主要概念となる享楽へ着眼し、精神分析の理論を振り返る。そのため現代社会とラカンの理論を繋ぎ本書全体の軸となる基礎理論を解説・提示することが第一部の眼目となる。
第二部では
臨床における現代の状況やDSMなどの問題を中心に論じる。ここではとりわけ現代の鬱に対して現勢神経症を中心に読解する松本氏独自の視点が光り、非常に興味深く説得力のある斬新な仮説が提示される。
第三部では
現代の政治をラカン派の側面から分析している。主にレイシズム2.0へと移行した現代における全体主義の問題やイロニーの問題を論じる。また政治に関する国民のシニカルな態度を克服し民主主義において社会が刷新される経路が示される。
読解ポイント
本書の特徴は、フロイト時代VSラカン以後というパースペクティブで貫かれている点にある。
具体的に示すと、第一部から三部までの多くの議論が概ね、「〈他者〉の〈他者〉はいる」というフロイト時代を反映する初期ラカンのテーゼから「〈他者〉の〈他者〉はいない」という後期ラカンのテーゼへの変遷を軸に論じられる。
そのため本書を読むときは、2つのテーゼの違いを理解し、つねに2つのテーゼを意識して読むことで読書がはかどるだろう。
また本書では、〈父〉(ビッグブラザー)のいた時代からいない時代へという転回の軸は、ラカンの理論における男の式(強迫神経症、否定神学システム)から女の式(ヒステリー、郵便的システム)へと移行したことに対応させられる。
さらに、厳密にいえば、本書の議論では50年代ラカンをフロイト時代とし、60年代をフロイト以後の父亡き時代、70年代以降のラカンを両者の止揚として捉えてもいる。
たとえば第三部で提示される政治思想における「基礎付け主義(独断論)」「反基礎付け主義(相対主義)」「ポスト基礎付け主義」は、本書ではそれぞれ50年代、60年代、70年代ラカンと結びつけられる。
以上から本書の多くの議論は、この初期と後期の転回の軸をベースに体系的、重層的に展開されてゆくので、そのことに注意して読むとよいだろう。
| フロイト時代 | ラカン以後 |
| レイシズム1.0 | レイシズム2.0 |
| 宮廷愛 | 神の愛 |
| 男の式 | 女の式 |
| 欠如 | サントーム(S1) |
| 1つの〈父の名〉 | 複数形〈父の名〉 |
| 否定神学システム | 郵便的システム |
要約解説
ここでは僕が個人的に思う本書の見所を要約、解説する。また本書は内容が濃くボリューム多いのでこの記事で取り上げる見所はあくまでも本書の見所の一部に過ぎない。
またただの要約では、価値の低い記事になるので、この項では、ラカン理論に対する、ぼくの独自解釈や理論を適度にまぶしてある。
ともかく面白い本なので気になった方は是非、本書を手に取って読むことをオススメする。
第一部見所解説①
まず第一部では精神医学の歴史を振り返る。そこではヘーゲルやカントが参照され、精神病、ことに統合失調症の特異性と狂気がフォーカスされる。
またカントの「統覚」などを例にとりつつ、精神病的な異常を考察することが翻って正常の条件を取り出すことへ通じると示される。こうして異常が正常へと止揚可能なものとして、いわば正常の外部として捉えられてきた歴史が概観される。
次に精神分析のパラダイムが、そのような異常と正常を精神病と通常人とで二分する旧来のパラダイムと異なることが示される。
つまり精神分析では、神経症を扱うことで日常生活における言い間違いや物忘れ、失策行為に典型されるように、異常は正常性に内在する正常それ自身のうちにある裂け目(症状)として取り出される。
それ故に精神分析では異常は正常の内に消し去ることのできないものとして捉えられる。
ここに精神分析のパラダイムの革新性があるという。
第一部見所解説②
(※いかに記述される「存在者」とは物のこと、「シニフィアン」とは存在者に対応するもので、意味を示す単語(の音声面)のこと)
キルケゴールの宮廷愛と神の愛の区別についてが本書では丁寧に論じられる。
宮廷愛とは男性が身分違いの宮廷にいる高貴な女性に対し、叶わぬ恋慕の情を詩に読むこと。
したがって宮廷愛は身分による禁止によってかき立てられる理想の女性なるもの(定冠詞つきの女性)との不可能な結合の空想(幻想)を示す。
そのため宮廷愛は、ファルス関数(直接性の禁止、近親相姦の禁止)によって去勢されつくした主体(男、強迫神経症)の幻想だという。
この意味での宮廷愛を男の式という。本書では触れられていなかったと思うが、男の式とは強迫神経症に対応する。ひらたくいえば、意識における〈他者〉の存在を嫌い全体を言語的に把握し知り尽くすことを幻想する主体といえる。
つまり言語的な意味に不可知の欠如があることを認めない主体が男であり、男はその欠如を埋めようとフェティッシュな対象(対象a)として理想の女性なるものを幻想しているのである。
ようするに男の式とは、自分について自分の知らない領域があったり、自分のつどの行為のうちに意味(意図)が理解できない自己を超えた要素があることを認めたがらない主体だということ。
これは、自己存在を示す記号である最初の幸福体験S1の全てが言語的意味であるS2へと置き換えられてしまうことで起きる。
別の言い方をすると男とは、1つの例外(自己主体)のみを欠如として認めることで言語的意味世界の全体性を成立させる主体であり、これを否定神学システムという。
補足すると、言語体系(象徴界)の根拠はその外部に依存する、というのも内部にそれ自体の根拠を措定しても、根拠の根拠が必要になるため、究極的な根拠は外部に求めざる得ないからだ。
そして外部の根拠は外部であり不可知のため体系の内側では欠如として表されることになる。
この不可知の例外、1つの究極的欠如(根拠)を設置することで、言語的意味世界の全体を完全規定するモデルを男の式といい否定神学システムという。
また僕の理解では、男の式とは、いわば決定論的世界観に他ならない。ニュートン力学的な時間は一神教的であり、男の式の典型と考えられる。
(※ラカンの理論は基本的に時間の話に変換するとどれも分かりやすい)
対する神の愛というのはファルス関数(直接性の禁止によるS1のS2化)そのものを去勢することで、S1(自己存在の記号)のうちにS2(言語的意味)に置き換えられない言語的意味から切り離された部分(根源的今)を認めることにあると考えられる。
これにより彼岸に空想される完全性としての不可能な宮廷愛(性的関係のなさ)を克服し、世界と自己の固有性へと開かれるとされる。
以下は僕の個人的な注釈になる。
また、ぼくの理解では、女の式に属する神の愛やサントームとは、起源を意味(シニフィアン、存在者)より切り離し存在(根源的今)を欠如でなく有として認めることとして解釈できる。
そのため、いわば話す行為のうちに言葉の意味(自己)を超えた享楽(存在、行為)を見いだす姿勢が女の式であり宮廷愛と考えられる。これは非常に多神教的な時間意識と言わねばならない。
また僕の理解では、現代ラカン派が重視するS1(最初の幸福体験の印)は二人称的であり個物としてシニフィアンの次元にある。じじつS1をラカンはシニフィアンとしている。
しかしハイデガー存在論ではシニフィアン(存在者)に存在が先行する、そのため現象学的には、S1よりも存在(あるということ、能う)が先行していることになる。
そこで存在に相当する概念を精神分析に見いだすとすれば、欲動、欲望、イドが該当するだろう。
とくにイドはもっとも始原の存在として、存在それ自体に該当させることができると考えられる。そのため現象学的に精神分析を捉える上ではS1より古き根源、イドが重要になるだろう。
そして女の式によって精神分析を捉える上でイドの視点は欠かすことができないと考えられる。
サントームや後期ラカンについては以下の記事を参照のこと
第二部見所解説
第二部ではDSMがいかに欠如を排除するポストモダンに呑み込まれた歪んだ概念であるかが紐解かれるが、やはり一番の見所は、メランコリー論考になる。
第二部では、現代増えつつある鬱病について新型鬱病などにもふれつつ、それがクラシックな内因性鬱病=メランコリーではなくデプレッション(神経衰弱など)であることをしめす。
また本書によると昨今多い鬱はデプレッションでも現勢神経症だという。
現勢神経症とはフロイトの概念で、神経衰弱と不安神経症の2つを下位に含むカテゴリー。
そんな現勢神経症は欲動の処理不全によって生じるという。
欲動の処理不全を具体的に見てみよう。まずそれは不適切な欲動の処理であり、フロイトでいえば性欲をマスターベーションで満たすことが不適切な処理に相当する。
また、欲動の処理不全には他に禁欲があるという。
これを現代にあてはめると、僕はたちは社会的な欲望をもつわけだが、この欲望に問題があると現勢神経症として、新型鬱などになると分かる。
そのことを簡単に説明しよう。
まずラカンのいう欲望とは社会的なもので、直接性が断念され間接的に自己が追求されることをいう。
つまり子どもは母親からの承認を、近親相姦的な直接性の承認ではなく、言語的象徴を介して得ることで言葉を学習すると精神分析では考えるのだが、その言語的象徴を媒介して親から承認をえるアクチュアリティを欲望という。
欲望とはしたがって弁護士や政治家、東大生などの言語的象徴を目指して欲する動きを示す。そのため完全に欲望が満足して満たされると欲することができなくなり欲望は死んでしまう。ようするに欲しいものが全て手に入ったら、もはや何も欲しくなくなるということ。
欲望は不満足によってその対象が欠如することで生じるわけだ。
そのためラカンは満足は欲望を殺すという。
(※欲望について詳しくは、ラカンで分かる映画ハンコック)
以上の説明から、欲望は近親相姦(直接の承認)の断念、母の欠如・不在を埋める直接の対象となることの断念によって生じると分かる。そして、この断念された直接的満足を言語象徴を迂回した承認によって間接的にえるプロセスが欲望である。
したがって欲望はその間接性ゆえに、つねに絶妙に欠如し満たされることがない。
以上から現勢神経症の原因となる「欲動の処理不全」とは、欲動の求める直接的な満足が、適切に言語象徴=〈他者〉を迂回し欲望を構成することなく、マスターベーション的(自体愛的)な短絡を起こして主体に直接与えられることをいう。
ところで本書では第一部から一貫して、現代社会が直接的な満足の断念(欠如)なしに欲望が可能であるという狂ったメッセージを発しているという。
たとえば、赤ちゃんがおしゃぶりするかのごとく現代人はイヤホンを常時はめて音に満足し、好きなコンテンツをYouTubeなどで見続ける。しかもそれらは飽きるまもなく新しいコンテンツが供給され続け、結果、依存症的に消費しつづけることとなる。
かくして、現代社会では社会的欲望は限りなく直接的な欲動の満足へと短絡し、間接性(欠如)をともなわないという。
すると社会的な欲望に本来あるはずの直接性の断念という欠如が、刹那的な消費の快楽によって埋められてしまう。
そして、このような欲望を殺しにくる不適切な欲動の処理が、現勢神経症としての鬱病の増加につながっていると松本はいう。
つまり、〈他者=言語〉を迂回しない自足的、自体愛的な消費の満足はフロイトでいうマスターベーションに相当し、それによって現勢神経症が起こるわけだ。
さらに、そのつど刹那的に消費し即欲動を満たすことになれると、わずかな消費の停止期間が決定的な禁欲と化す。
かくして不適切な欲動の処理である消費と禁欲という2つの欲動の処理不全が現代人に生じ、そのことで鬱病(現勢神経症)が増えているのだ。
ちなみに精神分析では通常の神経症を転移神経症と呼ぶ。そのため現勢神経症は神経症とはいっても神経症とは異なる。
精神分析における神経症の症状とはあくまでも無意識に抑圧された内容物がメッセージとして隠喩により症状に回帰したものとされる。
よって欲動の処理が問題となり憂鬱や不安にさいなまれる現勢神経症は神経症とは異なる。
現勢神経症の議論はラカンの欲望の議論を知っている人にとっては非常に面白く説得力のある仮説であり興味深い。とくに僕のようなアニメやゲームの考察を介して現代社会分析をする人にとっては現勢神経症説は非常に説得力のある仮説といえよう。
第三部見所解説①
第三部は政治編になる。レイシズム1.0から2.0への変遷や享楽の政治など見逃せない話がトピックが多い。
※レイシズム1.0から2.0への変遷の詳細は、レイシズムについて
しかしとりわけ興味深かったのが政治思想における、基礎付け主義と反基礎付け主義とポスト基礎付け主義の議論になる。
これを満足に解説するにはフランス革命における王殺しに端を発する父権の終わりや、ラカンの有名なクッションの綴じ目、などの説明が必要で長くなるので、ここではざっくりとした解説にとどめる。
まず基礎付け主義とは、ヒトラーなどの社会秩序の根拠となるような〈父〉としてのカリスマがいた時代のあり方で、哲学で言う独断論に相当する。
つまり社会には絶対的な正しい単一の摂理があるという考え方。
この考えは50年代ラカンにおける「〈他者〉の〈他者〉はいる」(社会の根拠はある)に対応させられる。
つぎに反基礎付け主義は、ポストモダン的な相対主義に相当する。
これは60年代ラカンの「〈他者〉の〈他者〉はいない」(社会の根拠はない)に対応する。
そしてポスト基礎付け主義とは最終的な絶対的摂理はないが何らかの基礎付けは必要であるという考え方になる。
これは70年代ラカンの「〈父の名〉とはそれ(〈父の名〉)なしですませることである」に対応する。
ラカンの優れた考察に、騙されないものは迷う、という言葉もあるが70年代ラカンのポスト基礎付け主義的なロジックは、ポストモダンの相対主義のダメさをよく表していると思う。
基本的に現代の社会問題や経済問題の根幹は、相対主義と独断論との分裂に起因すると考えるのが人文知のスタンダードではなかろうか。ともすれば、70年代ラカンの思想には現代において一定の価値があるだろう。
ここではこれ以上の解説は控える、興味のある人は本書を読むことをすすめる。
第三部見所解説②
第三部でひときわインパクトがあるトピックに柄谷行人の交換様式理論とラカンのサントーム理論との興味深い考察がある。
本書によると柄谷は世界史を決定する要因として4つの交換様式ABCDをとりあげる。
Aは、贈与と返礼であり、これは氏族社会に主流だった形式だという。
Bは、搾取と再分配であり、これは国家が税金で回収して財政出動で再分配するモデル。
Cは、商品交換であり資本主義。
Dは、農耕定住社会以前の古き遊動民時代の交換様式だという。
現代の社会はB+Cでなりたち、その原型はAにあるという。
そして現代のネオリベ資本主義による格差が拡大しつづける歪んだ世界の克服として、多国籍企業への増税などにたよるやり方は、既存の交換様式Bに頼る方法でありこれでは根本的には解決しないという。
そのため柄谷はネオリベ資本主義の交換様式には存在しないDによって社会は止揚され解決に向かうという。
ここで既存の交換様式Bに依存してネオリベを克服する方法論を松本はラカンの大学のディスクールと関連付ける。
大学のディスクールとは、権威的な体制を克服するにあたり当の権威的体制のシステムに依存するモデルである。
つまり大学のディスクールでは権威が保存されたまま学生運動が起きるため、権威を克服することができないことが示される。
たとえば、大学の言語空間では、フロイトによると、とかハイデガーによると、というようにネームバリュー(権威S1)によって知が権威づけられるが、知の根拠とされる当のネームバリューについては不問にされてしまうわけだ。
このような社会的権威(S1)を保存する大学空間でおきる学生運動は本質的には権威を克服する革命を実現できず、新しい権威による支配を招聘するだけだということ。
そして、柄谷が根本的な解決として提示する交換様式Dが本書では分析家のディスクールに対応させられる。
Dとは人類史上もっとも古き交換様式でありながら、未知性をもつ新しいものだという。
このDは分析家のディスクールにおいて分析主体から切り出されるS1(言語的意味の外部にある自己の根源性)に相当するという。
S1(サントーム)とは個人における原初の満足体験の印であり、その意味でもっとも古いのだが、同時にそれは言語的な意味の外部にあり、その意味でつねに未知であり新しいものといえる。
古くて新しいDとサントームはとても似ているのだ。
また、ラカンは分析家のディスクールにおいて権威(S1)は震撼させられるとし、これを根本的な社会の解決策として提出している面がある。
以上から柄谷が提示するDとサントームには類同性らしきものを確認できる。
個人的には経済は金本位制の時代と信用創造の時代とでは、まるっきしBの意味が変わるので、柄谷の話はまったくピンとこないのだが考察としては面白いと感じる。
ここで多くのこの記事の読者がなんでネオリベの克服に課税などのB(税金と再配分、国家)で対応してはいけないのか?と疑問に感じていると思うのでその点を補足しよう。
これは僕の想像だが柄谷はおそらく、現代社会では共同体と個人との分裂が生じ、それが経済の審級においては、福祉政策=国家(B)とネオリベ=資本主義(C)の分断を引き起こし混乱が生じると考えているのだろう。
そのためBによってCを押さえつけても個人主義的な自由を求める個々人からの反発が強まり社会は激しく分断するといいたいのだと思う。
このことは前項で解説した基礎付け主義(独断論、B国家)と反基礎付け主義(相対主義、Cネオリベ)に対応しているのはいうまでもないだろう。
したがってこの分断構造の克服として措定されるDは、サントーム(S1)=ポスト基礎付け主義に対応すると松本氏は考えているのだと思う。
また、Bを福祉主義、Cを個人主義とすれば、BとCは普遍と個の対立原理として捉えられるが両者は弁証法の関係にあると考えられる。
ちなみに柄谷は既存の交換様式の外部としてのDに固執しているようだが、ヘーゲル弁証法的(ユング的)な観点からするとDを外部として措定する意味はないと考える。
余談になるが僕の理解する限りでは、現象学者の竹田青嗣は、この対立の問題を存在論的差異の混淆として捉え、現象学によって解決可能だと提唱している節がある。
僕は哲学も現象学もあまり詳しくないのだが、竹田青嗣の考えに100%同意である。
終わりに
本書は内容が濃く、この記事で紹介したのは本書の魅力の一部に過ぎない。
また本書の見所であるディスクールやマルクスの剰余価値をベースにした剰余享楽についての丁寧な説明については、今回は触れることができなかった。
というのもラカンの珍妙なディスクールの式はブログで記述するのが面倒で記事にするのが大変だからである。
言葉だけで説明しても分かりにくいので実際にディスクールの式を表示する必要があるのだが、それはブログ記事だと手間なので断念した。
本書のディスクールの解説は秀逸で、たとえば真理と生産物との間を隔てる遮蔽線を重視しその意味を分かりやすく解説しているのだが、他の本だとディスクールの遮蔽線は軽視され、ほとんど説明されないことが多い。
またフロイトが父を生かそうと必死だったことや、眼差しと恥、倒錯と対象aのミレールの分かりやすいモデルなど、この記事では紹介しきれていない精神分析好きには興味深い内容が多々ある。
他にも本書では、昇華がラカンでは対象を〈物〉へ高める、と解釈されることが解説され、芸術と昇華の関連にも言及していたりする。このように本書は非常に幅広いトピックを扱っていてかなり面白い。
とくに個人的には「対象がまなざしている」というラカンの議論は西田の「物来て我照らす」に通じるところがありとても面白かった。
というわけで今回、はじめて松本氏の本を読んだが、日本人のラカンの本なら松本卓也が一番分かりやすくて面白いと感じた。
享楽社会論はラカンについて最低限理解のある全ての人にオススメ!
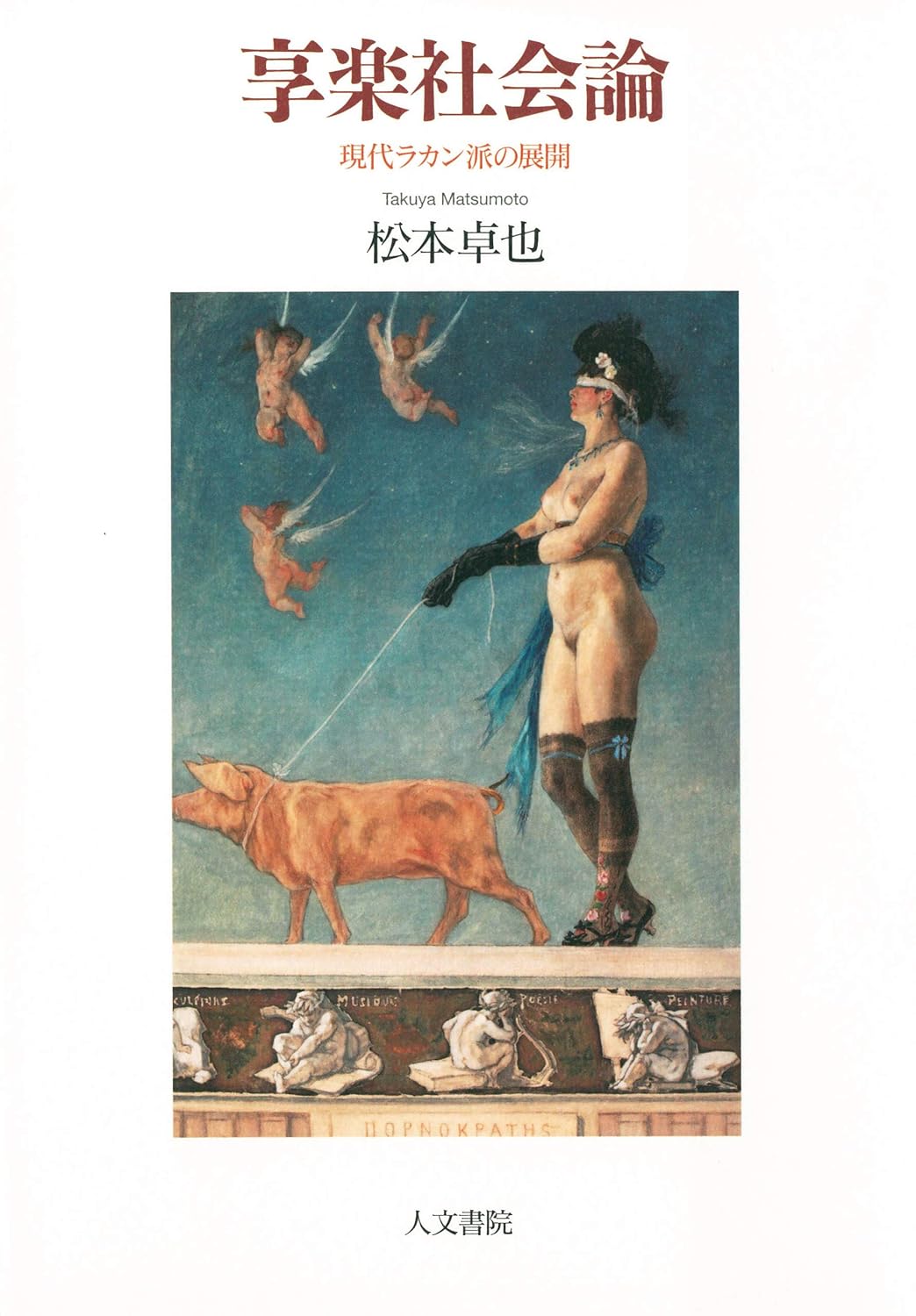



コメント